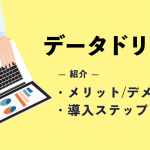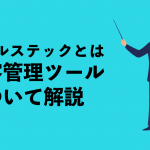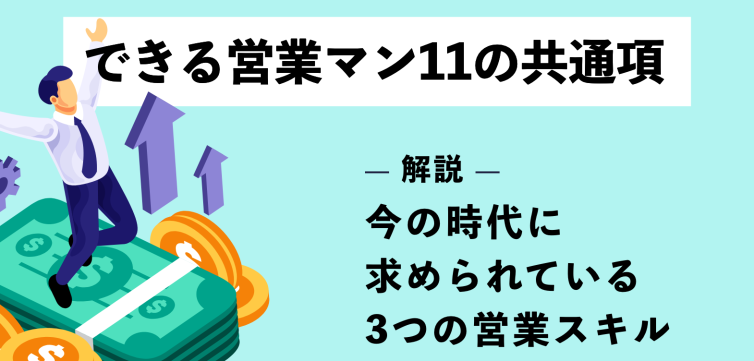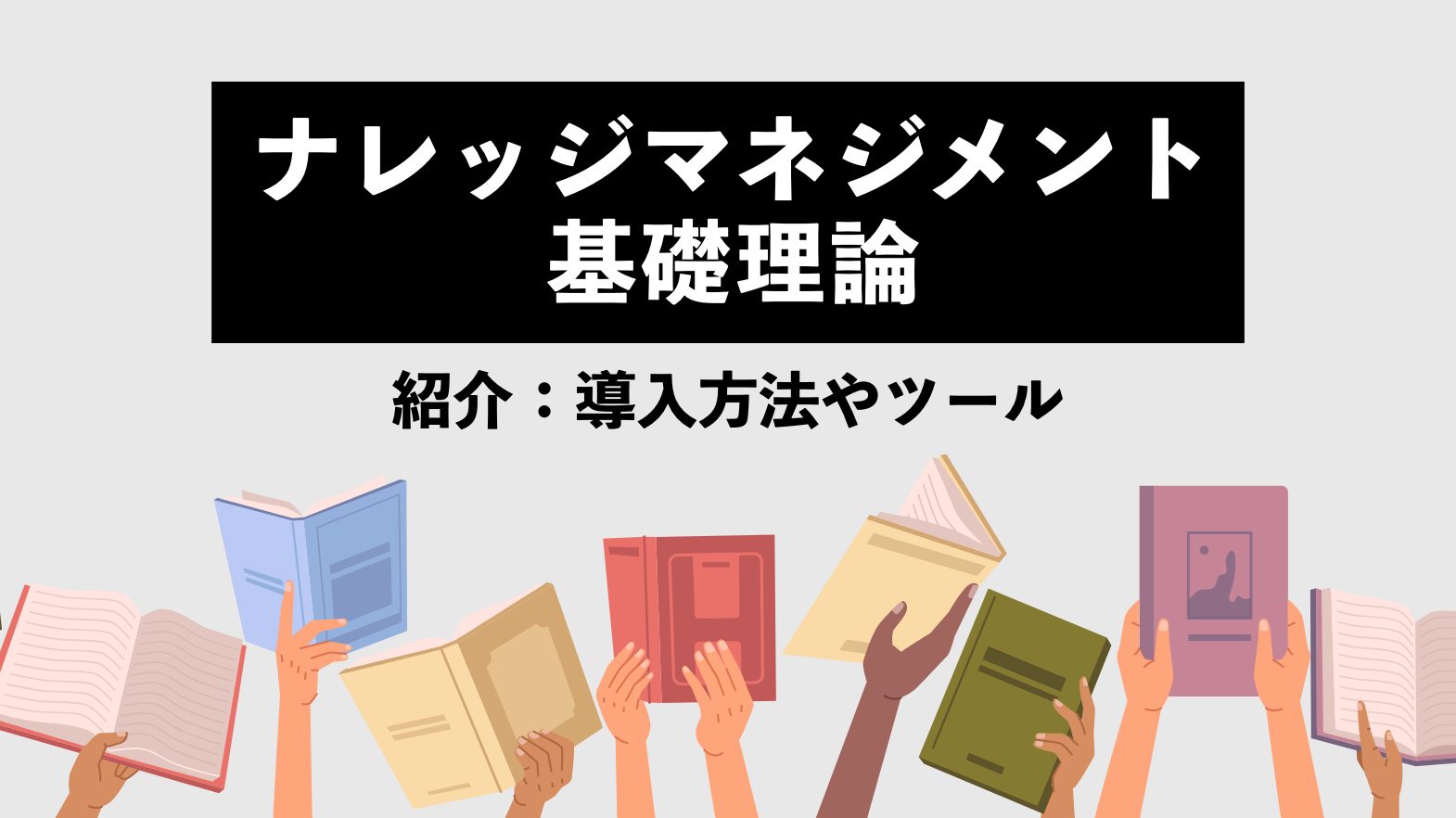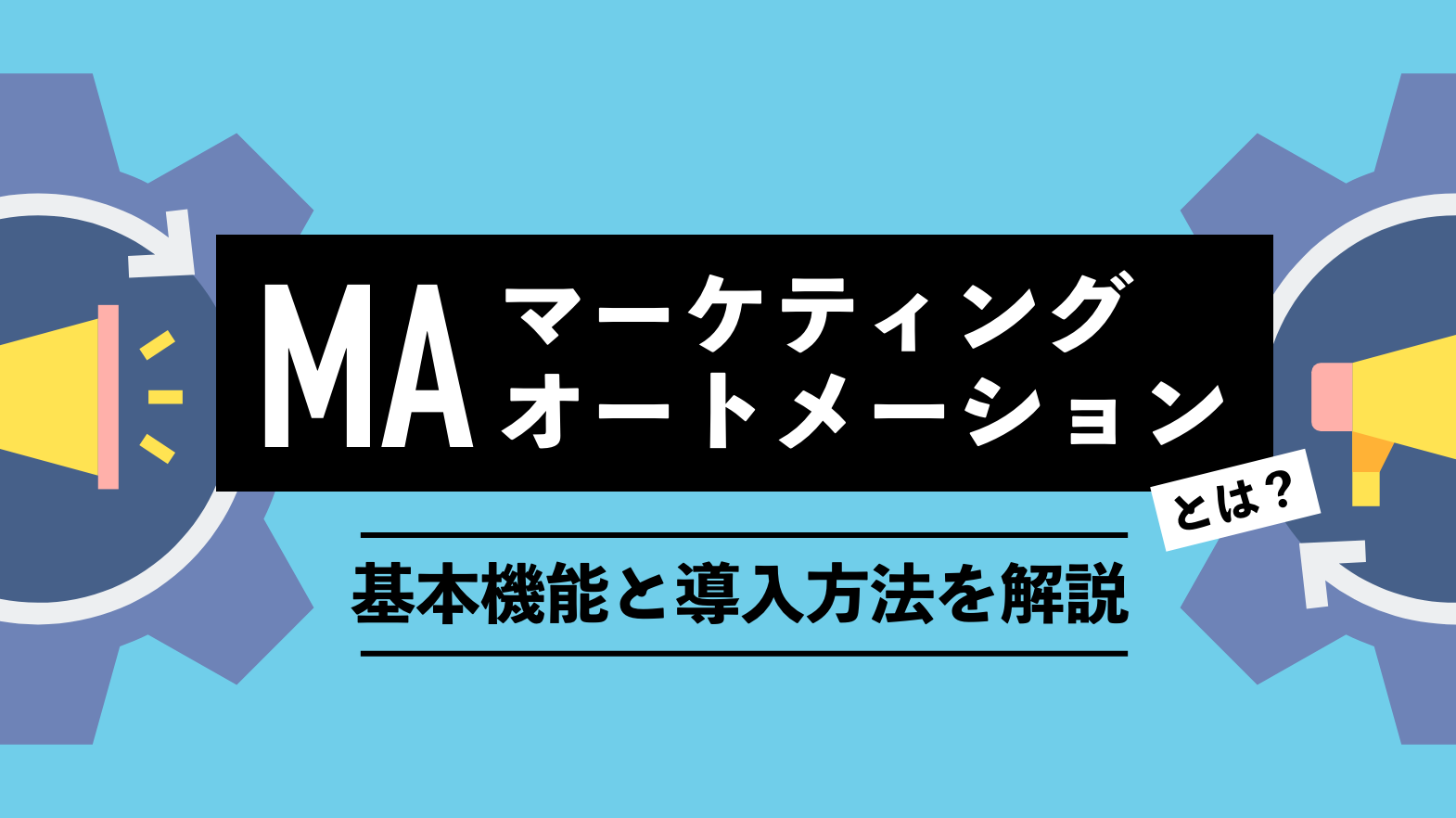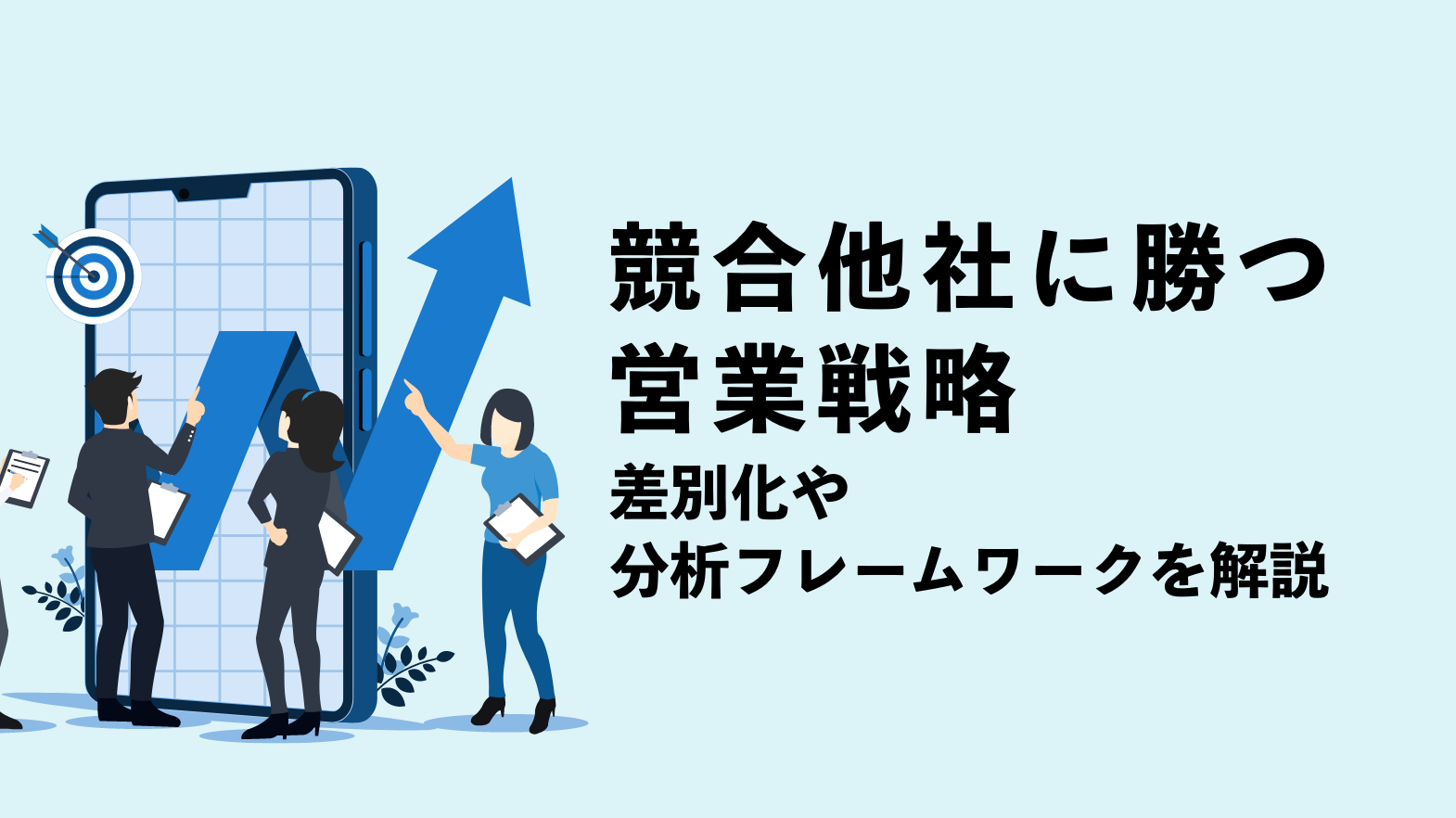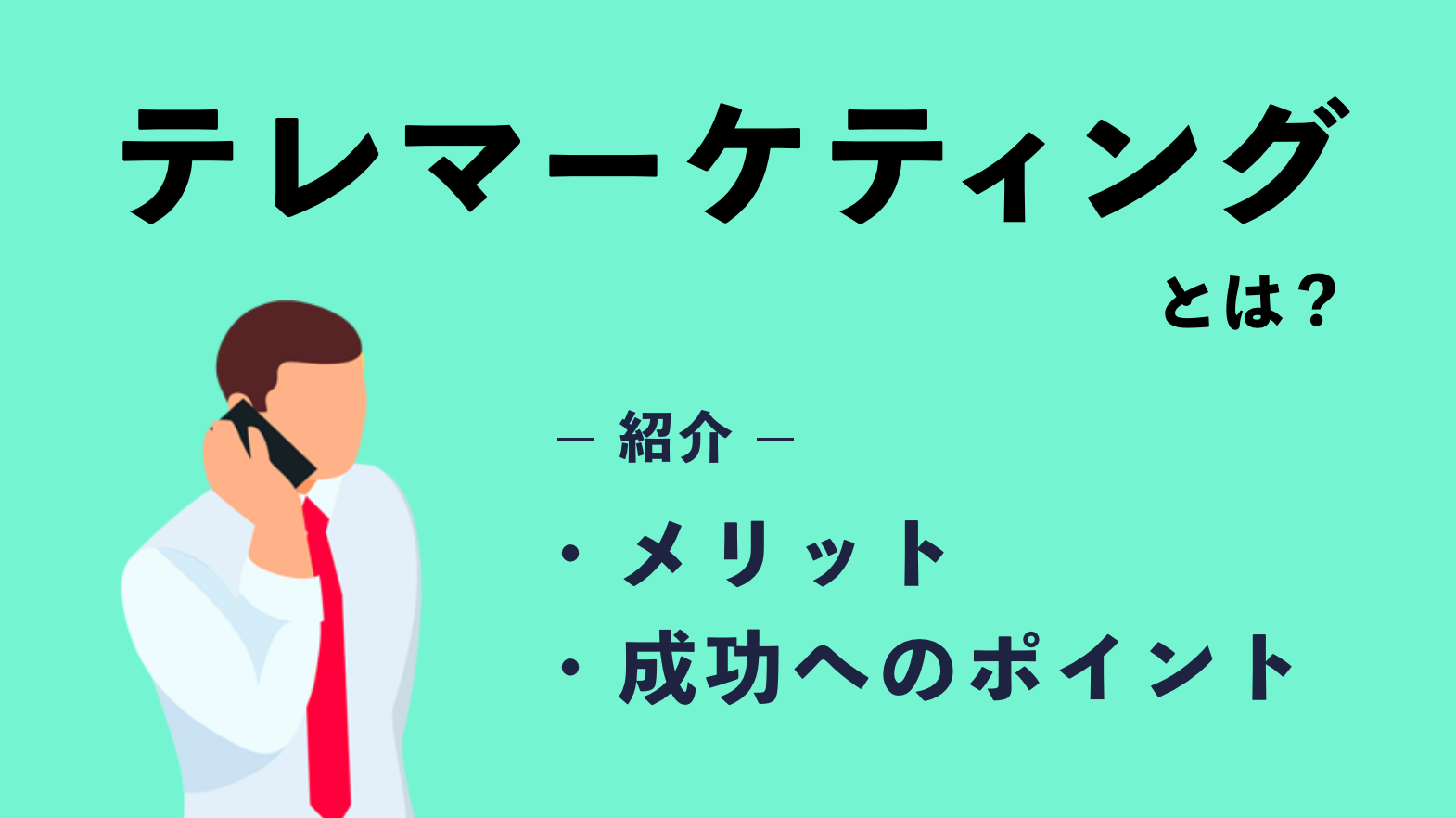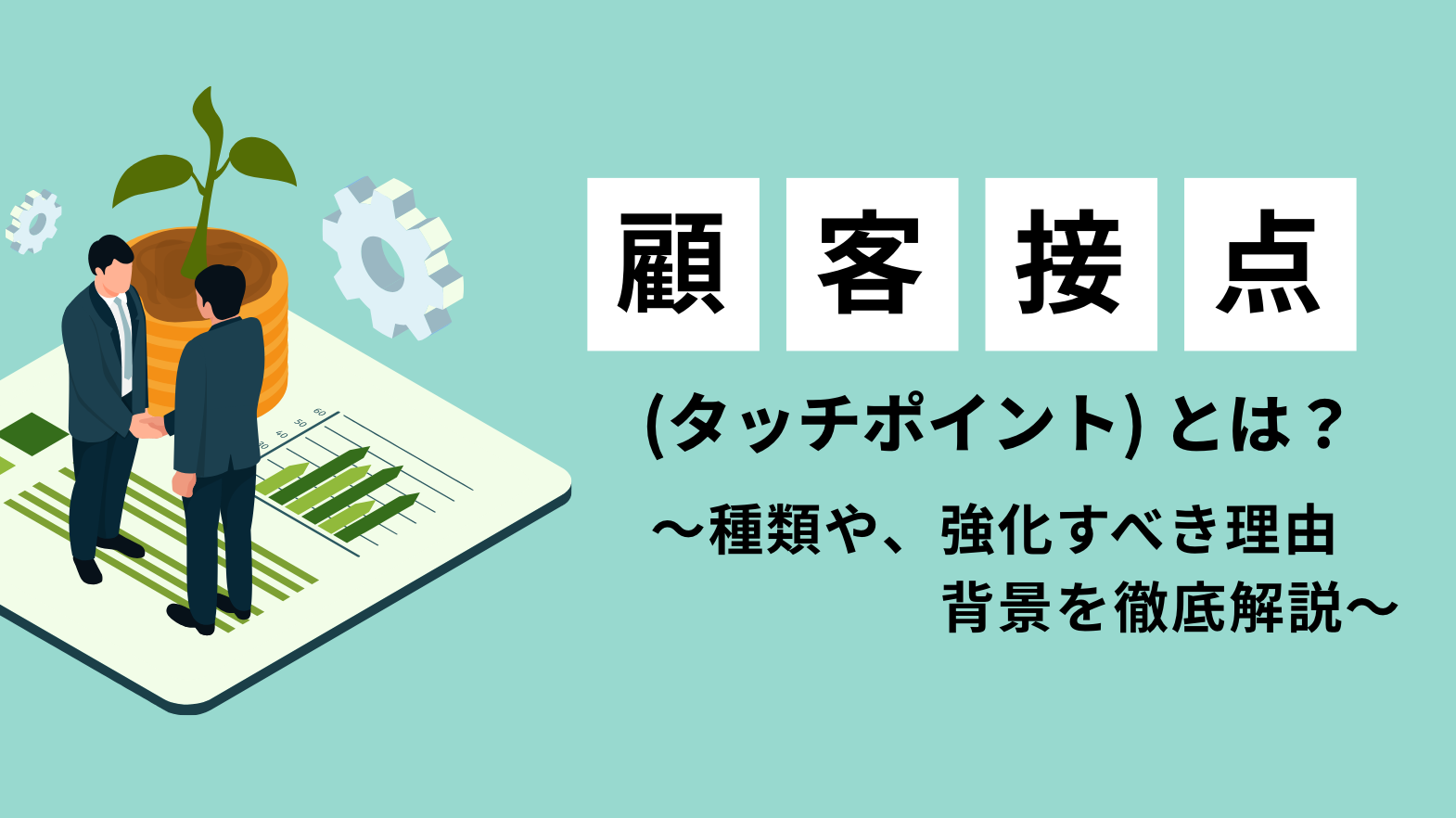マーケティングとは|戦略の立て方や代表的な分析手法を解説【成功の鍵は顧客理解】
自社の商品やサービスを販売し、安定的に利益を獲得するには、顧客が自然に商品やサービスを購入したくなるような仕組みを作る必要があります。
マーケティングの本質は「どのターゲットにどのような商品やサービスを届ければ、よろこんでもらえるのか」を追求し、ユーザーに商品を届ける導線を組み立てることです。
本記事では、マーケティングの意味や戦略の立て方、市場の分析方法について徹底解説します。
このページのコンテンツ
マーケティングとは|概要を解説

まず、マーケティングについて言葉の意味や、セールスとの違いなどについて解説します。
マーケティングは「商品やサービスを販売する導線をつくること」
マーケティングとは、商品やサービスを販売するための導線を作ることです。商品やサービスを顧客に届けるには、ニーズに合わせて製品開発や販売戦略を立てる必要があります。
また今の時代は、YouTubeやInstagramなどのSNSを駆使し、効果的に商品やサービスの魅力を訴求することが求められます。
「いかにして効率よく商品やサービスを売るか」を考え、実行することがマーケティングの本質といえるでしょう。
マーケティングとセールスのちがい
マーケティングとセールスは、どちらも売上を伸ばすことを目的としていますが、その役割は明確に異なります。
マーケティングは、顧客のニーズを把握し、商品やサービスの開発や価格設定、プロモーションなどを通じて、商品やサービスを販売する導線をつくることです。一方、セールスは、マーケティングによって引き付けられた潜在的な顧客を実際の購入に結びつける活動を指します。
つまり、マーケティングは顧客を集めるための「種まき」であり、セールスは「収穫」の役割を担っているといえます。
たとえば、新商品の発売に際してターゲット層を絞り込み、効果的な広告宣伝を展開するまでがマーケティングです。その後、実際に顧客と接触し、商品の購入を促して成約につなげる活動がセールスというように分けられます。
継続的に利益を出し続けるためには、マーケティングとセールスが互いに連携する体制を整える必要があります。
マーケティングの種類
マーケティングには、大きく分けて「マスマーケティング」と「ターゲットマーケティング」の2種類があります。両者のちがいは、以下のとおりです。
| 種類 | 手法 |
| マスマーケティング | 不特定多数の顧客を対象とし、テレビCMや新聞広告などを通じて、広く商品やサービスをアピールする手法 |
| ターゲットマーケティング | 特定の顧客層を対象とし、そのニーズに合わせた商品開発やプロモーションを行う手法 |
高級車メーカーは、富裕層をターゲットに品質や快適性をアピールするターゲットマーケティングを展開しています。一方、日用品メーカーは、幅広い顧客層を対象に、価格の安さや利便性を訴求するマスマーケティングを行っています。
このように、商品やサービスの特性、ターゲット層によって、適切なマーケティング手法を選択することが重要です。
また、ネットがインフラとして社会を支えるようになった現代においては、Webを用いたマーケティングも活発になっています。オンラインのみで実施されるマーケティングには、以下のような種類があります。
| 種類 | 手法 |
| インバウンドマーケティング | 潜在顧客を惹きつけ、自然に製品・サービスに興味を持ってもらうマーケティング手法。価値のある情報やコンテンツの提供により、顧客との長期的な関係構築をめざす |
| SNSマーケティング | ソーシャルメディアを活用したマーケティング手法。X(旧Twitter)やFacebook、Instagramなどのプラットフォームを通じて、ユーザーとのコミュニケーションを図り、ブランド認知度の向上や商品・サービスの販促を行う |
| アフィリエイトマーケティング | 自社の商品やサービスを第三者に紹介してもらい、成果に応じて報酬を支払うマーケティング手法。成果報酬型のため、広告費用を効果的に管理できるのも魅力 |
「自社のマーケティング戦略において、どの手法が顧客にアプローチしやすいのか」を考えながらマーケティング戦略を組む必要があります。
この先も時代の流れにともなって、新たなマーケティング手法が生まれるでしょう。
マーケティング戦略の立て方
次に、マーケティング戦略の立て方について解説します。
売りたい商品やサービスが属しているマーケットやねらっている顧客層に合わせてマーケティングのやり方を調整する必要があります。自社の状況に合わせて、正しいマーケティング戦略を構築していきましょう。
市場を調査する
マーケティング戦略を立てるうえで、はじめに取り組むべきことは市場調査です。市場調査では、自社の商品やサービスに対する潜在的な需要や、競合他社の動向を把握します。
具体的には、顧客アンケートやインタビュー、ウェブ上の口コミ分析などを通じて、顧客のニーズや満足度を探ります。
また、競合他社の商品やサービス、価格設定、プロモーション方法などを詳しく分析し、自社の強みや弱みを明確にすることも大切です。
市場調査を通じて得られた情報を元に分析すれば、自社の商品やサービスの改善点や、新たな事業機会を見出すきっかけをつかめるでしょう。
ターゲットを決める
市場調査を行ったあとは、自社が重点的にアプローチするべき顧客層であるターゲットを決めます。ターゲットを決める際は、市場調査で得られた顧客ニーズや競合他社の動向を踏まえ、自社の強みを最大限に活かせる層を選びましょう。
高品質な商品を提供している企業であれば、品質にこだわる富裕層をターゲットに設定するのが効果的です。一方、低価格を武器にしている企業なら、価格に敏感な顧客層をターゲットとするのが一般的でしょう。
ターゲットを明確にできれば、商品開発や価格設定・プロモーション活動など、あらゆるマーケティング施策を最適化できます。
広告宣伝活動に着手する
ターゲットが決まったら、いよいよ広告宣伝活動に取り組みます。このステップで、ターゲット層に効果的にアプローチできる媒体を選びましょう。
たとえば、若者向けの商品であればX(旧Twitter)やInstagram、YouTubeなどのSNSを活用するのが効果的です。一方、シニア層向けの商品なら、新聞や雑誌などの伝統的な媒体はもちろん、テレビCMも活用できます。
また広告宣伝のメッセージは、ターゲット層の関心事や価値観に合わせて文言を考えなくてはいけません。
もし、30代の働く女性をターゲットにした化粧品を宣伝するなら、時短しつつ効果的に肌をケアする方法に関心があると推測できます。ニーズを元に宣伝メッセージを考えると「忙しい日々でも、わずか1分で完了する集中ケア」というような文言にすれば、ターゲットに刺さる可能性が高くなるでしょう。
このように、宣伝文句はユーザーニーズから逆算して設定すると、マーケティング効果を得やすくなるのです。
マーケティングの効果を検証する
広告宣伝活動を展開したら、その効果を検証し、次回以降の宣伝や広告の戦略に活かしましょう。
具体的には、売上高や利益率、ウェブサイトのアクセス数など、さまざまな指標を用いて、マーケティング施策の成果を評価します。評価の結果、効果の見られない施策については、すみやかに改善したり中止の判断をしたりする必要もあるでしょう。
PDCAサイクルを回すことで、マーケティング戦略の最適化を図っていくことが大切です。
マーケティングにおける代表的な分析手法

ここでは、マーケティング戦略を考える際に使える分析手法を5つ紹介します。ぜひ活用してみてください。
3C分析
3C分析は、市場・顧客(Customer)、競合他社(Competitor)、自社(Company)の3つの視点から、市場環境を分析する手法です。
マーケティング戦略を立てるには、市場を取り巻く外部環境と社内の環境の双方を分析する必要があります。3C分析では、内部環境と外部環境を市場・顧客、競合、自社の3つに分けて調べていきます。
| 分析 | 手法 |
| 市場・顧客分析 | 顧客のニーズや購買行動、満足度などを詳しく調べ、効果的なアプローチ方法を探る |
| 競合分析 | 競合他社の商品やサービス、価格戦略、販売チャネルなどを分析し、自社の差別化ポイントを見出す |
| 自社分析 | 自社の強みや弱み、経営資源などを洗い出し、競争優位性を明確にする |
3C分析を通じて、自社の立ち位置や課題を明らかにし、競合他社にはない自社の強みを明確にすれば、どの領域で戦っていけば良いかが見えてくるでしょう。
3C分析についてより詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
参考:3C分析とは?ビジネスのための顧客・自社・競合の分析方法
4P分析
4P分析は、製品(Product)、価格(Price)、流通(Place)、販売促進(Promotion)の4つの視点から、マーケティング施策を最適化するために使われる手法です。
各項目の分析ポイントは、以下のとおりです。
| 分析 | 手法 |
| 製品 | 自社の商品やサービスの特徴や品質、パッケージデザインなどを見直し、顧客ニーズとのマッチングを図る |
| 価格 | 競合他社の値段設定や消費者が許容できる価格帯を考慮しながら、最適な価格設定を行う |
| 流通 | 販売チャネルの選定や物流網の構築など、商品やサービスを効率的に届ける方法を検討する |
| 販売促進 | 広告宣伝や販売促進キャンペーンなど、効果的なプロモーション施策を立案する |
4P分析を活用すれば、自社の商品やサービスの強みを最大限に活かしつつ、顧客ニーズに合わせたマーケティング施策を設計できるでしょう。
4P分析についてより詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
参考:4P(マーケティングミックス)とは? 営業戦略に活かす方法も解説!
SWOT分析
SWOT分析は、自社の強み(Strength)、弱み(Weakness)、機会(Opportunity)、脅威(Threat)を分析する手法です。各分析内容は、以下のとおりです。
| 分析 | 手法 |
| 強み分析 | 自社の独自性や競争優位性を洗い出し、差別化戦略に活かす |
| 弱み分析 | 自社の課題や改善点を明らかにし、対策を講じる |
| 機会分析 | 市場の成長性や新たなニーズの発見など、事業拡大のチャンスを探る |
| 脅威分析 | 競合他社の動向や法規制の変更など、事業に影響を及ぼしかねないリスク要因を特定する |
主に、既存事業の改善点を発見したり、新規事業における将来的なリスクの評価に役立つ手法といえます。SWOT分析を行えば、自社を取り巻く環境を多角的に評価し、適切な戦略を立てやすくなるでしょう。
SWOT分析についてより詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
PEST分析
PEST分析は、政治(Political)、経済(Economic)、社会(Social)、技術(Technological)の4つの視点から、マクロ環境を分析する手法です。自社を取り巻く外部環境の変化が、将来的にどのような影響を与えるのかを予測できます。
各項目の詳細は以下のとおりです。
| 分析 | 手法 |
| 政治 | 政府の政策や規制の変更が、自社の事業に与える影響を予測する |
| 経済 | 景気動向や為替レート、原材料価格の変動など、経済的な要因を考慮する |
| 社会 | 人口動態や消費者の価値観の変化、ライフスタイルの多様化など、社会的なトレンドを捉える |
| 技術 | 新技術の登場や既存技術の陳腐化など、技術革新が自社の事業に及ぼす影響を見きわめる |
PEST分析を行う際は、分析すること自体が目的になってしまわないよう注意が必要です。最終的には、分析結果をもとに事業戦略に落とし込むことが目的であることを見失わないようにしましょう。
PEST分析についてより詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
参考:PEST分析とは?目的や分析のやり方、注意点などを徹底解説
STP分析
STP分析は、市場の細分化(Segmentation)、ターゲット市場の選択(Targeting)、自社の立ち位置の決定(Positioning)の3つのステップで市場を分析し戦略を立てる手法です。
| 分析 | 手法 |
| 市場の細分化 | 市場を特定の基準で細分化し、顧客ニーズや購買行動の違いにもとづいて、いくつかの群に分ける |
| ターゲット市場の選択 | 市場の細分化で分けた顧客群の中から、自社が重点的にアプローチするべき層を選定する |
| 自社の立ち位置の決定 | 選定したターゲット層に対して、自社の商品やサービスがどのような特徴や価値を提供するのか、競合他社との差別化ポイントは何かを明確にする |
STP分析を通じて自社の強みを活かせる市場を見つけ出せれば、勝てるマーケティング戦略を創出できるでしょう。
また、4P分析やSWOT分析などと組み合わせれば、より多角的な戦略の立案につながります。
STP分析についてより詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
参考:STP分析とは?やり方や注意点、活用事例を解説【マーケティング戦略】
マーケティングを成功させるために外せないポイント
市場を分析し、綿密に戦略を立てたとしても、日々得られるデータからマーケティング施策を調整していかないと、継続的な成長は見込めません。ここでは、マーケティングを成功させるために欠かせない考え方を3つ紹介します。
顧客データを蓄積して今後の施策に活用する
マーケティングを成功させるには、顧客データを蓄積し、活用していく必要があります。顧客の購買履歴や属性情報、行動データなどを継続的に収集し、データベース化しましょう。
蓄積したデータを分析することで、顧客のニーズや嗜好、購買パターンなどを把握できます。
たとえば食品を扱う事業において、顧客の購買データから、頻繁に購入するユーザー層を特定できたとします。その場合、特定できた層に向けてSNSやメルマガで自社商品を用いたレシピやアレンジ方法を配信すれば、売上げアップが期待できるでしょう。
データにもとづいた商品開発や販促施策、顧客とのコミュニケーションはマーケティング施策の最適化に欠かせません。
アフターフォローを欠かさない
販売後のアフターフォローは、顧客満足度の向上やリピート購入の促進につながる重要な施策です。
具体的には、商品やサービスの使い方をサポートしたり、不明点や不満点に迅速に対応したりすることなどが挙げられます。
商品やサービスを購入してくれたユーザーに感謝の気持ちを込めたメッセージを送ったり、2回目以降の利用がお得になるような特典を配布したりする方法も、効果的なアフターフォローになるでしょう。
アフターフォローを通じて、顧客との長期的な関係を構築できれば、ファン化を促してリピーター数を確保できます。顧客との信頼関係を築いて満足度を高めることが、長期的に売上を安定させることにつながるでしょう。
顧客の満足度を高めるうえで重要な指標である「顧客エンゲージメント」について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
参考:顧客エンゲージメントとは?向上させる方法や成功事例とあわせて概説
マーケティングツールを導入する
マーケティング活動を効率化・自動化するために、各種ツールの導入が有効です。たとえば、以下のようなマーケティングツールが挙げられます。
| ツール | 概要 |
| CRMツール | 顧客データを一元管理 効果的なコミュニケーションを実現 |
| MAツール | メールマーケティングの最適化 見込み顧客の教育や子興味づけの配信を自動化 |
| SFAツール | 営業活動の見える化 営業プロセスの標準化 |
| Web解析ツール | サイト訪問者の行動を分析 サイト最適化やコンテンツマーケティングの最適化 |
適切なツールを選定し、運用体制を整えることで、マーケティング活動の効果をより高められるでしょう。
なお、MAツールの「esm marketing」を活用すれば、リード獲得からナーチャリングまでの導線を最適化できます。

営業 × マーケティングで受注率UPを実現!MAツール「esm marketing」はこちら
自社にマッチしたマーケティング施策を取り入れて売上を改善しよう
事業を安定的に成長させるために、効果的なマーケティング戦略を組み立てることは避けては通れない道です。
マーケティング施策が成功すれば、狙っているターゲット層に商品やサービスを届けられるだけでなく、顧客満足度も高い水準で安定します。そうなれば、売上や利益も上がっていくでしょう。
ただし、他社のマーケティングのやり方が自社にマッチしているとは限りません。そのため、市場を分析して自社商品の強みを再確認することで、自社に最適なマーケティング施策を考案する必要があるのです。