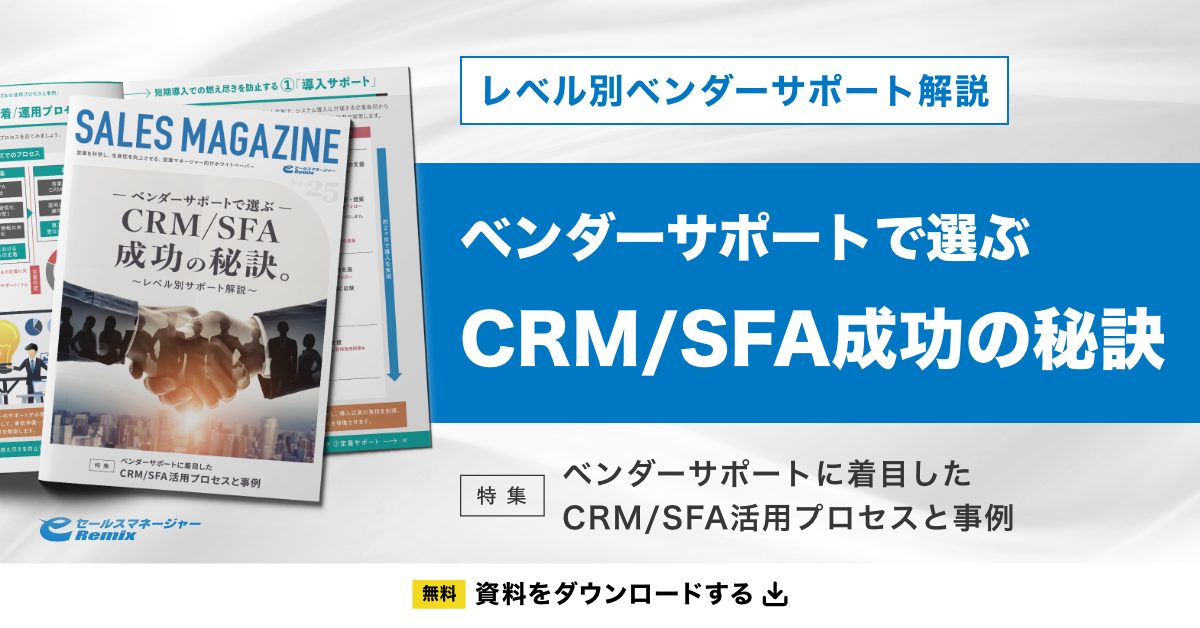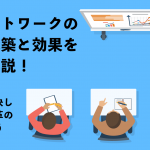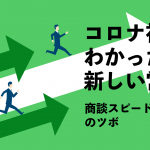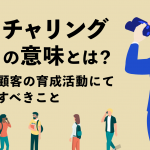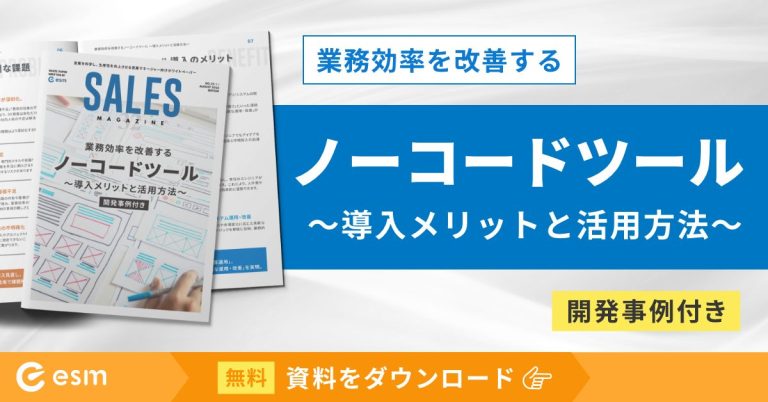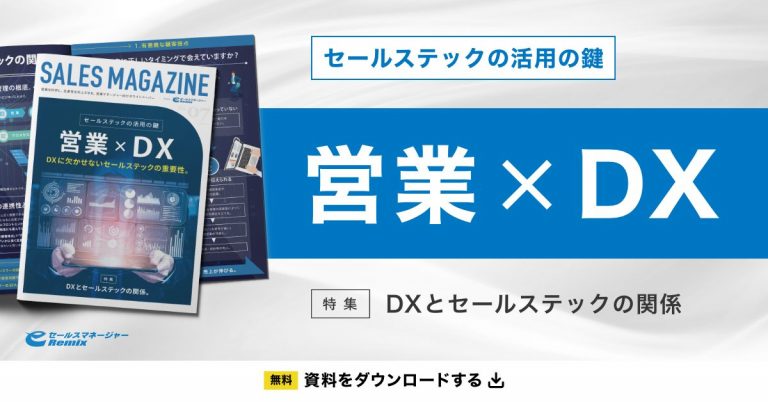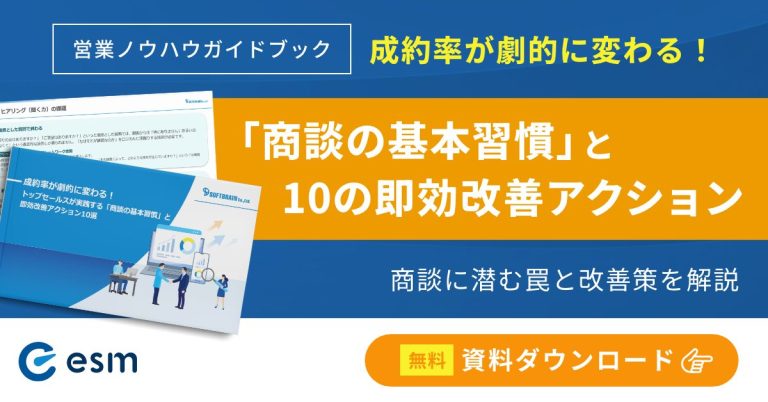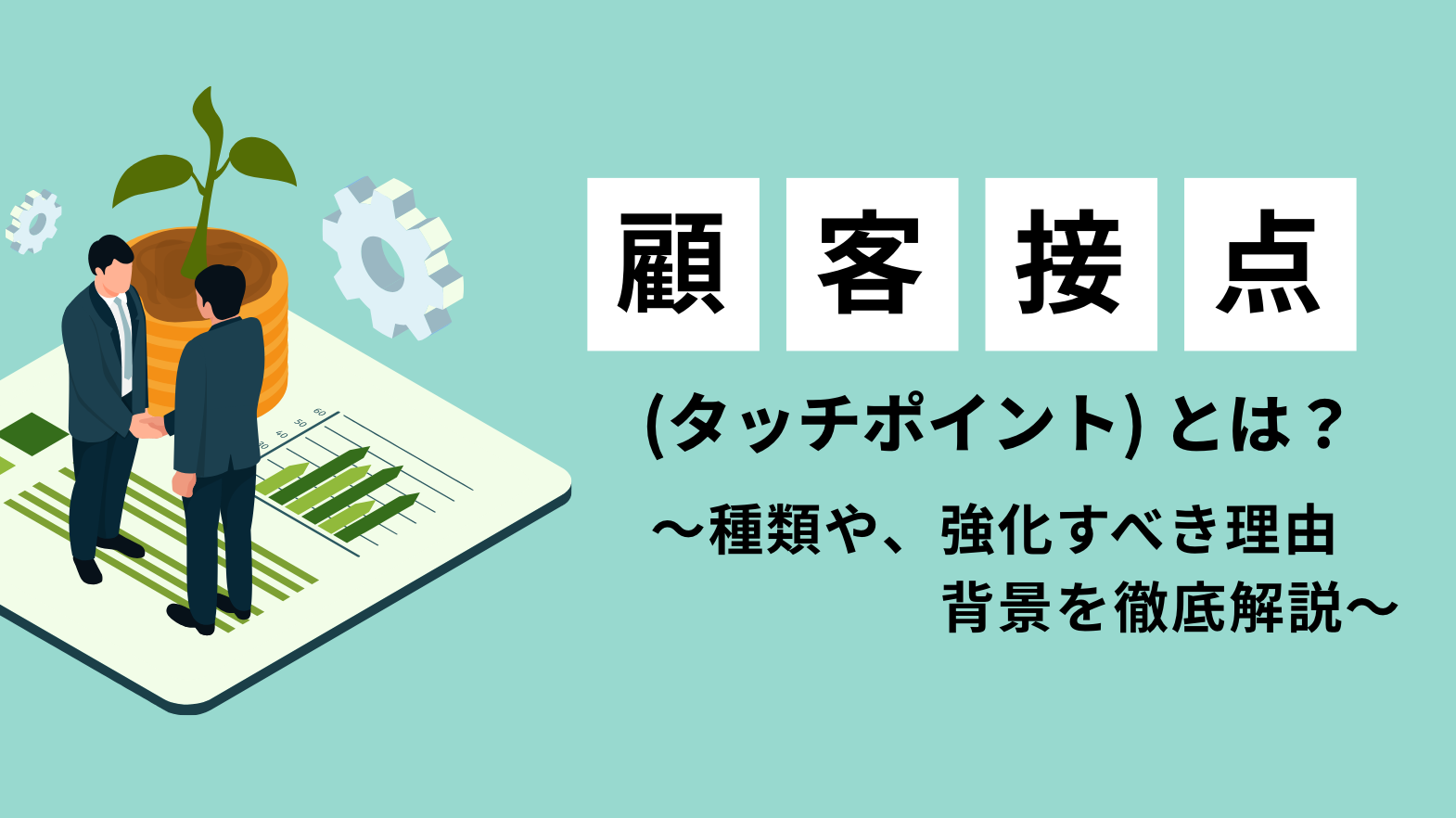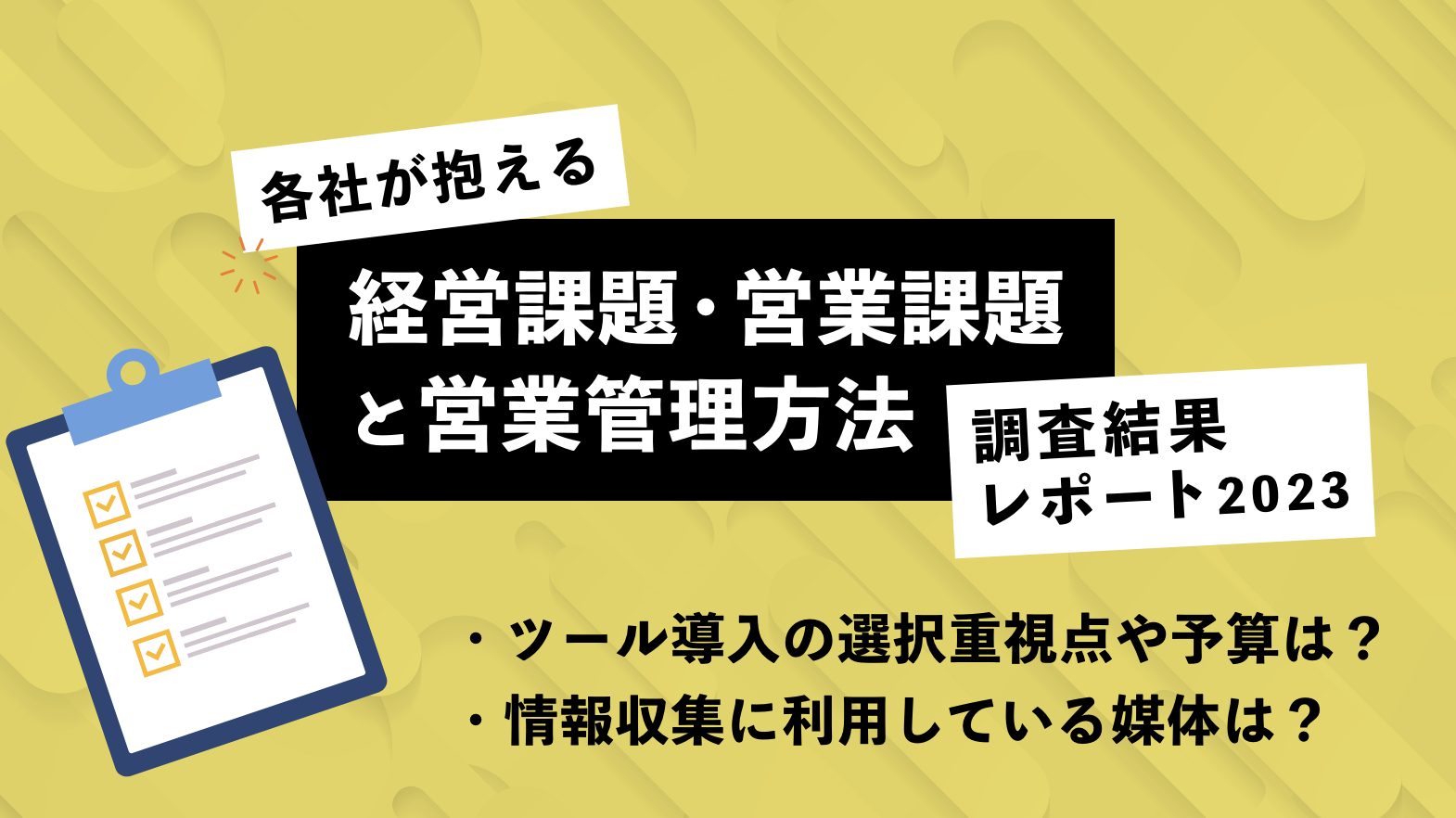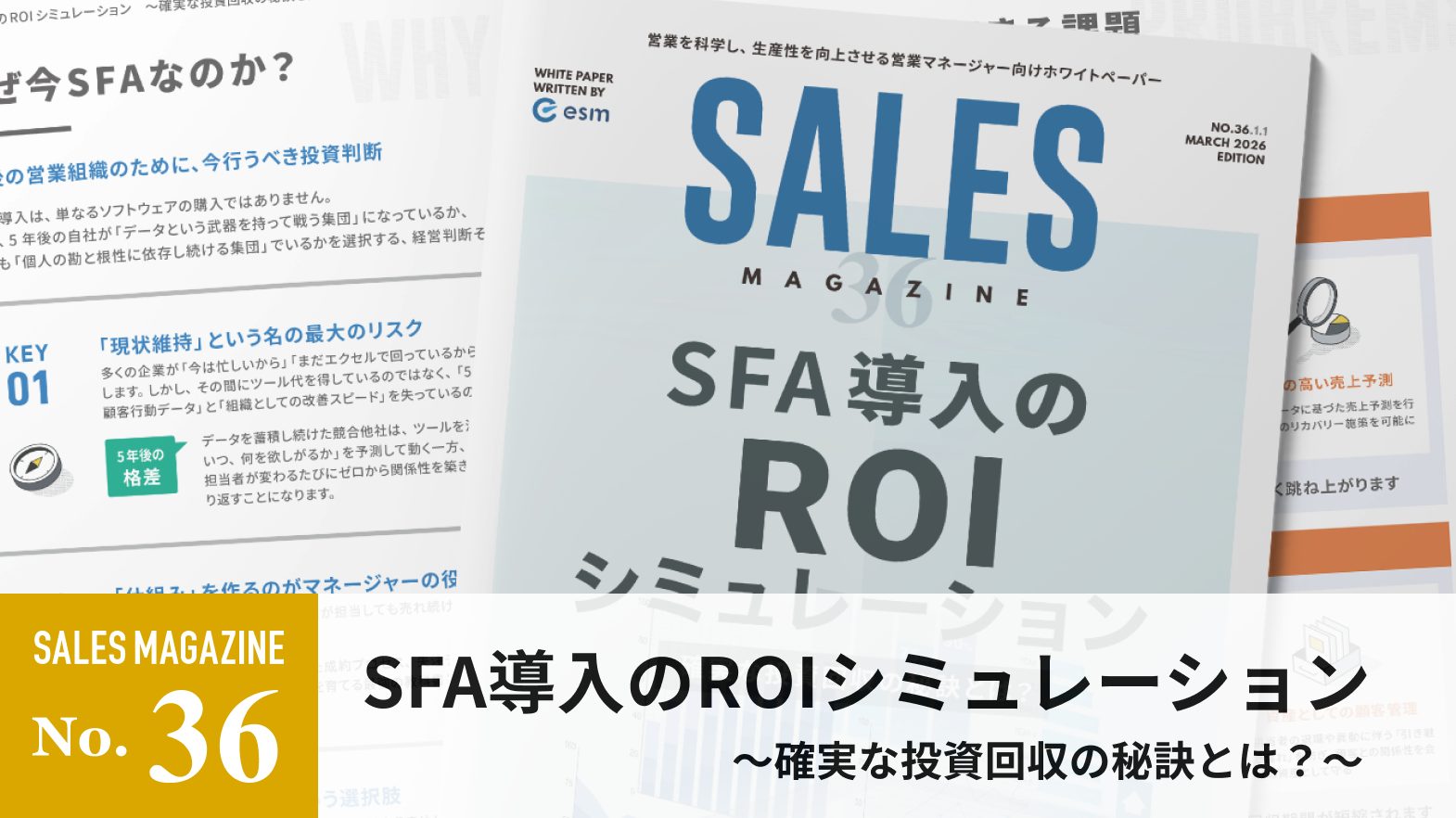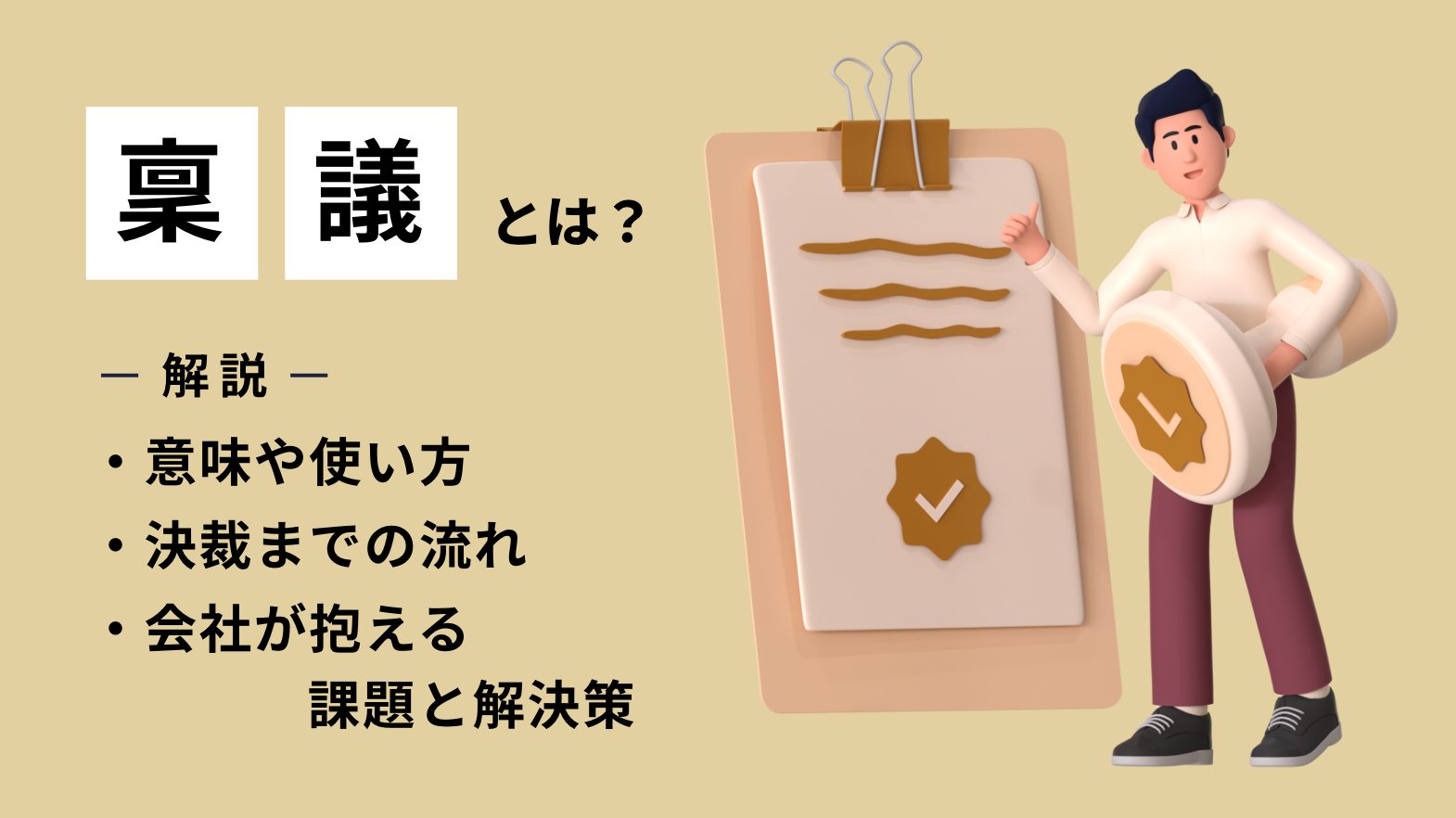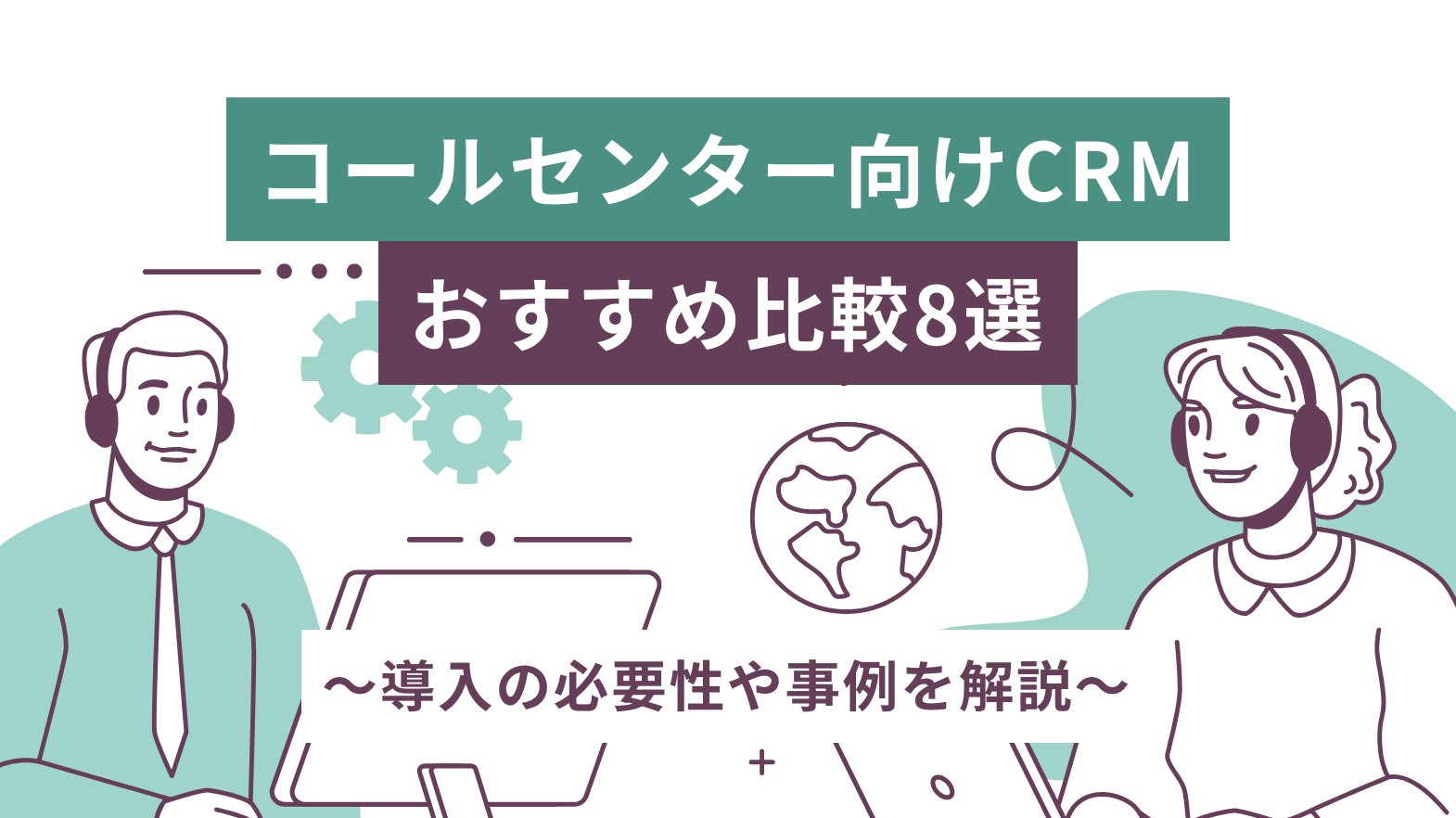顧客管理システム(CRM)15選!機能や導入メリット、選び方を解説
この記事では、顧客管理システム(CRM)のおすすめ15選と選び方、運用のポイントを解説します。エクセルによる顧客管理に課題を感じている方は、ぜひ参考にしてください。
このページのコンテンツ
顧客管理システム(CRM)とは?

顧客管理システム(CRM)は、お客様に関する情報を一つにまとめて管理し、その情報を活用するためのツールです。ただ情報を記録するだけでなく、お客様と長く良い関係を築き、商品の購入やサービスの利用を続けてもらうための手助けをします。
今では、ほとんどのお客様がネットを使って情報を調べ、購入を決める準備をしています。企業がアプローチするときには、すでに購入するかどうかが決定しているケースも少なくありません。この場合、お客様のニーズをよく理解し、適切なタイミングでアプローチする必要があります。
特に興味を持ってくれた可能性のある人との信頼関係を作り、選ばれる企業になるのが大切です。しかし、お客様の数が増えると、個別に対応するのは難しくなります。そこで役立つのがCRMです。
CRMを使えば、名前や連絡先以外にも、購入履歴やウェブサイトでの行動、問い合わせ内容などをまとめて管理できます。さらに、メールの自動配信などの機能を使って、一人ひとりに合った対応も可能です。CRMは、信頼関係を深めながら売上を拡大するための強力なサポートツールといえるでしょう。
顧客管理システム(CRM)が注目される背景
顧客管理システム(CRM)が注目される背景には、大きく顧客ニーズの多様化と市場競争の激化の2つがあります。
インターネットを介して大量の情報に簡単にアクセスできる環境が整ったことや、ライフスタイル・価値観の変化により、顧客ニーズは以前よりも幅広く、細分化しています。さらに、市場が成熟して同種の商品やサービスが市場に広まった結果、差別化が図りづらくなり、新規顧客獲得の難易度が上がっています。そこで、既存顧客をリピーターとして囲い込む重要性が増しました。
リピートしてもらうために必要なのが、顧客一人ひとりの興味関心や課題に合わせた提案や、きめ細かなフォローです。営業社員ごとに顧客情報を個別に管理していると、過去の購入履歴や問い合わせ内容などが追えません。
こうした課題の解決に役立つのが顧客管理システムです。顧客情報を一元管理し、担当者がすぐに活用できる体制を整えられることから、顧客管理システムの重要性が高まっています。顧客管理システムで蓄積した情報はマーケティングや営業戦略の立案に役立ち、収益拡大にもつながるでしょう。
顧客管理システム(CRM)と営業管理システム(SFA)の違い
CRMは顧客情報をまとめて管理し、会社のさまざまな活動に役立てるシステムです。お客様のニーズに基づいて売り込みやサポートを行い、満足度を高めることが目的です。
一方でSFAは、営業活動に特化したシステムです。商談の管理や営業報告の作成、知識の共有を通じ、営業の効率を上げて売上を伸ばします。どちらも顧客情報を扱いますが、利用目的と対象範囲が異なります。
参考:SFAとは?CRM・MAとの違いから機能、選び方まで解説
自作フォーマットやExcelによる顧客情報管理の課題
ExcelやGoogleスプレッドシートなどを使ってフォーマットを自作し、顧客管理に活用しているケースは少なくありません。実際、顧客が多くないうちは自作のフォーマットでも十分に機能します。自社仕様にアレンジが可能で、コストを抑えて管理できることが大きなメリットです。
しかし、顧客数や商談件数が増えてくると、自作フォーマットでは限界が生じ、以下のような問題が起こり始めます。
- 複数人で共有し入力している場合、最新情報がどれか分からなくなる
- 知りたい情報にすぐにアクセスしにくい
- 入力ルールを徹底していない場合、データの形式が揺れて検索性が落ちる
上記のような課題は、顧客管理システム(CRM)を導入することで解決します。CRMは、顧客情報や案件情報、商談の進捗管理や履歴などを一元的に蓄積・更新でき、複数人がリアルタイムでアクセスすることも可能です。検索性にも優れており、必要な情報を簡単に取り出せてすぐに次の行動に移れるので、時間的なロスが減らせるでしょう。
顧客管理システム(CRM)を導入するメリット
顧客管理システム(CRM)の導入には、次のようなメリットがあります。
営業やマーケティングの業務効率化につながる
エクセルで管理していた顧客情報をCRMに一元化することで、必要な情報を簡単に検索できるようになります。レポート作成にかかる時間も削減できるでしょう。
部署を越えてリアルタイムの顧客情報を共有できる
個人のパソコンや社内共有システムなど、顧客情報は社内に存在する複数の端末やフォルダに保存されています。それらの情報を一元化し、部署を問わずリアルタイムに編集・閲覧できる仕組みを構築すれば、情報共有が容易になります。
顧客満足度やLTV(生涯顧客価値)の向上が実現する
システムによって顧客情報を管理することで、顧客との適切でスピーディーなコミュニケーションが実現可能です。さらに、顧客のニーズにマッチする提案ができれば、顧客満足度の向上、ひいては売上アップにもつながります。
参考:LTV(ライフタイムバリュー)とは?意味や計算方法・向上させる施策をわかりやすく解説
顧客管理システム(CRM)を導入するデメリット
CRMにはさまざまなメリットがありますが、導入時に注意すべき点もあります。下記でCRMを導入するデメリットを解説します。
初期費用や維持費がかかる
CRM導入には初期費用と維持費がかかり、選んだ機能で金額は変わります。オープンソースなら費用を抑えられますが、機能を使いこなせない場合、費用が無駄になる恐れもあるため、コストパフォーマンスに優れたシステムを慎重に選びましょう。
成果を得るには時間がかかる
CRMは、お客様との良好な関係づくりを目指すツールです。関係構築には時間がかかるため、導入後すぐに効果が出るわけではありません。売上アップや業務効率化といった目に見える成果もすぐには得られない可能性があります。
データ入力を定着させる必要がある
CRMの効果を発揮するには、顧客情報などをシステムへ入力しなければいけません。しかし、新しいツールの利用を負担に感じる社員もいる可能性があります。入力作業が習慣化されないと、システムを導入した効果を十分に得られないため、活用を促す工夫や導入後のサポート体制づくりが必要です。
顧客管理システム(CRM)の機能
CRMには、基本となる情報管理から、分析、コミュニケーション、外部連携など、お客様との関係づくりを支援するための機能が備わっています。下記で、各機能の特徴と活用方法を詳しく解説します。
顧客情報管理機能
お客様に関する情報を1つのシステムで効率的に管理するCRMの基本機能です。名前や住所といった基本情報はもちろん、家族構成、問い合わせ内容、商談の記録など幅広いデータをまとめて管理できます。
必要な項目は自由に追加でき、会社の業務に合わせた使い方が可能です。蓄積された情報を活用し、きめ細かな対応や効果的な営業活動を実現できます。
問い合わせ管理機能
問い合わせ管理機能は、お客様からのメールやウェブフォームでの質問を自動で記録・整理できる便利な機能です。担当者はお客様の情報や過去のやり取りをすぐに確認でき、スピーディーな対応が可能になります。
また、同じような質問には定型文を用意したり、よくある質問をFAQとしてまとめたりすることで迅速に返答できます。
メール配信機能
メール配信機能は、お客様への情報発信を自動化し、効率的に行えるツールです。単発のメールから、定期的なメルマガ、特定の条件で送信されるステップメールまで、さまざまな形式で配信できます。メールの開封率やクリック率を追跡できるので、顧客との関係構築やビジネスの成果向上に役立てられます。
参考:メールマーケティングとは?メリットや基礎知識・実践手法を紹介
顧客分析機能
顧客分析機能は、お客様の購入履歴やウェブサイトでの行動を自動で分析し、購買パターンを可視化してくれる機能です。購入金額、利用頻度、最近の取引状況などの基準でお客様をランク分けします。
購入額の多いお客様も瞬時に見つけ出し、特別なサービスを提供することで、長期的な関係づくりが可能です。分析結果をもとに、それぞれのお客様の好みや行動に合わせたメール配信や商品の提案を実施できます。
外部サービス連携機能
外部サービス連携機能は、日常的に使用するGmailやSNSから、会計・在庫管理といった基幹システムまで、幅広いビジネスツールを繋ぐ機能です。異なるシステム間でデータのやり取りがスムーズになり、必要な情報をリアルタイムで共有できます。
検索・CSV出力機能
検索機能を活用すると、顧客名や業種、対応状況、商談ステータスなど複数の要素を組み合わせて絞り込み検索ができ、必要な情報をすぐに取り出せます。
CSV出力機能は、検索で絞り込んで抽出されたデータを一覧化し、Excelなど指定した形式に変換する機能です。別のシステムに取り込んだり、社内で共有したりする際に役立ちます。
顧客管理システム(CRM)を選ぶ際のポイント
CRMは、自社に合ったツールを見極めるのが大切です。ただ、具体的にどのようなポイントが重要なのか分からず、選定に悩む場合もあるでしょう。下記で、業務効率を最大化し、効果を十分に発揮してくれるCRMの選び方のポイントを紹介します。
使いやすいかどうか
CRMは多くの社員が日常的に使用するツールのため、使いやすさという観点は欠かせません。画面のレイアウトや入力のしやすさ、目的の情報へのアクセスのしやすさなどをしっかりチェックする必要があります。
特に重要なのが、直感的な操作が可能かどうかです。必要な情報や機能にスムーズにアクセスでき、各部署のニーズに合わせたカスタマイズができるシステムを選びましょう。CRMのサービスの中には、無料お試し期間が用意されているものもあるので、実際に触れて使い心地を確認するのも良い方法です。
必要な機能がついているか
CRMを選ぶ際、自社の課題を解決するための機能が含まれているかを確認するのも大切です。導入する目的を明らかにし、何を実現したいのかを具体的に考えましょう。例えば、顧客の購買履歴をマーケティングに活用したい場合、購買傾向の分析や新商品の提案機能が必要です。
さらに、データを視覚的に理解できるダッシュボード機能があると生産性アップにつながります。
また、商談管理や案件の進捗状態可視化といったSFAの機能を併せ持つシステムを選べば、顧客管理だけでなく、営業活動そのものの効率化が可能です。顧客のフォロー漏れを防ぎやすくなり、担当者の活動内容や商談履歴、案件進捗状況などのデータから次に取るべきアクションを判断しやすくなるため、営業の精度を高められるでしょう。
ただ、使わない機能が多ければ使いづらくなるため注意が必要です。自社の目標につながる機能を持つシンプルなシステムを選びましょう。
サポート体制の充実さ
CRMの導入を成功させるには、サポート体制の充実さもポイントです。導入時に、初期設定やデータ移行、操作研修などのサポートが必要です。さらに運用開始後は、電話やメールでの問い合わせ対応、トラブル発生時の迅速な解決、システムの使い方に関するアドバイスなども重要になります。
継続的なサポートがあれば、安心してシステムを活用できるでしょう。また長期的な視点で、運用ノウハウや担当者を育てるサポートも求められます。導入前に各社のサポート内容を見比べることが大切です。
外部システムと連携できるか
CRMと外部システムの連携は、業務効率を向上させるために欠かせません。例えば、社内チャットツールとつながれば、顧客に連絡するタイミングが自動で通知されます。普段使うツールで必要な情報を確認できれば、見落としを防げます。
また、マーケティングツールや基幹システムと連携すれば、顧客情報をまとめて管理できます。データの被りや転記ミスも防げるようになり、部門を超えた情報共有もスムーズです。社内の売上管理や在庫管理システムと組み合わせれば、より正確なお客様への対応も実現できます。
料金は適正か
CRMの料金設定は、機能の豊富さや利用人数によって変わります。初期費用と月額利用料に加え、システムの保守費用や社員研修費用なども検討しなければいけません。料金を検討する際は、以下の点をチェックしましょう。
- 必要最低限の機能は何か
- 実際の利用人数はどれくらいか
- 将来的な拡張の可能性
- 業務効率化による経費削減効果
機能性に優れたシステムが自社に最適とは限りません。システムの入れ替えは、時間とコストが大幅にかかるため、慎重な選択が求められます。
企業におすすめの顧客管理システム(CRM)15選
ここでは、企業にぜひ導入を検討いただきたい、おすすめのCRM15選を紹介します。企業規模や目的に応じて、自社に合ったCRMを探してみてください。なお、価格情報は2025年1月時点のものです。
1. eセールスマネージャー(ソフトブレーン株式会社)

【形態】クラウド型
【価格】Basic 月額3,500円/1ユーザー
Enterprise 月額12,500円/1ユーザー
【特徴】中小・大企業向け
従業員100人以下の中小企業から、大企業まで対応できるツールです。CRMツールには海外製のものが多くありますが、eセールスマネージャーは日本製で、日本語を母国語とするユーザーが利用しやすい設計になっています。
アフターフォローにも定評があり、システムの定着・運用までサポートしてくれます。
「eセールスマネージャー」で即実現!~CRM/SFAの活用方法のご紹介~
2. Sales Cloud(株式会社セールスフォース・ジャパン)

【形態】クラウド・オンプレミス型
【価格】Essentials(10ユーザーまで)月額3,000円/1ユーザー
Professional 月額9,600 円/1ユーザー
Enterprise 月額19,800 円/1ユーザー
Unlimited 月額39,600 円 /1ユーザー
【特徴】大企業向け
顧客関係構築の強化による商談成立(カスタマーサクセス)を第一としているCRMです。「Custumer360」という名称で、営業支援、カスタマーサービス、マーケティングやコマース、インテグレーションなど、あらゆる情報の一元的な管理が可能です。
Sales Cloudは、多機能で高品質なCRMである一方、費用が高額で使いこなすのが難しい一面があります。予算が豊富にあり、ITスキルを持った人材が社内にいる大企業におすすめのツールです。
3. Dynamics 365 Sales(マイクロソフト株式会社)

【形態】クラウド・オンプレミス型
【価格】Dynamics 365 Sales Professional 月額8,125円/1ユーザー
Dynamics 365 Sales Enterprise 月額11,875円/1ユーザー
Dynamics 365 Sales Premium 月額16,875円/1ユーザー
【特徴】大企業向け
AIを活用した営業案件スコアリングやガイダンスによって、顧客に対して適切なアプローチが可能になります。
Dynamics 365 Salesを含む「Microsoft Dynamics 365」は、国内外で豊富な導入実績があり、営業・マーケティング、コマース、財務、サプライチェーンなど、包括的な機能を持つ管理ツールです。OfficeアプリケーションやTeamsなど、マイクロソフト社が提供するほかのサービスとの連携もできます。
4. Mazrica Sales(株式会社マツリカ)

【形態】クラウド型
【価格】Starter 月額27,500円~/5ユーザー
Growth 月額110,000円~/10ユーザー
Enterprise 月額330,000円~/20ユーザー
【特徴】中小企業向け
Mazrica Sales(旧Senses)は、顧客管理・案件管理・行動管理・名刺管理などの情報を一元管理できるツールです。案件をカード形式で管理できるのが特徴で、直感的な操作が可能です。データを分析し、受注率や進捗率が表記されるレポート機能も搭載されています。
5. Kintone(サイボウズ株式会社)

【形態】クラウド型
【価格】ライトコース 月額780円(年額9,170円)/1ユーザー
スタンダードコース 月額1,500円(年額17,640円)/1ユーザー
【特徴】中小企業向け
直感的に操作しやすいツールで、機能のカスタマイズも可能です。コストも月額780円からと、リーズナブルに利用できます。
6. Zoho CRM(ゾーホージャパン株式会社)

【形態】クラウド型
【価格】スタンダード 月額1,680円(年間契約)/1ユーザー
プロフェッショナル 月額2,760円(年間契約)/1ユーザー
エンタープライズ 月額4,800円(年間契約)/1ユーザー
アルティメット 月額6,240円(年間契約)/1ユーザー
【特徴】中小企業向け
Zoho CRMは、AI機能が搭載されたCRM/SFAツールです。営業の業務内容を蓄積していくと、AIがタスクを分析して効率のよい進行方法を提案してくれます。リード・顧客・商談情報の一元管理から、リードスコアリング、メール分析まで、幅広い機能が備わっていながらも低価格で利用できるのが魅力です。
7. Knowledge Suite(ブルーテック株式会社)
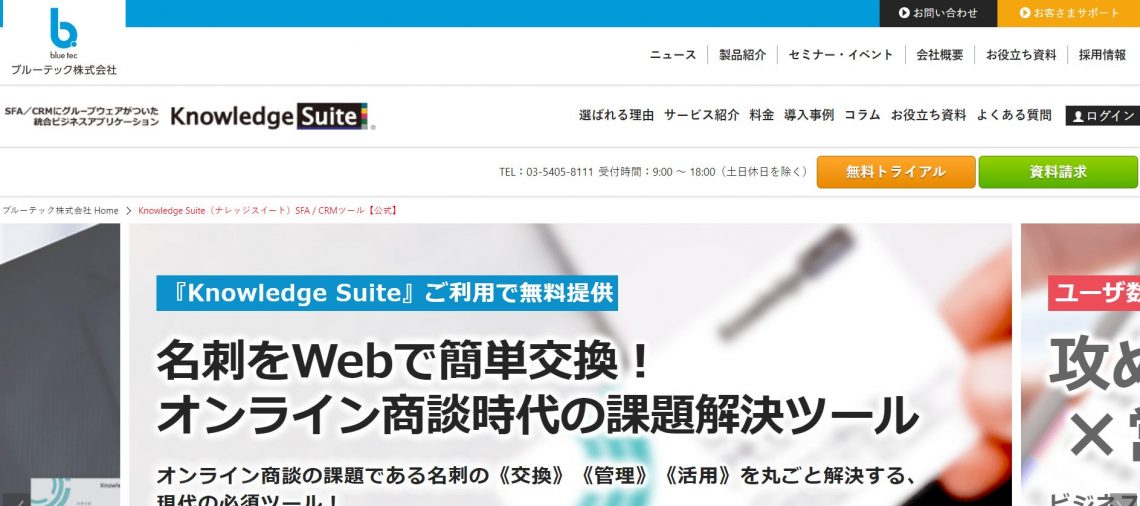
【形態】クラウド型
【価格】グループウエア 月額10,000円
SFAスタンダード 月額50,000円
SFAプロフェッショナル 月額80,000円
【特徴】中小企業向け
オールインワン型の顧客管理ツールで、グループウエア、CRM/SFA、外部システムとのデータ連携が可能なアプリケーションなどが備わっています。いずれのプランもID数の制限はなく、必要な機能だけを自社に合わせて選択可能です。
8. GENIEE SFA/CRM(株式会社ジーニー)

【形態】クラウド型
【価格】スタンダード 月額29,800円 /10ユーザー
プロ 月額49,800円 /10ユーザー
エンタープライズ 月額98,000円 /10ユーザー
【特徴】中小企業向け
GENIEE SFA/CRM(元「ちきゅう」)は、6,300社の導入実績を誇る国内製の営業管理ツールです。専任のカスタマーサクセスチームによる充実したサポートが魅力で、高い定着率を実現しています。
9. SATORI(SATORI株式会社)

【形態】クラウド型
【価格】初期費用300,000円 + 月額148,000円(年間契約)
【特徴】中小企業向け
SATORIは、リードの獲得・育成・管理に特化したツールです。一例として、セグメント機能で顧客の購買記録から購買意欲の高い顧客を抽出し、テレアポのためのコールリストを制作するなどの活用が可能です。
ステップメールやホットアラート通知、パーソナライズなど、マーケティングに活用できる機能も充実しています。
10. Sansan(Sansan株式会社)

【形態】クラウド型
【価格】要問い合わせ
【特徴】中小・大企業(BtoB)向け
名刺管理クラウドサービスとして知名度のあるSansanには、CRM機能もあります。
名刺から得られた企業の情報を、メール・電話・面会などの接触履歴と組み合わせて管理することで、情報を全社的に活用できます。メール配信やセミナーの開催といったマーケティング機能も活用可能です。
11. Customer Rings(株式会社プラスアルファ・コンサルティング)

【形態】クラウド型
【価格】初期費用あり
月額料金は要見積もり
【特徴】中小企業向け
カスタマーリングスは、ECサイト運営に強みを持つ顧客管理・マーケティングツールです。購買履歴やサイトでの行動データをきめ細やかに分析し、顧客一人ひとりの行動パターンを把握できます。
分析結果をもとに、メール、LINE、SMSなどさまざまな手段を使って最適なタイミングで情報発信も可能です。一斉配信やステップメールなど状況に応じた配信方法を選べます。
12. SugerCRM(SugarCRM社)
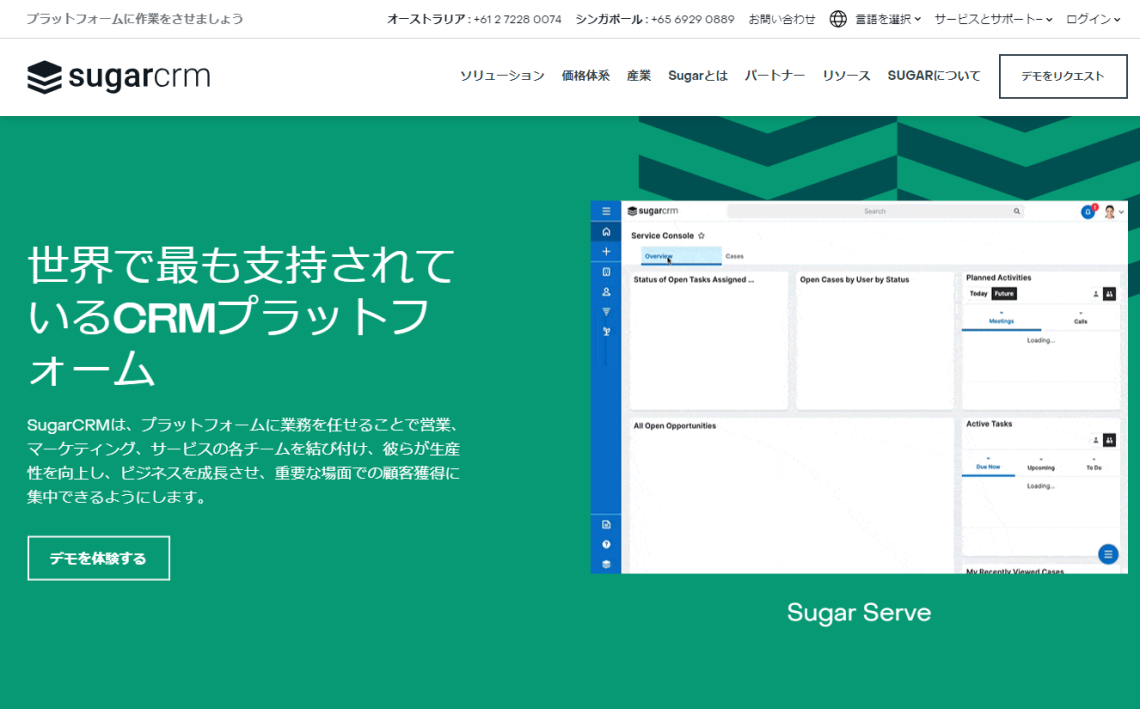
【形態】オンプレミス型
【価格※】Market 月額140,000円(連絡先10,000件あたり)
Sell 月額2,660円/1ユーザー
Serve 月額11,200円/1ユーザー
Enterprise 月額11,900円/1ユーザー
※1米ドル=140円で換算
【特徴】中小・大企業向け
SugarCRMは、世界で1,000万以上のダウンロード実績がある信頼性の高い顧客管理システムです。営業支援、見込み客管理、サービスの自動化など幅広い機能を搭載しています。基本プランでは、顧客情報の管理から商談の追跡、問い合わせ対応まで一通りの機能を利用できます。
カスタマイズ性が高いので、画面レイアウトの変更や外部のシステムとの連携も柔軟に対応可能です。
13. HubSpot CRM(HubSpot Japan株式会社)

【形態】クラウド型
【価格】基本無料
Marketing Hub Starter 月額2,400円
Starter Customer Platform 月額2,400円
Marketing Hub Professional 月額106,800円
Marketing Hub Enterprise 月額432,000円
【特徴】中小企業向け
HubSpot CRMは、見込み客の獲得から顧客化までをまとめてサポートしてくれるシステムです。マーケティング、営業、顧客サポートの機能が一体となり、直感的に操作できます。
基本機能は無料で利用可能です。成長に応じて、営業の支援やマーケティングの自動化など機能を追加できる柔軟性も魅力です。
14. b→dash(株式会社フロムスクラッチ)

【形態】クラウド
【価格】要問い合わせ
【特徴】中小・大企業向け
b→dashは、プログラミングの知識がなくてもデータ分析とマーケティングが実行できる統合型ツールです。16種類の分析機能と豊富な業界別テンプレートを搭載し、メールやLINE配信、アプリを使ったキャンペーンなどのマーケティング活動に対応しています。
データの活用に課題を持つ企業に適しており、自社のニーズに合わせた柔軟なカスタマイズが可能です。
15. Freshsales(Freshworks社)

【形態】クラウド型
【価格※】無料プランあり
Growth 月額2,520円
Pro 月額6,580円
Enterprise 月額11,620円
※1米ドル=140円で換算
【特徴】中小企業向け
Freshsalesは、AIを活用して営業活動を効率化するCRMツールです。ウェブサイトを訪れたユーザー情報の自動取得、電話・メール・SNSの一元管理まで、営業に必要な機能が搭載されています。
顧客の行動を分析してスコア化し、見込み客を特定も可能です。顧客のソーシャルメディア情報も確認でき、アプローチも的確になります。
顧客管理システム(CRM)で営業の成果向上を実現しよう
顧客ニーズの多様化や市場競争の激化などにより、顧客一人ひとりに合わせた製品・サービスの提供や、セールス戦略の重要性が増しています。顧客管理はExcelなどでも行えますが、情報量が増えるにつれて効率的に運用するのは容易ではありません。
顧客管理システム(CRM)を導入すれば、重要な顧客情報を一元管理でき、必要な情報にすぐアクセスできるようになります。その結果、業務の効率化が進み、より質の高い顧客対応が可能になります。SFA機能も備えたシステムを選べば、営業活動の効率向上にもつながり、成果の最大化が期待できるでしょう。
eセールスマネージャーは、CRMとSFAの機能を兼ね備えたツールです。顧客管理だけでなく、案件管理や日報の作成、地図機能、外部連携機能など豊富な機能で日々の営業活動をサポートします。顧客管理を強化したい方は、ぜひご相談・お問い合わせください。