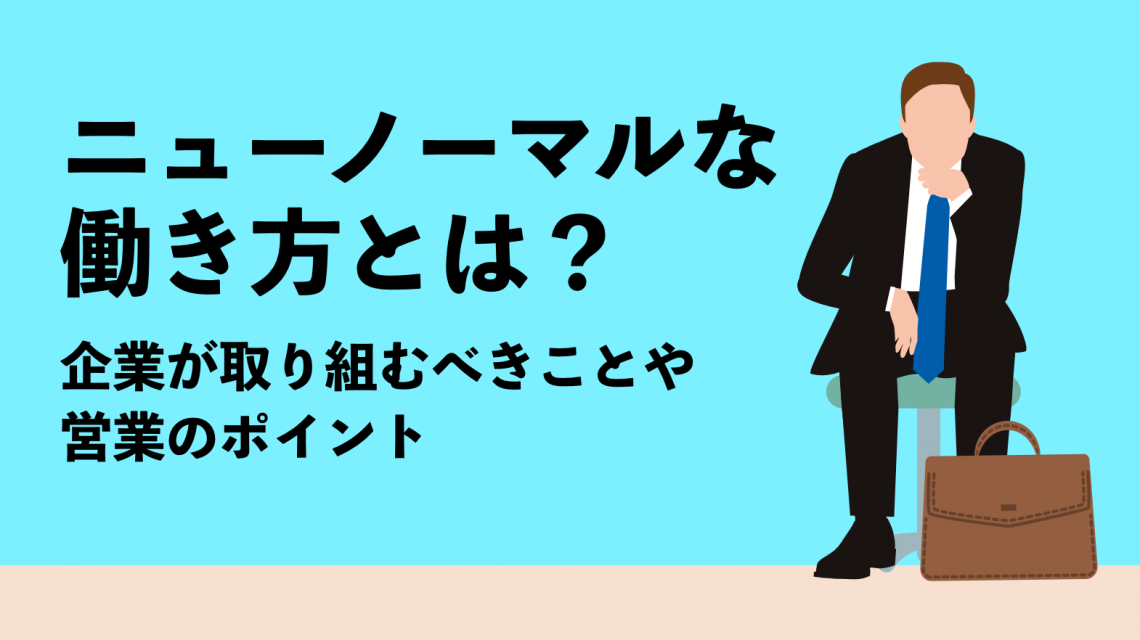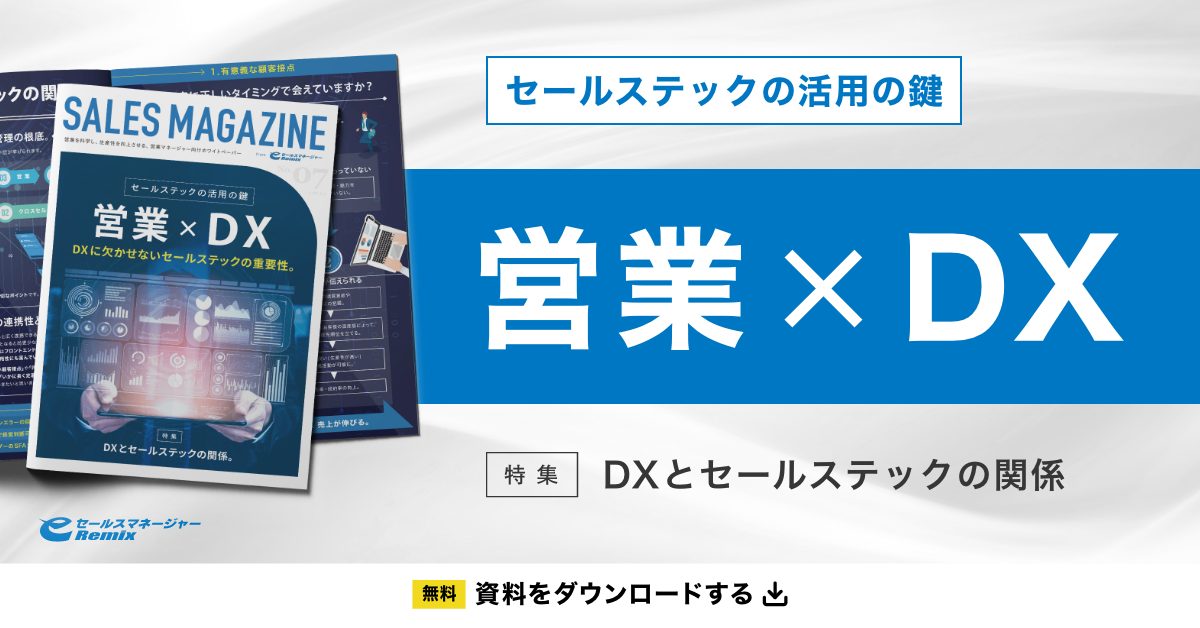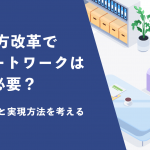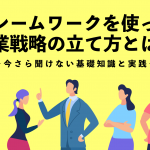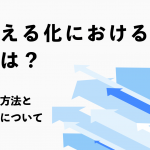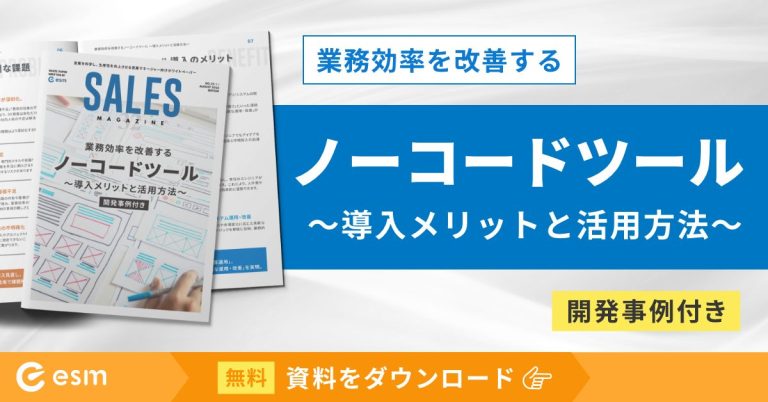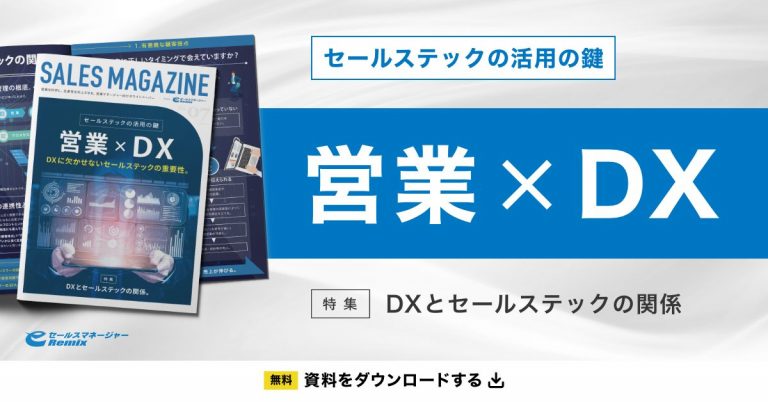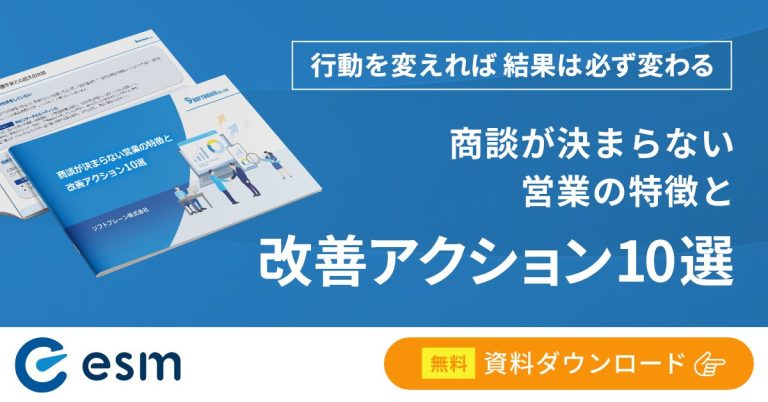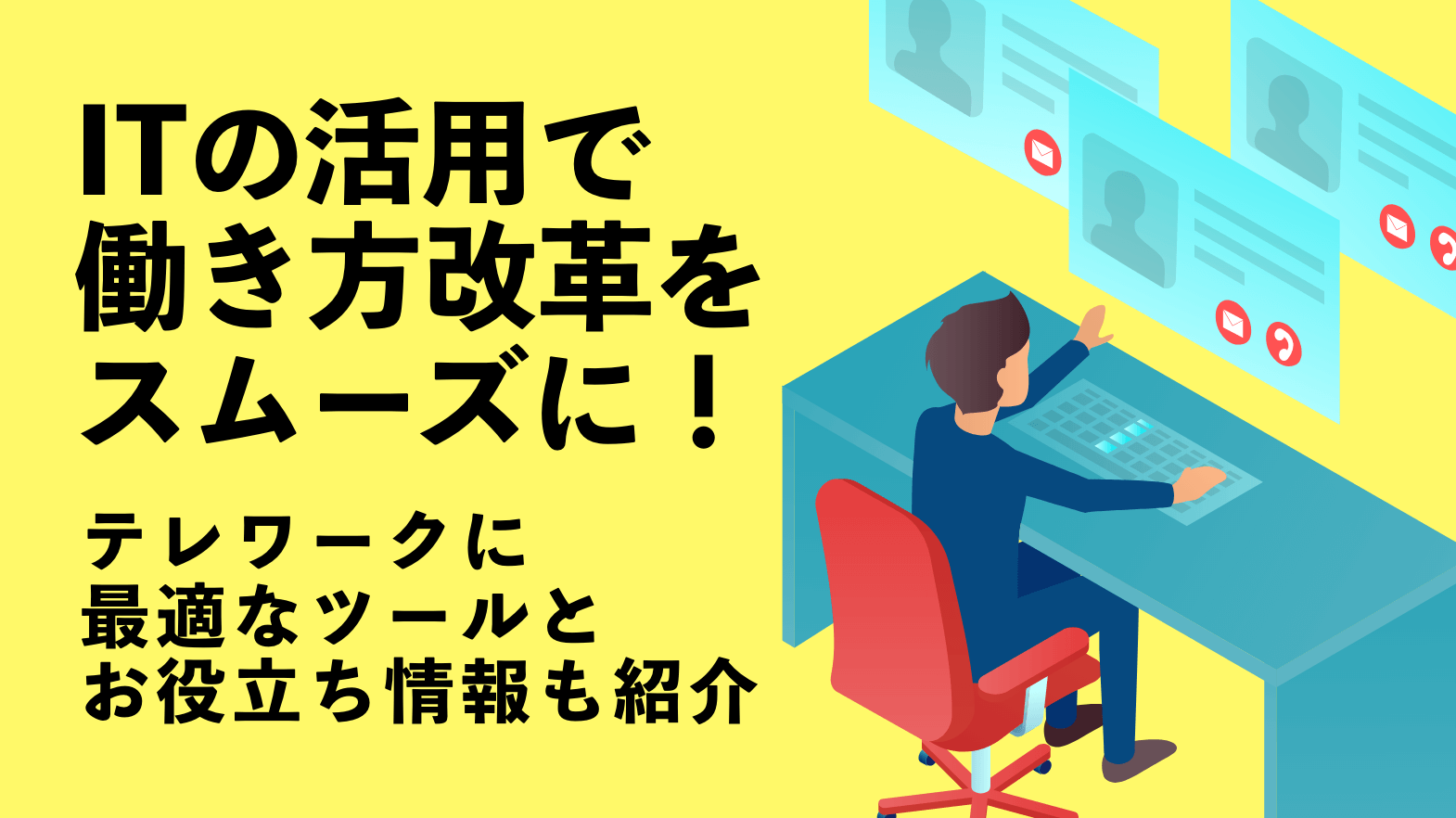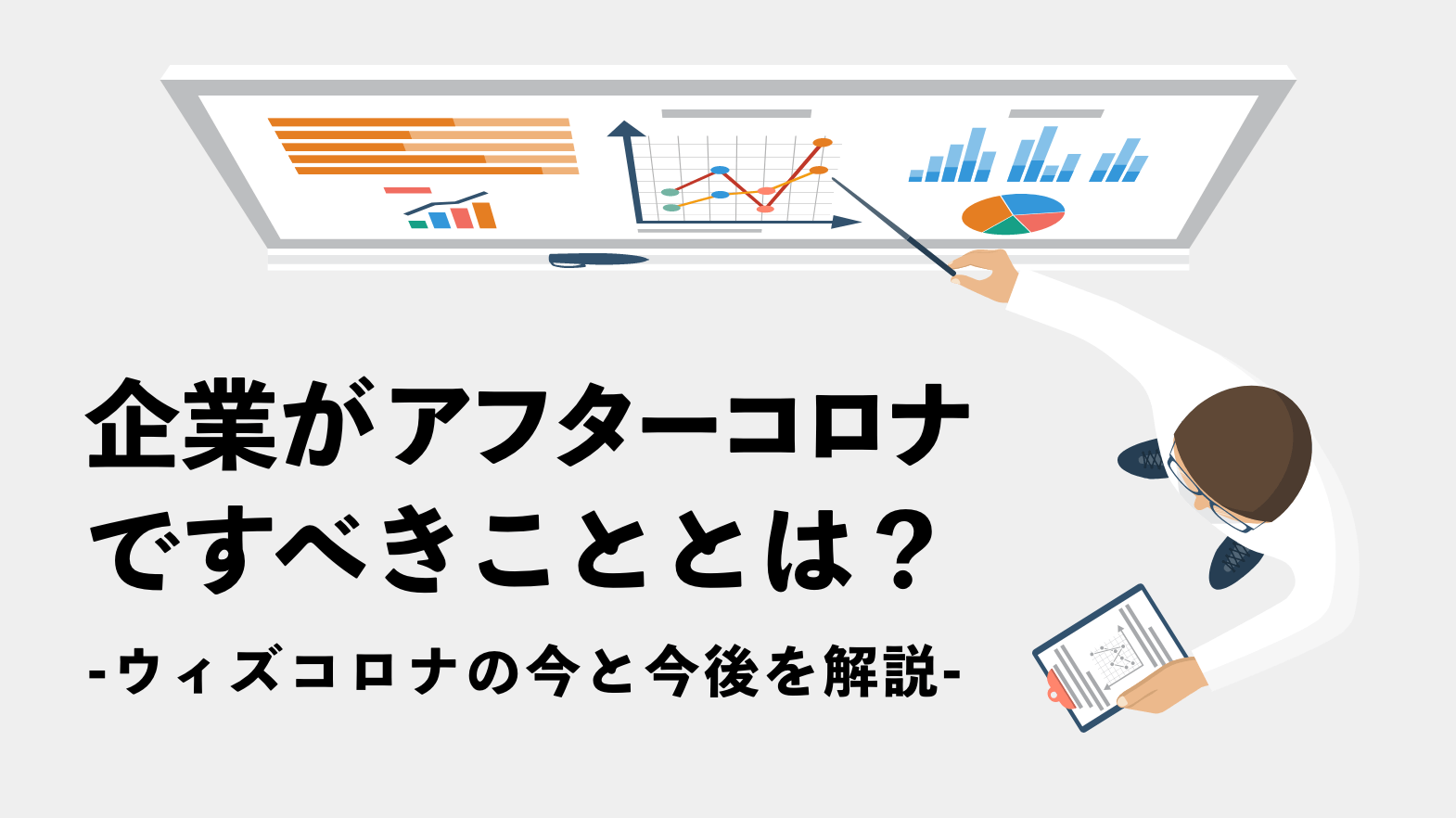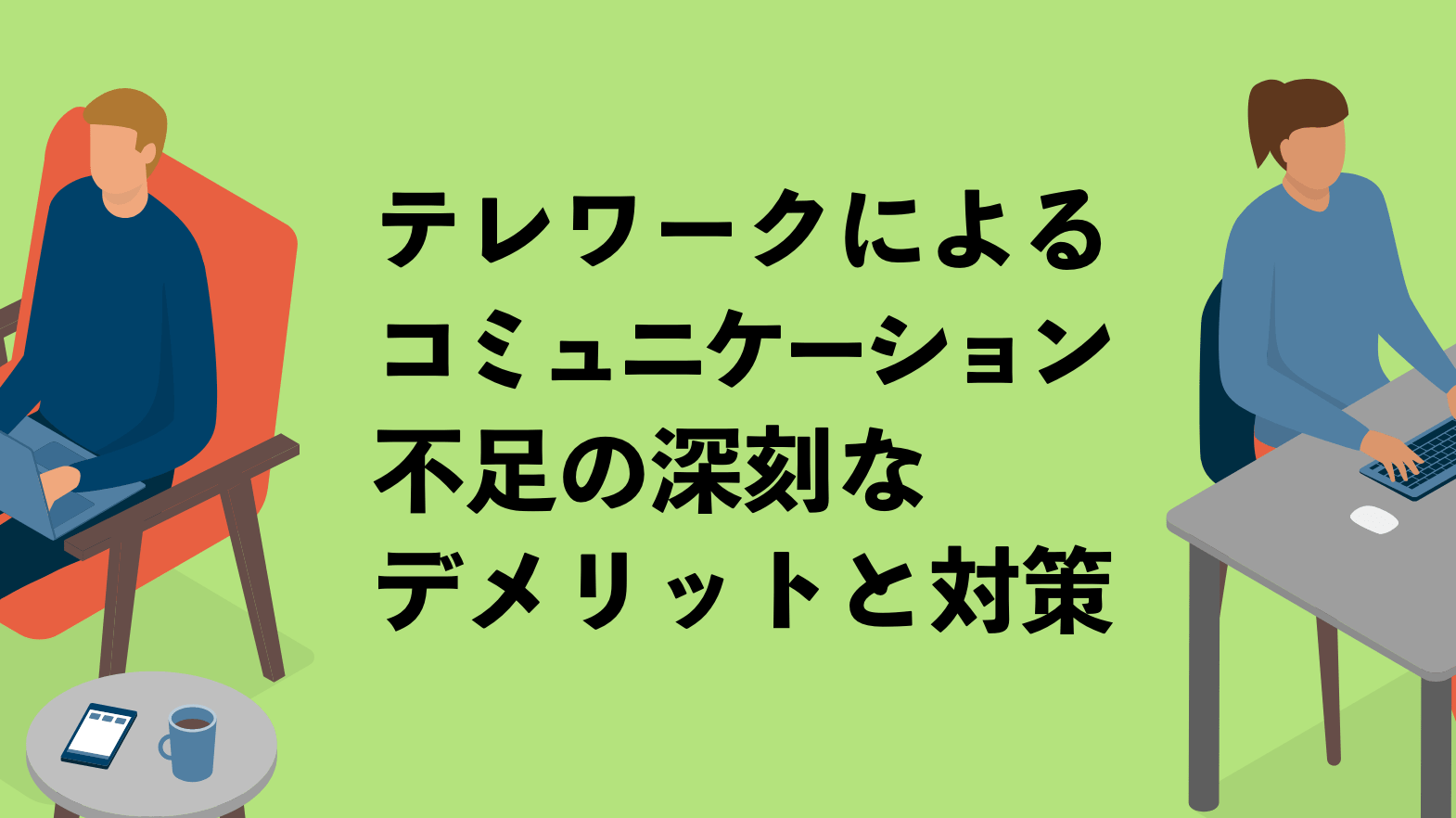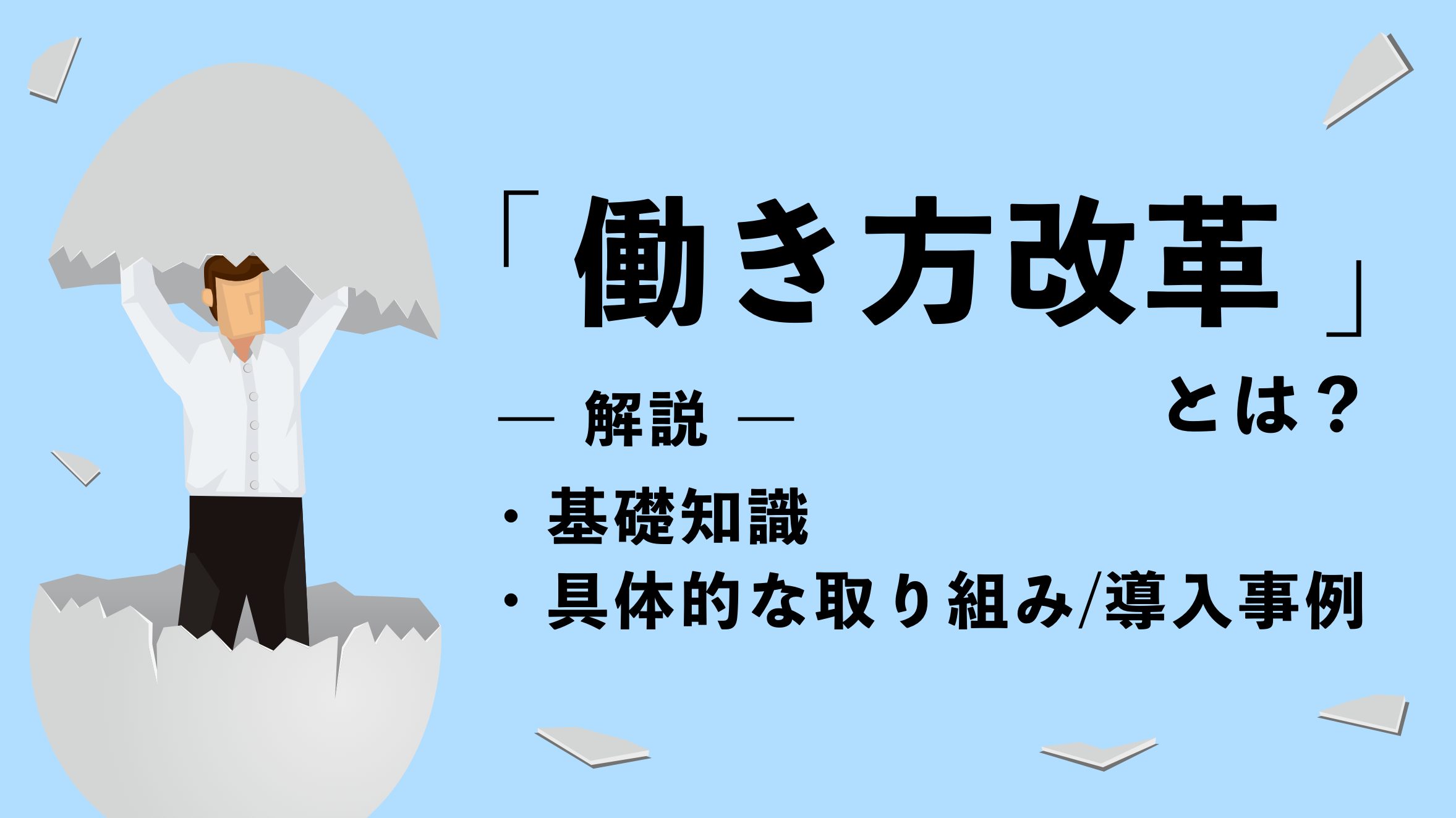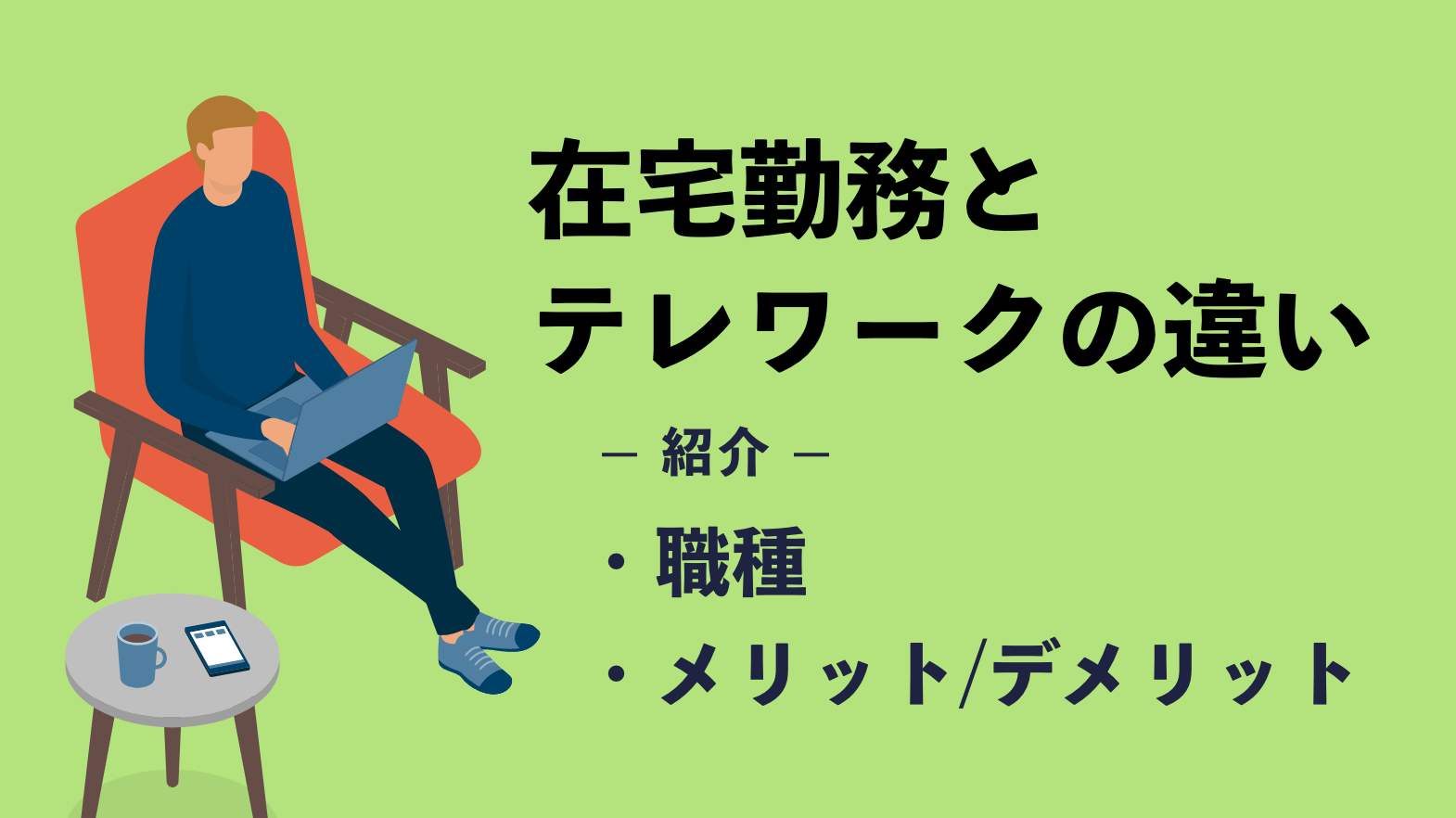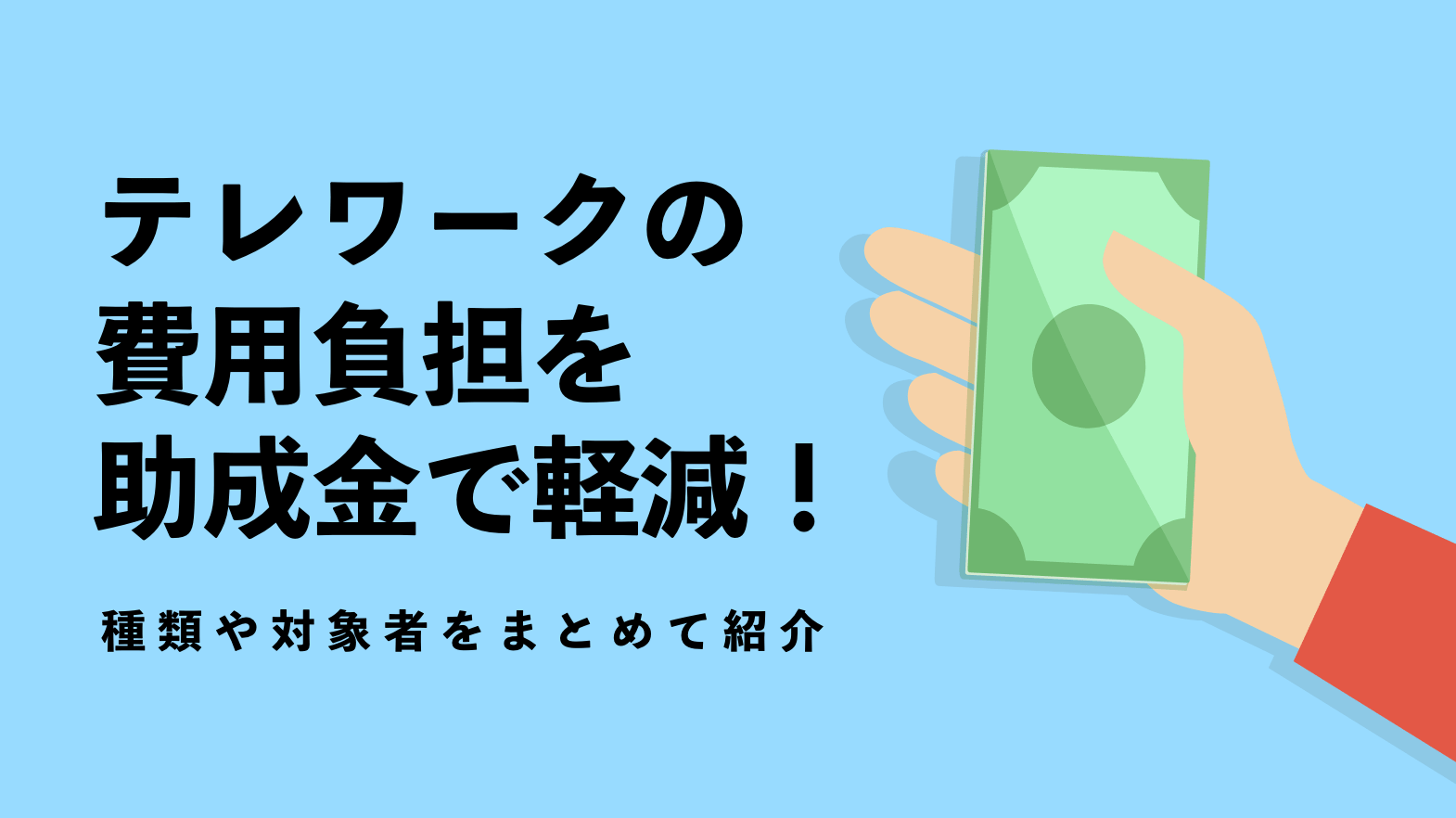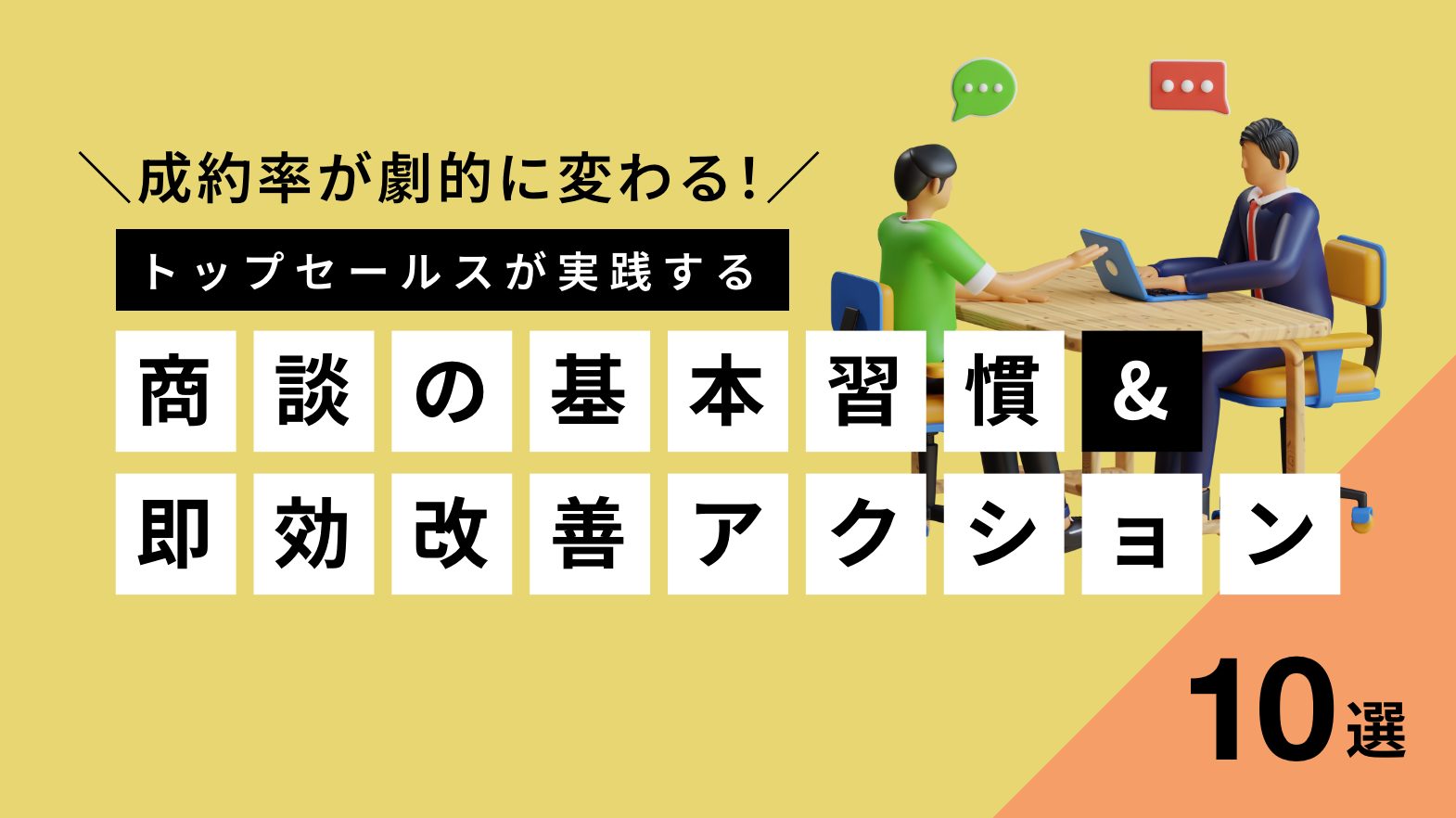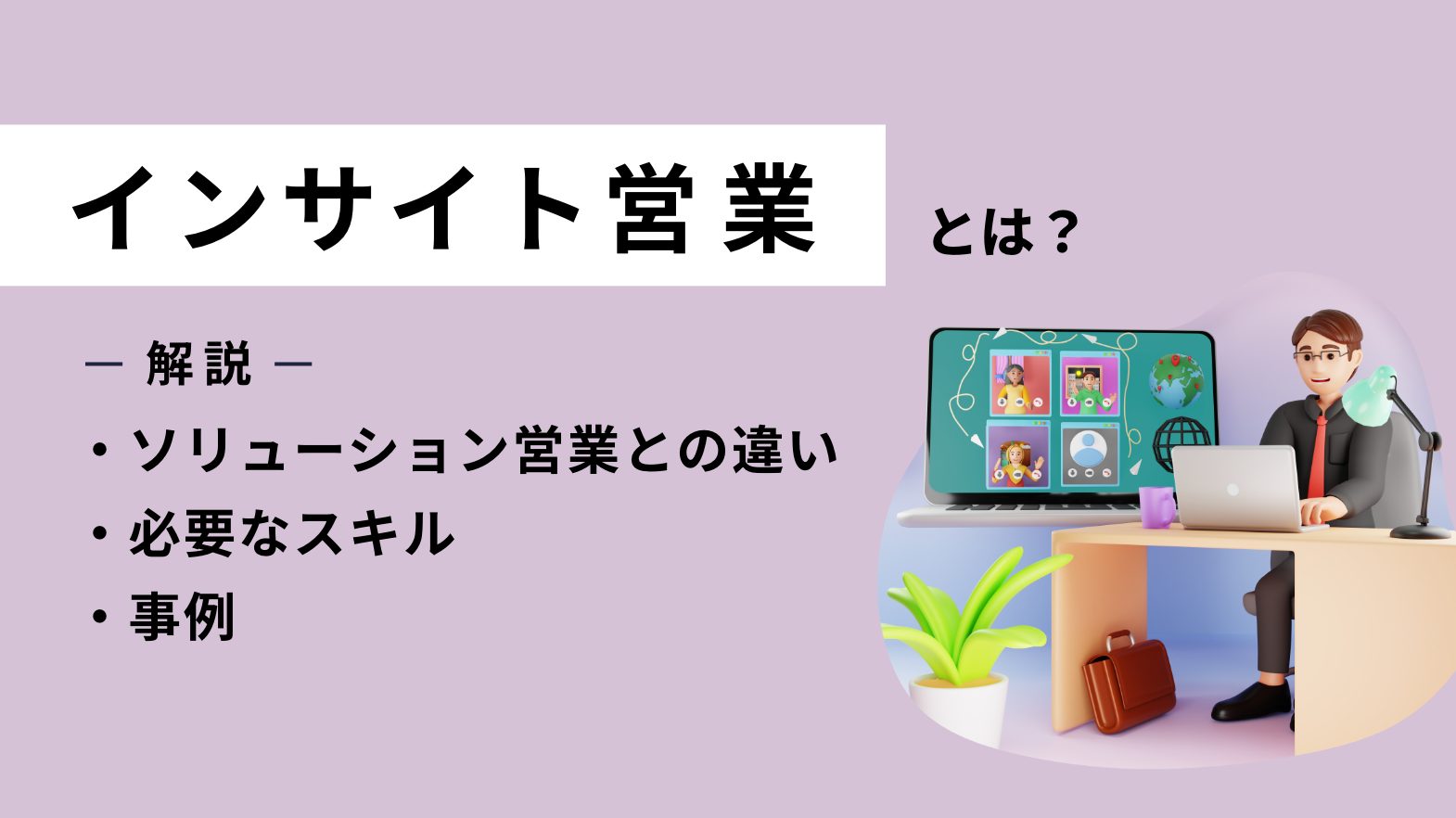ニューノーマルな働き方とは?企業が取り組むべきことや営業のポイント
新型コロナウイルスによりもたらされたニューノーマル時代は、私たちの生活や働き方に大きな変化をもたらしました。
ニューノーマルにより消費性向や暮らしが変わったことで企業にもさまざまな対応が求められ、ニューノーマルが一般化した今でも、さらなる変化の取り組みが必要となっています。
本記事では、ニューノーマルによるビジネスや働き方、暮らしの変化と、ニューノーマル時代に企業が成長するために必要な対策を解説します。
このページのコンテンツ
ニューノーマルとはビジネス・働き方の変革

ニューノーマルとは社会に起こった大きな変化が新しい常識として定着することです。過去に2回起きており、新型コロナウイルスの流行により、3回目のニューノーマル時代が到来しました。
今回のニューノーマルでは、テレワークや社内業務・営業活動のオンライン化などが常態化して働き方が変化したほか、DXの加速化、新たなビジネスモデルへの転換など、企業にも大きな変革が求められることとなりました。
つまり企業にとっては、「ニューノーマル=ビジネスの変革期」といえるでしょう。
なお、ニューノーマル自体についてより詳しくは以下の記事が参考になります。本記事は、ニューノーマルの到来をうけて企業がすべきことをメインに解説していきます。
参考:ニューノーマルの意味とは?新時代の働き方と企業に求められる対策も
ニューノーマルで起きた働き方などの変化
ニューノーマルでは私たちの生活や価値観、働き方に大きな変化が起こりました。以下で詳しく解説します。
消費者行動・ニーズの変化
新型コロナウイルスの流行をうけて、消費者の行動やニーズは大きく変化しました。代表的なものは巣ごもり消費やネットショッピングの活用の大幅な増加です。
また、消費者ニーズも顕著に変わりました。たとえば、新型コロナウイルスの流行をうけて拡大した「家飲み・宅飲み」が挙げられます。生ジョッキのような泡や味わいを楽しめる「スーパードライ 生ジョッキ缶」や高級日本酒の「百光」などの人気ぶりは、記憶に新しいでしょう。
こうした変化を受け、企業は新たな販売チャネルやビジネスモデルの創出を余儀なくされました。
ニューノーマルでもたらされた変化が一般化するこれからの時代でも、消費者のニーズや行動の変化に迅速に対応していくことが求められるでしょう。
新しい働き方で社員の価値観の変化も加速
ニューノーマルにより、私たちの働き方も大きく変わりました。
今ではテレワークが常態化し、ワーク・ライフ・バランスの実現や働き方改革の推進につながっています。社内会議も出社せずにオンラインミーティングで済ませることができ、申請や決済なども電子処理することで業務の効率化を実現した企業も多いでしょう。
また、営業活動もオンライン商談を行う機会が増え、遠方の企業にも簡単にアプローチできるようになりました。
働き方の変化により、オフィスの家賃や移動・出張にかかる交通費などの経費を削減できるといったメリットを享受した企業も多く、これからもハイブリッドな働き方を導入する企業は増えるでしょう。
一方で、従業員同士のコミュニケーション不足による弊害や、従業員の勤怠管理・評価が難しくなるといった課題も増えており、企業にはニューノーマル時代における新たな対策も求められています。
ウェビナー(Webセミナー)やインサイドセールス部隊によるオンライン商談の詳細は、以下の記事で確認できます。
参考:ウェビナーとは?メリットや開催方法・成功のコツを基礎から解説
参考:インサイドセールスとは?目的や既存営業との違い、導入のポイントを解説
ニューノーマル時代の企業経営で重視すべきこと
ここからは、働き方やビジネスの変化が定着したニューノーマル時代に、企業経営において重視すべきポイントを解説します。
顧客との関係性の再構築
ニューノーマルの到来で消費性向や暮らしが変わったことにより、顧客の変化に合わせた関係性の構築をあらためて行う必要があります。
オフラインよりもオンラインチャネルでの接点が増えたニューノーマル時代では、既存顧客とのタッチポイントの見直しや強化すべきアプローチ方法も再考する必要があるでしょう。
ターゲットのニーズや消費行動が変化しているため、新規に開拓する顧客の見直しも必須です。
CRM/SFAツールを活用して、ニューノーマル時代に合った顧客との関係性の見直しを、効率よく進めましょう。
DX推進によるコスト削減
ニューノーマルで定着したテレワークやオンライン商談などを加速させるには、DXによる業務の効率化が不可欠です。
今まで人がかかわってきたノンコア業務などのフローを、デジタル化やクラウドの活用で代替すれば、人件費や労務負担の削減につながります。従業員もコア業務に注力でき、生産性向上も期待できるでしょう。
顧客管理や営業活動管理も、CRM/SFA、MAの導入により大幅な業務の効率化につながり、リソースの最適化も実現します。
ニューノーマル時代に企業が成長して生き残るためにも、また、従業員に快適な労働環境を提供するためにも、DXによるコスト削減が不可欠といえるでしょう。
参考:DXは低コストでも実現できる!DXに役立つ14の無料ツールを紹介
新しい働き方の確立
テレワークはすでに常態化しており、今後も自社の状況に合わせたハイブリッドな働き方を導入する企業が増えるでしょう。
労働力の減少がますます進む現状では、優秀な人材の確保も企業にとって重要な課題です。
従業員が望む労働環境を整備して、ワーク・ライフ・バランスの実現やウェルビーイング経営を目指すなら、自社に最適な働き方の確立が求められます。
参考:テレワーク(リモートワーク)とは?基本から導入の秘訣まで解説
リスクマネジメント
ニューノーマルをきっかけに、企業のリスクマネジメントも重視されるようになりました。ニューノーマル時代では、特にBCPの充実や従業員のマネジメント、情報セキュリティ強化などに注力しましょう。
BCP(事業継続計画)の立案や保守
地震や台風といった自然災害のほか、疫病などのパンデミック、サイバーテロなど、さまざまなリスクが企業にふりかかる危険が高まり、BCPの策定が重視されるようになりました。
万が一の事態が起きたときに事業がストップしないよう、BCPを充実させておくことは、ニューノーマル時代に欠かせないリスクマネジメントといえるでしょう。
従業員のマネジメント
テレワークが一般化すると、従業員の勤怠管理や体調やモチベーションなどを把握しづらくなるため、新たなマネジメントシステムが必要となります。
たとえば、CRM/SFAやタスクマイニングツールといったシステムを導入すると、従業員や業務の今を可視化できます。適切なアドバイスや対応が可能となるため、従業員のモチベーションアップや生産性向上も期待できるでしょう。
情報セキュリティ強化
社内業務や営業活動のデジタル化が進めば、情報セキュリティの強化は必須のリスクマネジメントとなります。
自社の環境に合った設備などハード面のセキュリティ強化はもちろん、従業員のITリテラシー向上のための対策も必要です。
マニュアル作成や研修のほか、普段のコミュニケーションやマネジメントを通じて、身につけるべきスキルを共有するようにしましょう。
ニューノーマル時代の営業ポイント
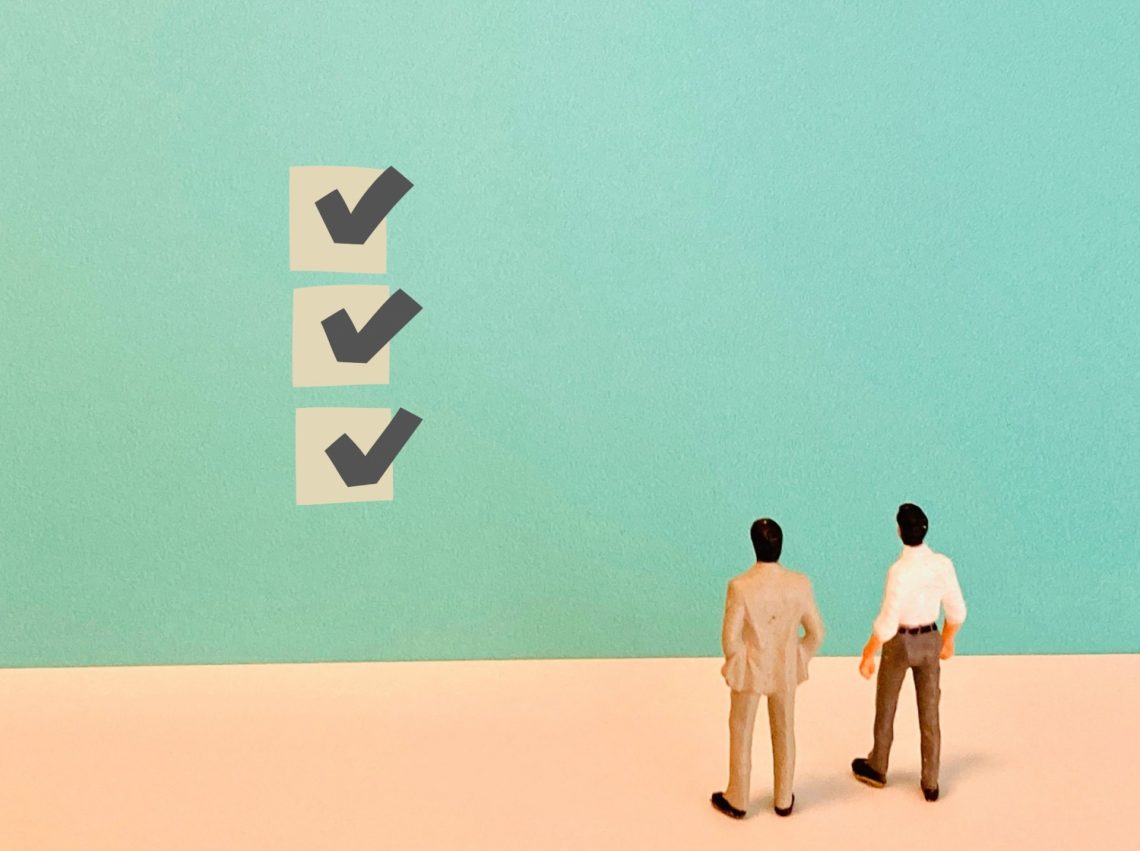
ここからは、ニューノーマル時代の営業活動で注力したいポイントである「既存顧客との接点強化」と「新規顧客開拓の見直し」について、詳しく解説します。
ポイント1:既存顧客との接点強化
既存顧客との接点強化では、「顧客との接点確保」と「提案の質の向上」が必要です。
顧客との接点確保
ニューノーマル時代においても、成約件数=提案数×成約率であることに変わりはありません。そのためにまず考えるべきは提案数の確保、つまり顧客との接点の確保といえるでしょう。
ニューノーマル時代では、顧客との接点が対面のオフラインよりも非対面のオンラインが多くなりました。そのため、非対面の接点をいかに増やすかが重要です。
自社ホームページが訪問者にとって見やすいものになっているか、問い合わせは簡単にできるかなどはかならずチェックしましょう。
オンラインによるインサイドセールスやオンライン商談・ミーティングも積極的に活用し、接点を増やす努力が必須となります。
提案内容の質の向上
顧客との接点=提案数を増やすだけではなく、成約件数や成約率を上げなければなりません。そのためには提案の質を高めることが重要になるので、CRMの活用が有効です。
CRMにより自社のデータをAI分析させることで、既存顧客に対してどの商品を高い確率で売れるかなどの分析が可能となります。またSFAとの連携で、効果的な営業活動も展開できるでしょう。
データ分析にもとづいた提案や営業活動を行なえば、効率よく成約率の向上を目指せます。
CRMについてより詳しく知りたい場合は、以下の記事を参考にしてください。
参考:CRMとは?機能・メリットや選び方、活用のコツをわかりやすく解説
ポイント2:新規顧客開拓の見直し
新規顧客開拓の見直しでは、「ターゲットを明確にする」ことと「最初の接点を改善する」ようにしましょう。
ターゲットを明確にする
ニューノーマルによるターゲットのニーズや消費性向の変化に対応するため、再度、自社製品のターゲット・ペルソナを明確にすることが重要です。BtoBなら、相手企業のニューノーマルによる変化なども把握しておく必要があるでしょう。
ターゲット像が明確になれば、適切なタッチポイントやアプローチ方法なども再設定できます。
あらためてカスタマージャーニーマップを作成して、各タッチポイントで良質なCX(顧客体験)を提供できるような手法を整理しましょう。
最初の接点を改善する
非対面が主流となるニューノーマル時代では、最初のタッチポイントが重要です。
非対面ではどうしてもプッシュ型(企業から顧客に対して接近するタイプ)の営業が難しくなり、プル型(顧客から企業に対して接近するタイプ)の営業が多くなります。
そのため、顧客が興味を持つ最初の接点が重要で、ここでの印象により顧客が継続してアクセスするか、二度と戻って来ないかが決まると言っても過言ではありません。
最初の接点としては、自社ホームページやSNS、既存メディアでの広告などがあります。顧客視点に立った手法やコンテンツでアプローチするようにしましょう。
ニューノーマル時代は働き方や暮らしの変化に対応したビジネスを
ニューノーマルにより、消費者の志向や働き方、ビジネスに大きな変化が起きました。
ニューノーマル時代に企業が効果的な営業活動を行い成長していくためには、こうした変化に柔軟・迅速に対応できるようにすることと、BCP対策やセキュリティ強化といった体質強化が重要です。
ニューノーマル時代に顧客の変化にアジャストするには、接点やアプローチ方法などを見直す必要もあります。
CRM/SFAツールを活用すれば効率よく進められるため、営業活動やリソースの最適化をめざすのであれば、ぜひ導入を検討しましょう。