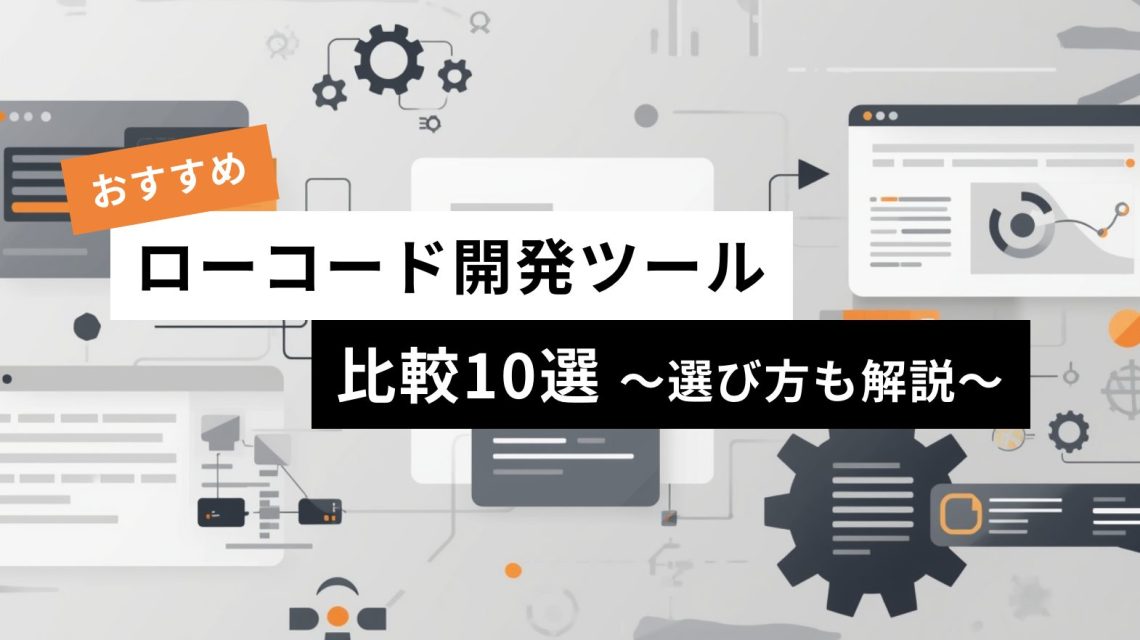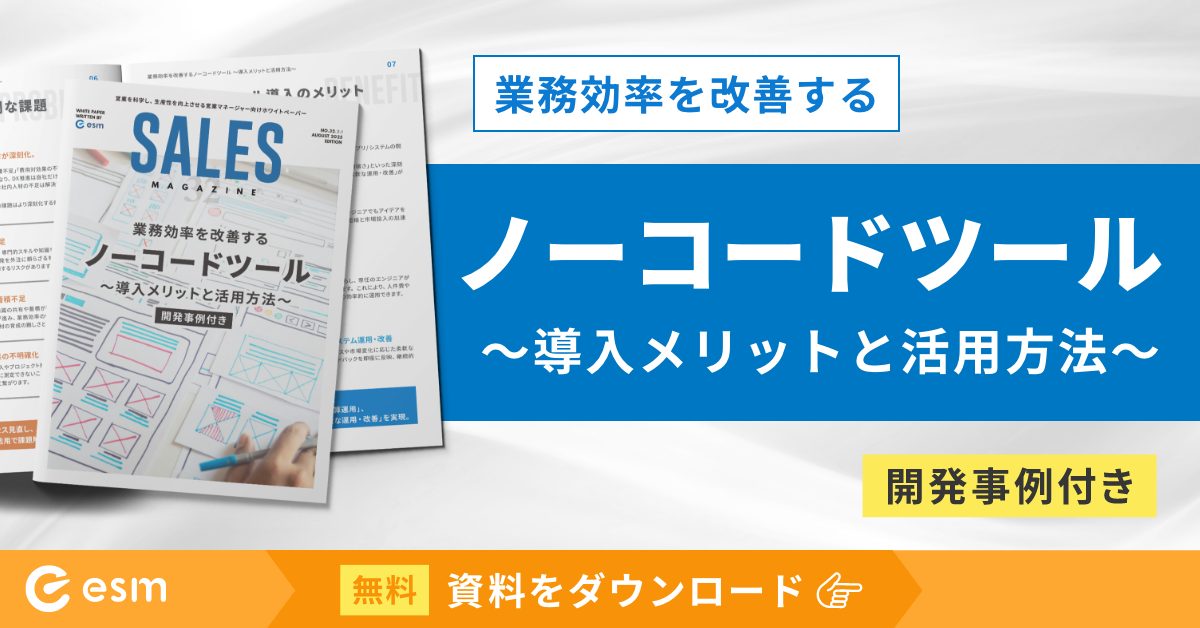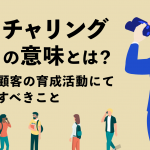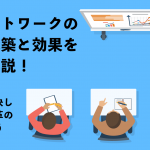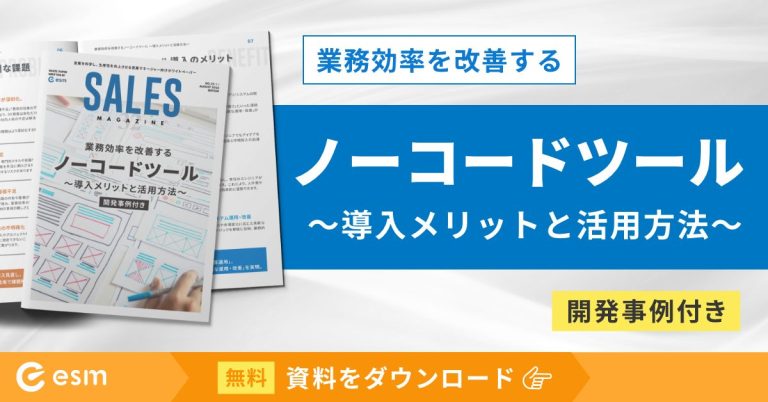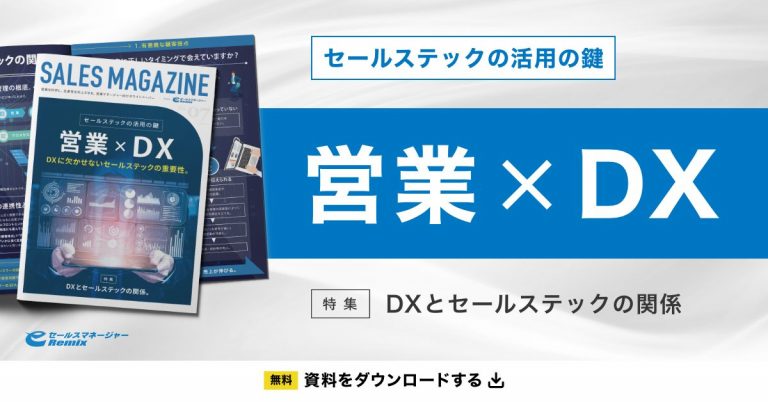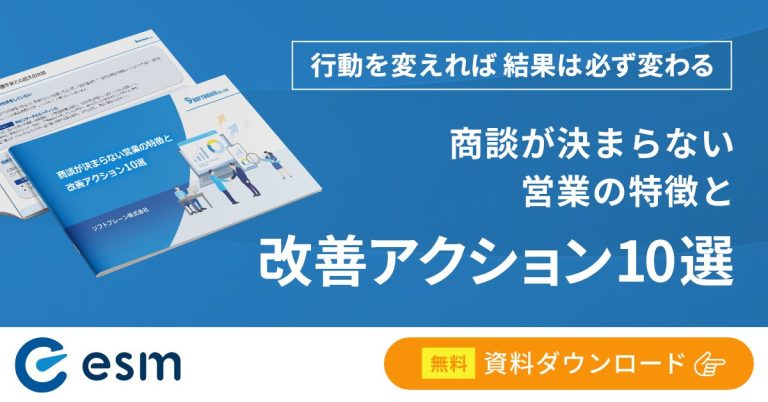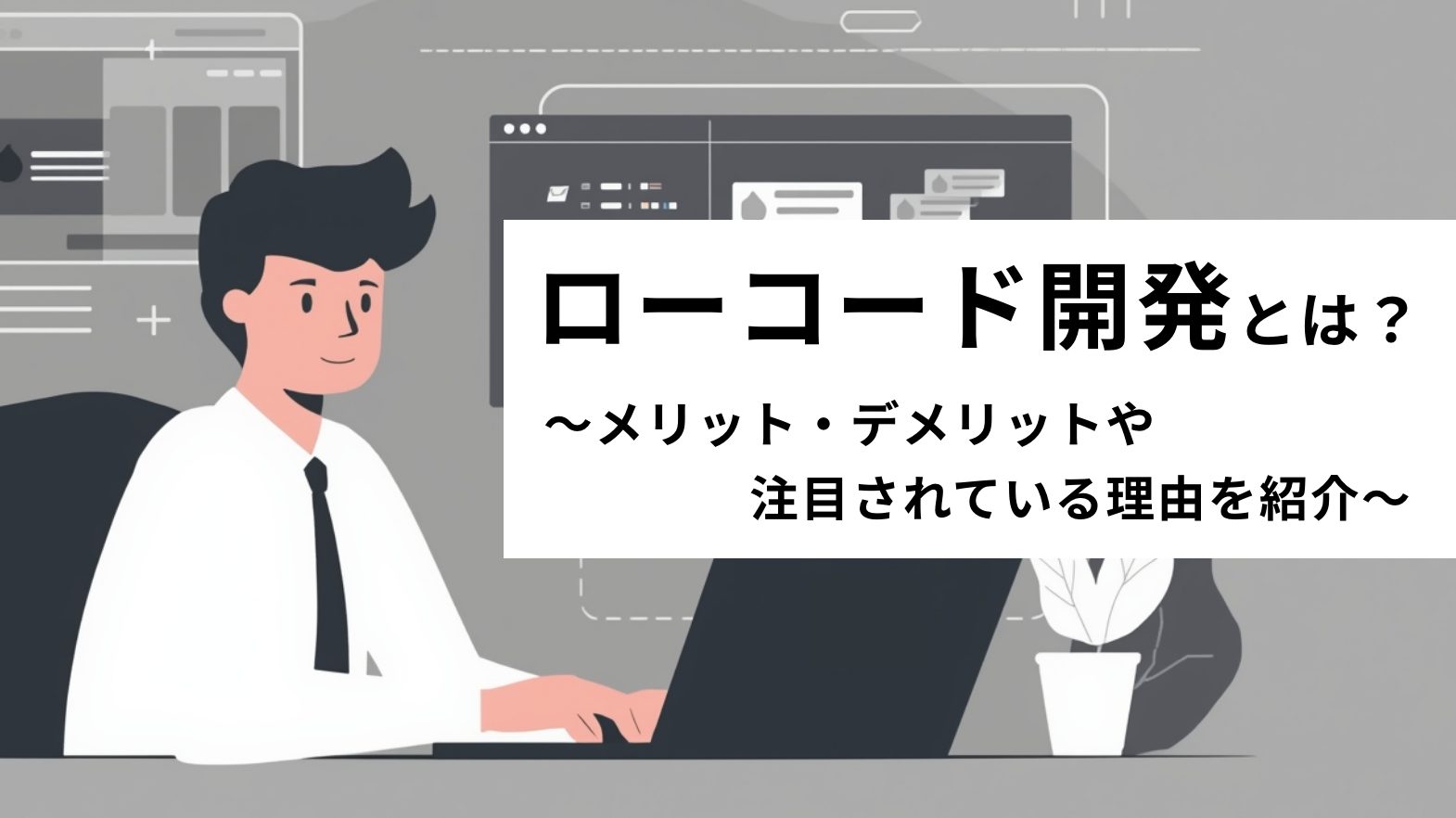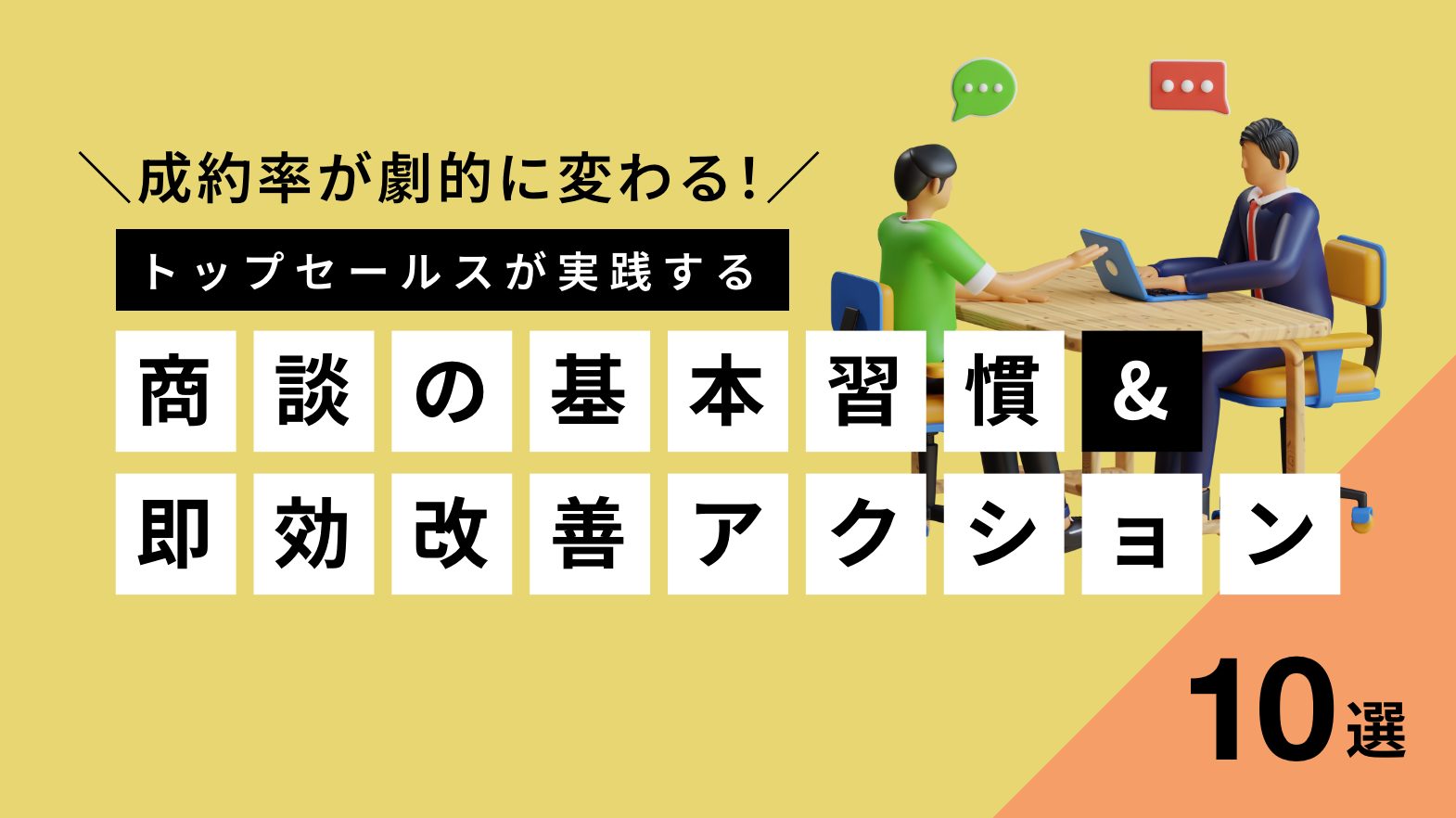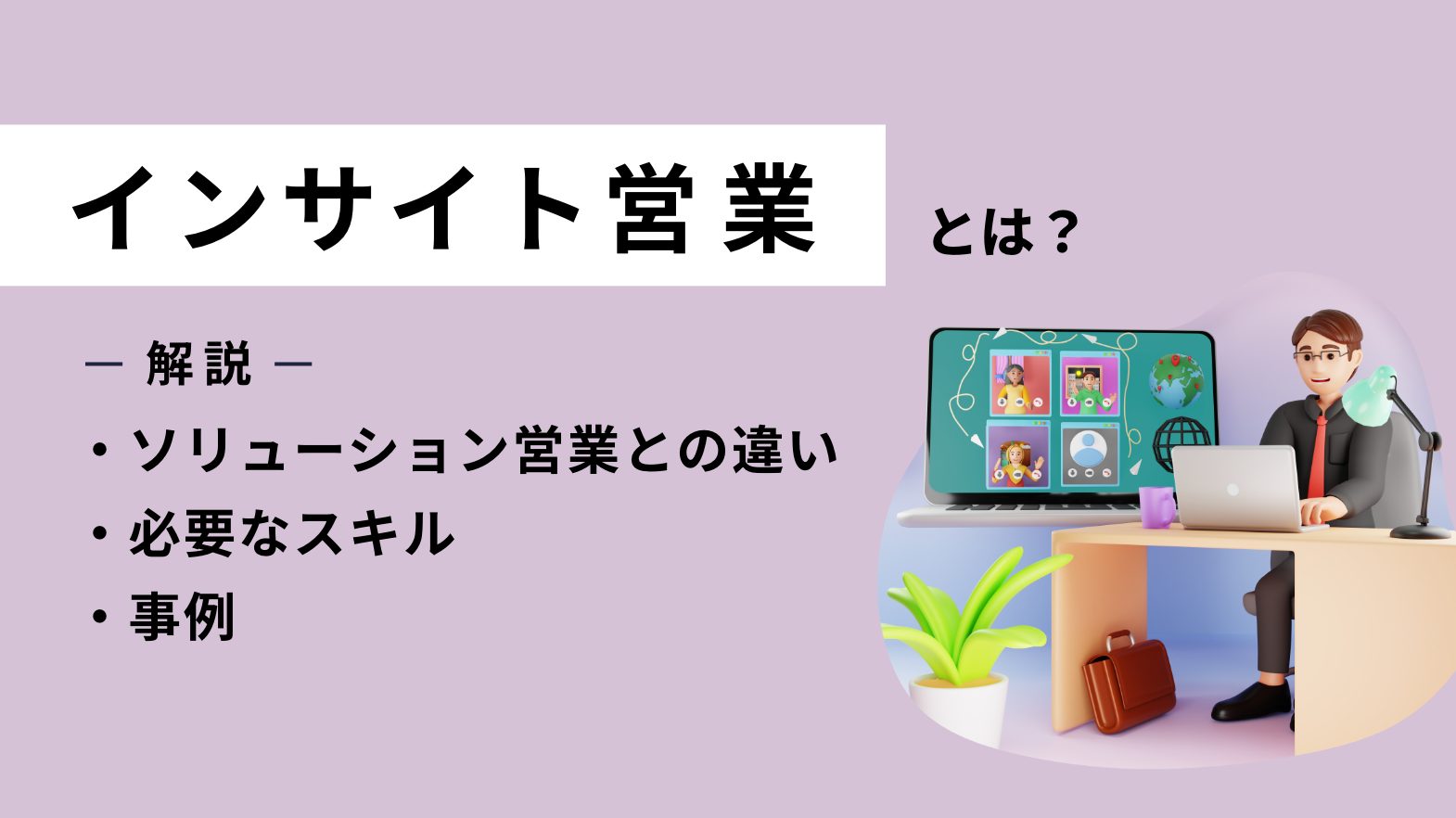おすすめローコード開発ツール比較10選【2026】選び方も解説
開発効率を大幅に向上させる手法として、ローコード開発ツールがトレンドになっています。ローコード開発は極力コードを書かずにアプリを開発する手法です。また必要に応じて、コードを書いて独自の機能を実装することも可能です。
国内外のベンダーから多様なローコード開発ツールが提供されており、導入を検討しているものの、どれにすべきか決めかねている企業担当者の方も多いのではないでしょうか。
本記事では、おすすめのローコード開発ツール10選を紹介し、選び方のポイントやローコード開発ツールを導入するメリットやデメリットについても解説します。導入を検討する際の参考にしてください。
このページのコンテンツ
ローコード開発ツールとは
ローコード開発ツールとは、その名のとおり、ローコード開発をするためのツールです。ローコード開発は、コーディング量を少なくし、基本的に画面上でパーツをドラッグ&ドロップしたりテンプレートを調整したりしてアプリを開発する手法を指します。必要であれば、コードを書いて独自の機能を実装することも可能です。
一からコードを書く従来の開発手法に比べ、大幅に開発期間を短縮できる点が大きな特長です。高度なプログラミング知識がなくても設計できるため、非エンジニアが業務アプリを開発しているケースもあります。
なお、ローコード開発ツールの中には、開発機能だけではなく、デプロイやテスト、ユーザー管理といったアプリのライフサイクル全体を管理できるものもあります。開発の土台となるため、「ローコード開発プラットフォーム」とも呼ばれています。
おすすめローコード開発ツール比較10選
ローコード開発ツールやプラットフォームにはさまざまな製品があり、それぞれ得意分野や特徴が異なります。導入する際は、自社の状況や開発目的に合ったもの選ぶことが欠かせません。
ここでは、おすすめのローコード開発ツール・プラットフォームを紹介します。
OutSystems

(引用:OutSystemsトップページ)
OutSystems社はポルトガルのリスボンとアメリカに本社を置くグローバル企業で、日本にも法人を構えます。提供しているOutSystemsは世界規模で高いシェアがあり、日本でも多くの企業が導入しています。大規模開発向けで、小規模な開発用途にはオーバースペックになる可能性があるため注意しましょう。
導入した日本企業からは「社内システムの開発に適している」「UIが分かりやすい」などの意見がある一方、カスタマイズが難しいとの声も見られました。
料金についてはお問い合わせください。
Mendix
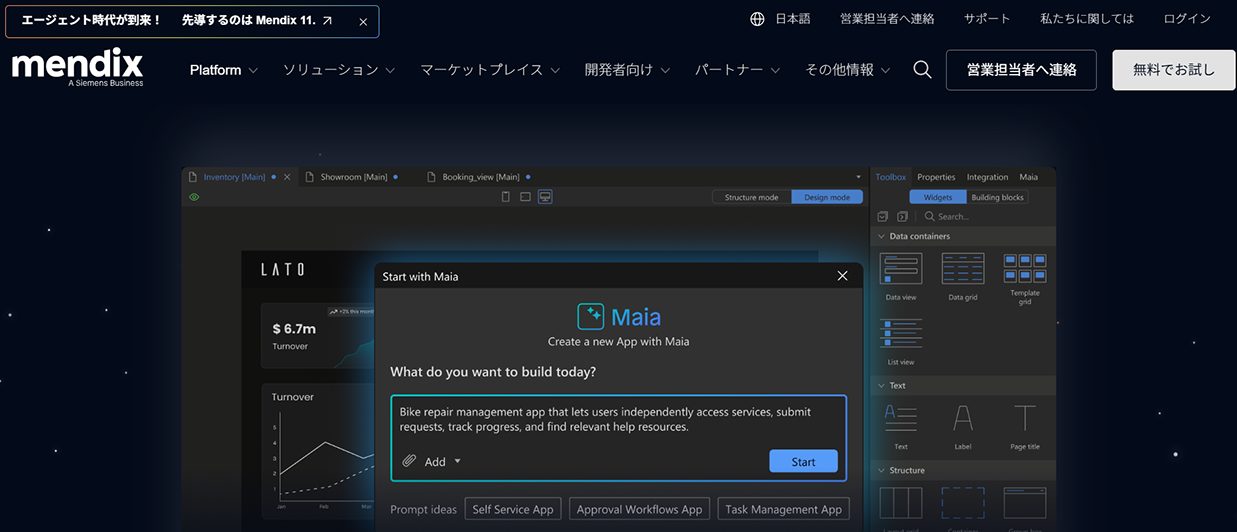
(引用:Mendixトップページ)
Mendix社はオランダ発の企業で、現在はドイツのシーメンス傘下です。日本では東京にオフィスを構え、日立ソリューションズやNECなどが販売代理店を務めています。大規模・エンタープライズ用途向けです。
日本の導入企業からは「アプリ表示と実際の開発画面が同じで操作しやすい」「直感で操作しやすい」など操作性の高さを評価する意見が見られました。
無料で利用できるフリープランがあるほか、スタンダードプラン(月額€900~)とプレミアムサーマルバッグ(要見積もり)があります。詳しい料金はお問い合わせください。
Microsoft Power Platform

(引用:Microsoft「Power Platform」)
Microsoft社が提供する開発プラットフォームで、主に以下の5つからなります。
- Power Apps(アプリ作成)
- Power Automate(自動化)
- Power BI(データ分析)
- Power Pages(サイト構築)
- Copilot Studio(AIチャットボット構築)
Microsoft 365やTeamsなど、Microsoft社が提供する多様なサービスと連携しやすいのが大きな強みです。
日本の導入企業からは「さまざまな業務改善アプリがすぐ作れる」「ネット上に情報が多く、調べやすい」などの意見が見られました。
料金体系はやや複雑で、ツールごとに課金する仕組みです。Power Appsでは以下のようになります。
- 開発者向けプラン:無料
- Power Apps Premium:2,998円/ユーザー
- Power Apps Premium:1,799円/ユーザー/最小2,000シート
※税抜き、月相当・年払い
Appian

(引用:appianトップページ)
Appianはアメリカで1999年に創業した会社で、グローバルに展開しており、日本では拠点としてAppian Japan合同会社を構えます。Appian Platformは世界中で多くの企業が導入しているツールで、大規模システムの開発や業務プロセスの自動化、難易度の高いワークフロー構築が強みです。
公式サイトでは「アプリケーションの処理速度が53%アップした」「処理スピードが50%向上した」など、優れた性能を評価する声が紹介されています。
プランはスタンダード・アドバンスト・プレミアムの3つです。料金についてはお問い合わせください。
Zoho Creator

(引用:Zoho Creatorトップページ)
Zohoはインドと米国に本社を置くグローバル企業です。150を超える国でサービスを提供しており、日本にも法人を構えています。Zoho Creatorはシンプルなアプリから複雑なアプリまで構築できるローコード開発ツールで、価格帯も手ごろです。導入のしやすさから、中小企業にも人気があります。
導入ユーザーからは「コードなしで作れる範囲が広い」「構成パーツの細かいところまで配慮が行き届いている」など使いやすさで高評価を得ています。
料金プランは以下のとおりです。
- スタンダード:960円/ユーザー
- プロフェッショナル:2,400円/ユーザー
- エンタープライズ:3,000円/ユーザー
- フレックス:要問い合わせ
※税抜き、月相当・年払い
kintone

(引用:kintoneトップページ)
kintoneはサイボウズ株式会社が提供する国産のローコード開発ツールです。国内での導入実績は高く、大手企業から中小企業まで3万9000社に上ります。kintoneはとにかく分かりやすい画面が大きな魅力で、直感的な操作でさまざまな業務アプリの開発が可能です。
実際のユーザーからは「プログラミングの知識がなくても柔軟にシステムが構築できる」「利用者が多いため事例を調べやすく、問題が起こっても解決しやすい」などの意見がありました。
料金は以下のとおりです。
- ライトコース:月額1,000円/ユーザー
- スタンダードコース:月額1,800円/ユーザー
- ワイドコース:月額3,000円/ユーザー
※税抜き
Pleasenter

(引用:Pleasanterトップページ)
株式会社インプリムが提供している、国産のローコード開発プラットフォームです。シンプルな画面がまるでエクセルのように分かりやすく、スムーズな導入が期待できます。中小企業や業務部門の開発需要に適したツールです。
利用ユーザーからは「マニュアルが細かく、サポート体制も整っている」「使うと良さが分かる」といった評価が見られました。
料金は以下のとおりです。
- フリープラン:無料
- ライトプラン:月額2,500円
- スタンダードプラン:要問い合わせ
- プライベートクラウド:要問い合わせ
Web Perfomer

(引用:Canon「WebPerfomer」)
Canonが提供するローコード開発ツールです。データ構造から設計する「データ中心アプローチ」と、画面を視覚的に操作して開発を進める「画面ファースト開発」の2つから開発スタイルを選べるのが特徴です。現場担当者が画面操作で開発したあとにエンジニアがロジックを補完することもできるので、より柔軟な設計ができるでしょう。
「開発経験がなくても習得しやすい」「サポート体制がしっかりしている」「マニュアルが大量にある」など、操作性の高さや分かりやすさ、サポートの充実度を評価する声が見られました。
料金についてはお問い合わせください。
SPIRAL ver.2

(引用:SPIRALトップページ)
SPIRALは日本のスパイラル株式会社が提供するローコード開発プラットフォームです。2023年5月にver.1からver.2に進化しました。高い操作性とともにセキュリティの高さ、フォローの手厚さが特長で、サポートデスク顧客満足は97%と高い割合を示しています。
「開発経験者・未経験者ともに扱いやすいツール」「ver.1に比べ設計の自由度が大きく上がった」といった意見が見られました。
価格は以下のとおりです。
- 初期費用:10万円
- スタンダードプラン:月額5万円(アカウント管理ができるユーザー上限5名/管理権限はないライトユーザー上限10名)
※税抜き
Wagby EE

(引用:Wagby「Wagby EE」)
Wagby EEは、株式会社ジャスミンソフトが提供するローコード開発ツールです。ノーコード開発としてWagbyも提供しています。Wagbyでは業務アプリを手軽に作成できますが、高度なカスタマイズや複雑な既存システムとの連携が必要な場合は、Wagby EEを選択しましょう。
サーバーごとにランタイムライセンスが必要なProjectとランタイムライセンスが不要なUnlimitedの2つのコースがあります。
以下はそれぞれの料金の目安です。
【Project】
- 開発者:5万160円
- ランタイム:105万6000円
※税抜
【Unlimited】
- 開発者:165万円
- ランタイム:0円
- サブスクリプション:月額6万6000円
※税抜き
ローコード開発ツールの主な機能
ローコード開発ツールには、多様な機能が備わっています。製品によって多少の違いがありますが、以下は代表的な機能の一覧です。
| ビジュアルモデリング | コードをほとんど書かず、パーツをドラッグ&ドロップして配置するなど、直感的・視覚的な操作でアプリを構築できる。 |
| テンプレート・コンポーネントの提供 | よく使われる業務に即したテンプレートや特定の機能を備えたパーツ(コンポーネント)が豊富に提供され、短期間でアプリを開発できる。 |
| ワークフロー機能 | 業務プロセスを視覚的に設計し、申請や承認などの流れを自動化できる。 |
| 外部サービスとの連携 | 既存の社内システムや外部のクラウドサービスと連携できる。 |
上記のような機能により、専門的なプログラミング知識がない人でも短期間で高品質なアプリケーションが開発できます。
ローコード開発ツールを選ぶ際のポイント
ローコード開発ツールにはたくさんの種類があり、それぞれ特徴や強みが異なります。人気があるツールでも自社に合うとは限らないため、導入にあたっては慎重に検討して選定することが必要です。
ここでは、ローコード開発ツールの選ぶ際のポイントを紹介します。
ツールの使いやすさ
操作性の高さや使い勝手の良さは重要なポイントです。基本的にローコード開発ツールは視覚的な画面で直感的に操作できるように設計されているものの、製品によって使いやすさは異なります。資料や公式サイトの説明、評判だけを確認して導入すると、「思っていた以上に運用が難しい」「現場が使いこなせない」といったことになりかねません。
デモやトライアルを実施している製品であれば、導入後に開発に携わる予定の従業員に参加してもらい、積極的に試しましょう。フリープランがあるなら、試してみるのもおすすめです。実際に操作を試すと運用イメージがつかめるため、導入後のギャップをなくすことにつながります。
操作性の高さは開発効率だけでなく、現場の定着率にも大きく関わるため、慎重に見極めましょう。
他システムとの連携のしやすさ
他システムとの連携のしやすさも、契約前に確かめておきたいポイントです。社内の既存システムとの連携がスムーズにできれば、ローコード開発ツールで開発した業務アプリに、社内で蓄積したデータが取り込めます。たとえば、在庫データを同期したり、顧客情報を自動反映したりすることが可能です。
また、開発したアプリで連携先のシステムの機能が利用できるようになるため、ローコード開発ツールで一から機能を構築する手間も減らせます。チャットサービスと組み込んで通知が送れるようにしたり、マップ機能を取りこんだりでき、アプリの利便性を高められるでしょう。
柔軟に連携できるツールを選べば多くのメリットが得られます。業務効率化にも役立つでしょう。
サポートの充実度
スムーズに導入し安定的に運用するためには、サポートが充実していることも大切です。従来の開発方法と比べるとローコード開発は難易度が下がるものの、導入時には「ログインできない」「想定どおりの動きをしない」といったトラブルが起こることも少なくありません。現場担当者などの非エンジニアが使用する場合、慣れるまでには時間がかかる可能性もあります。
そのため、導入時や導入後にどのようにサポートしてくれるかを確認することも大切です。たとえば、導入初期に設定支援が受けられたり、チャットや電話による相談窓口があったりすると、安心して運用を進められます。また、トラブル発生時に迅速に対応してくれる体制が整っているかも確かめておきましょう。
オンラインマニュアルや動画チュートリアル、勉強会など、利用者が自ら学べる環境があると、定着がスムーズになります。
ローコード開発ツールを導入するメリット
ローコード開発ツールの導入を検討するなら、メリット・デメリットの両方を知っておくことが大切です。メリットが大きければ、積極的に導入を検討しましょう。
ここでは、ローコード開発ツールの主なメリットについて解説します。
開発時間を大きく短縮できる
もっとも大きなメリットは、業務に必要なアプリの開発にかかる時間を大幅に短縮できる点です。ローコード開発ではほとんどコードを書かずに、テンプレートやコンポーネントを活用して設計が可能です。
そのため、必要な機能を実装するために一からすべてのコードを記述する必要がある従来の方法に比べ、短期間での開発が可能です。業務に必要なアプリを、現場の担当者が数日で作って活用することもできます。
数日から数週間でリリースできれば、生まれた時間でほかの開発にも着手できるでしょう。また、一つのアプリの開発に人手を取られないため、複数の開発者が同時に設計を進めることも可能です。
多くのアプリを短期間で開発できることで、業務効率や生産性を向上させられます。
開発コストが削減できる
開発にかかるコストを削減できるのも、ローコード開発の魅力です。
ローコード開発は、あまりコーディングをしなくても一定の品質のアプリが開発できます。そのため、ITエンジニアだけではなく、業務部門の担当者などが自分たちの業務を効率化するために、アプリを作成するケースも多いです。
従来の開発方法では、高度な知識を持つ多数のIT人材を長期間確保する必要があり、人件費がかさむ傾向にありました。ローコード開発であれば、IT人材ではなく現場の担当者でも開発可能なため、人件費を抑えることが可能です。
また、基本的に開発にかかる費用は工数に比例します。ローコード開発では短期間で設計できるため、トータルで開発にかかるコストの削減効果が期待できます。
ローコード開発ツールを導入するデメリット
ローコード開発ツールには、メリットも多い一方、デメリットも存在します。どのようなデメリットがあるかを把握し、メリットが上回るかどうかをしっかりと見極めることが大切です。
ここでは、主なデメリットについて解説します。
学習コストがかかる
ローコード開発ツールを使えば、高度な専門知識がない場合でも基本的な開発は可能です。とはいえ、操作方法はしっかり理解する必要があります。また、ツールの機能を最大限に生かすためには、操作の習熟が欠かせません。
多機能なローコード開発プラットフォームを導入した場合、開発を担当する従業員の学習コストがかかる可能性もあります。
ベンダーロックインの恐れがある
ローコード開発ツールを使った開発を進めると、ベンダーロックインが起こる可能性が指摘されています。ベンダーロックインとは、特定ベンダーの製品に依存することで、他社製品への移行が困難になる状況を指します。
仮にサービス終了などが起きたとき、開発したアプリの運用ができなくなる恐れがあります。契約する前に、ベンダーの安定性や将来性をしっかり見極めることが重要です。
企業が管理していないシステムが乱立する可能性がある
ローコード開発ツールを使うと手軽に業務に必要なアプリが構築できますが、管理体制が整っていないと、IT部門が把握していないシステムが乱立する可能性があります。
こういった「野良システム」の乱立はデータ重複やセキュリティリスクなどの問題を招きかねません。防止するためには、適切な管理体制やルール作りが必要です。
開発者でも中身がわかりにくい
開発者がコードを書かなくても設計できるローコード開発ツールは、裏でソースコードを自動生成し、処理を行っています。そのため、開発者は具体的に何がどのように動いているのかを正確に知ることができません。
そのため、不具合が起こったときに原因を突き止めづらいといった問題があります。
カスタマイズに制限がある
ローコード開発ツールを使うと、提供されたテンプレートを活用したり、コンポーネントを組み合わせたりすることで、アプリの設計が簡単にできます。裏を返せば、提供された機能以外を実装したくてもできないケースがあるということです。
ある程度はコーディングで対応できますが、独自の複雑な仕様を実装したい場合、ローコード開発ツールでは限界があることも知っておきましょう。
ノーコードとローコードの違いとは
ローコード開発と似ている開発手法にノーコード開発があります。以下は、それぞれの違いをまとめた比較表です。
| ノーコード開発 | ローコード開発 | |
|---|---|---|
| コーディングの有無 | コードを書かず、GUI操作のみで開発 | 基本はGUI操作で、必要に応じてコーディング可能 |
| 対象ユーザー | 非エンジニア中心 | エンジニア・非エンジニアの両方 |
| カスタマイズの自由度 | 低い | 一定程度はある |
| 主な用途 | 特定業務のアプリなど | 中規模以上の業務アプリ 基幹システムとの連携も可能 |
ノーコード開発は、文字どおり開発者がまったくコードを書かず、GUI上の視覚的な操作のみで開発を行う手法です。専門知識のない従業員でも業務アプリが設計できます。ただし、カスタマイズの自由度は高くありません。
一方、ローコード開発は、コーディングせずにGUI上の操作のみでアプリが構築でき、必要に応じてコードを書き加えて独自の機能も実装できます。IT知識のない現場担当者が基本的なアプリを開発し、エンジニアが高度なカスタマイズをすることも可能です。
また、他サービスとの連携もできます。特定の部門で使用する簡易的な業務アプリから、基幹システムと連携させる中規模なアプリまで対応できます。
ノーコードで業務改善を目指すなら「esm appli」
ローコード・ノーコードプラットフォームは、開発コストとスピードの面で大きなメリットがありますが、実際に業務改善を成功させるには「現場の業務にどれだけフィットするか」が鍵となります。
特に営業部門では、商談管理や顧客管理、日報などの基幹業務に加え、細かな申請業務や稟議フローが常に発生しています。
esm appliは、国産SFA/CRMで実績のあるesm(eセールスマネージャー)が提供するノーコードツールであるため、営業活動とシームレスに連携できることが強みです。
例えば、複雑な見積もり申請、キャンペーンの進捗管理、クレーム対応の報告フローなど、既存のSFAではカバーしきれないニッチな業務や急なニーズにも柔軟に対応可能です。
勿論、営業業務以外にも社内問い合わせ管理や資産管理など幅広い用途で使用可能です。
まとめ
本記事では、おすすめのローコード開発ツールを紹介し、選び方や導入のメリット・デメリットなどについて解説しました。ローコード開発ツールを使うと、高度な専門知識のない人でもアプリを開発でき、業務効率を高めることが可能です。必要に応じて、エンジニアなどの知識のある人がコードを書いて独自の機能を実装することもできます。
開発スピードを大幅に短縮でき、開発コストも削減できる点が大きな魅力といえるでしょう。とはいえ、自社に合っているツールを選ばなければ、うまく使いこなせずに終わることもあります。導入前に目的を明確化し、自社に最適なツールを選定することが重要です。
紹介したおすすめツールや選び方を参考に、ぴったりのものを選び、活用してください。