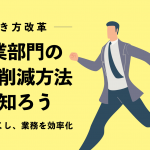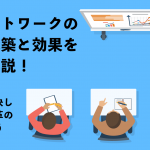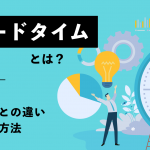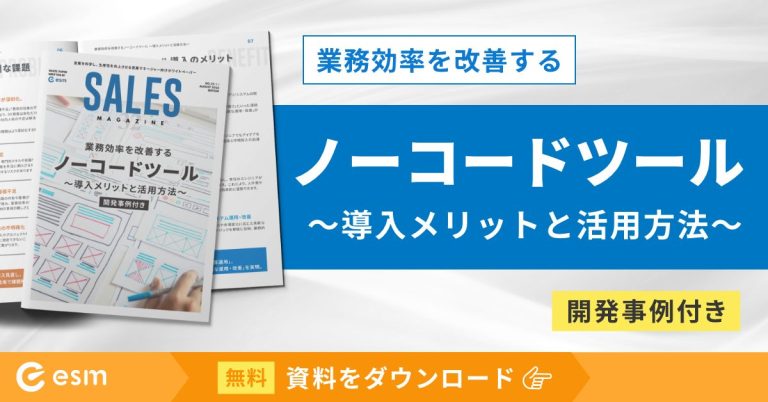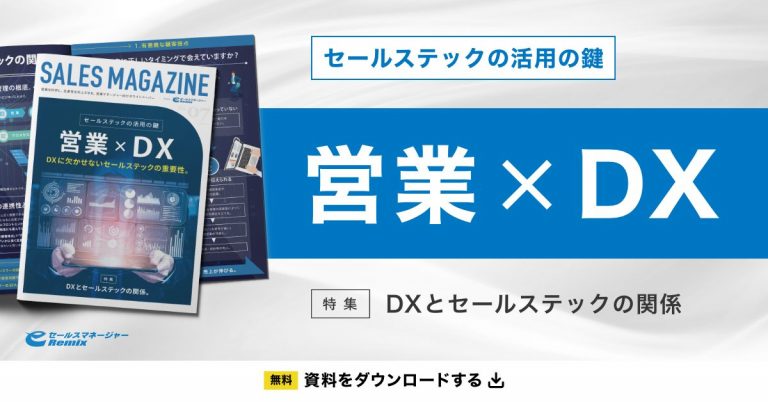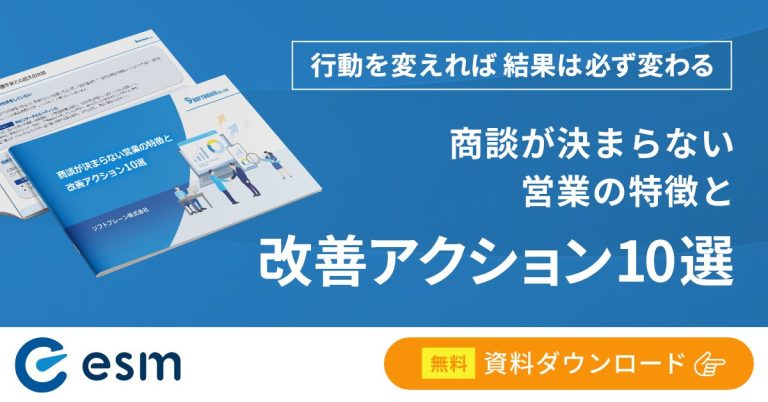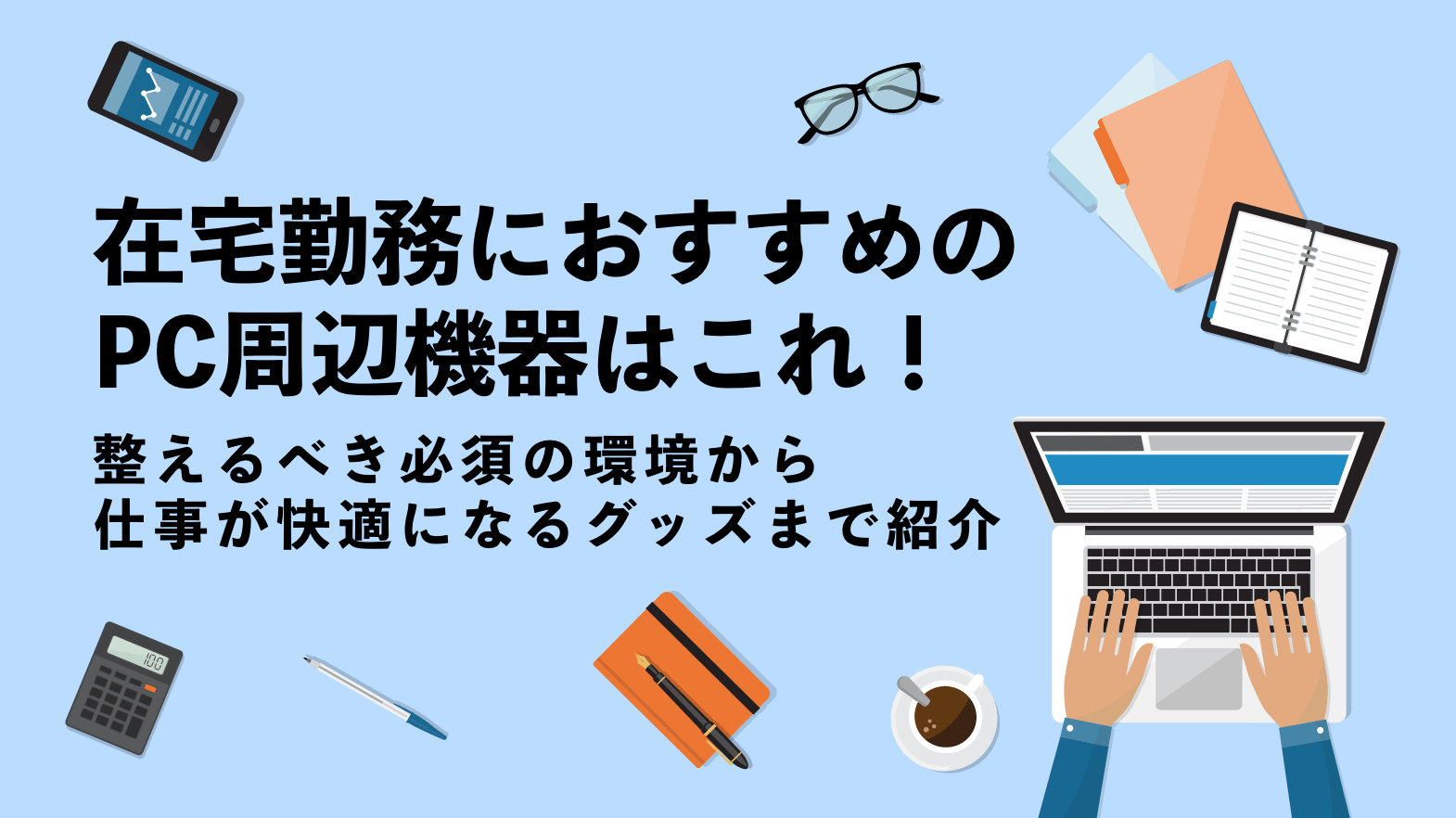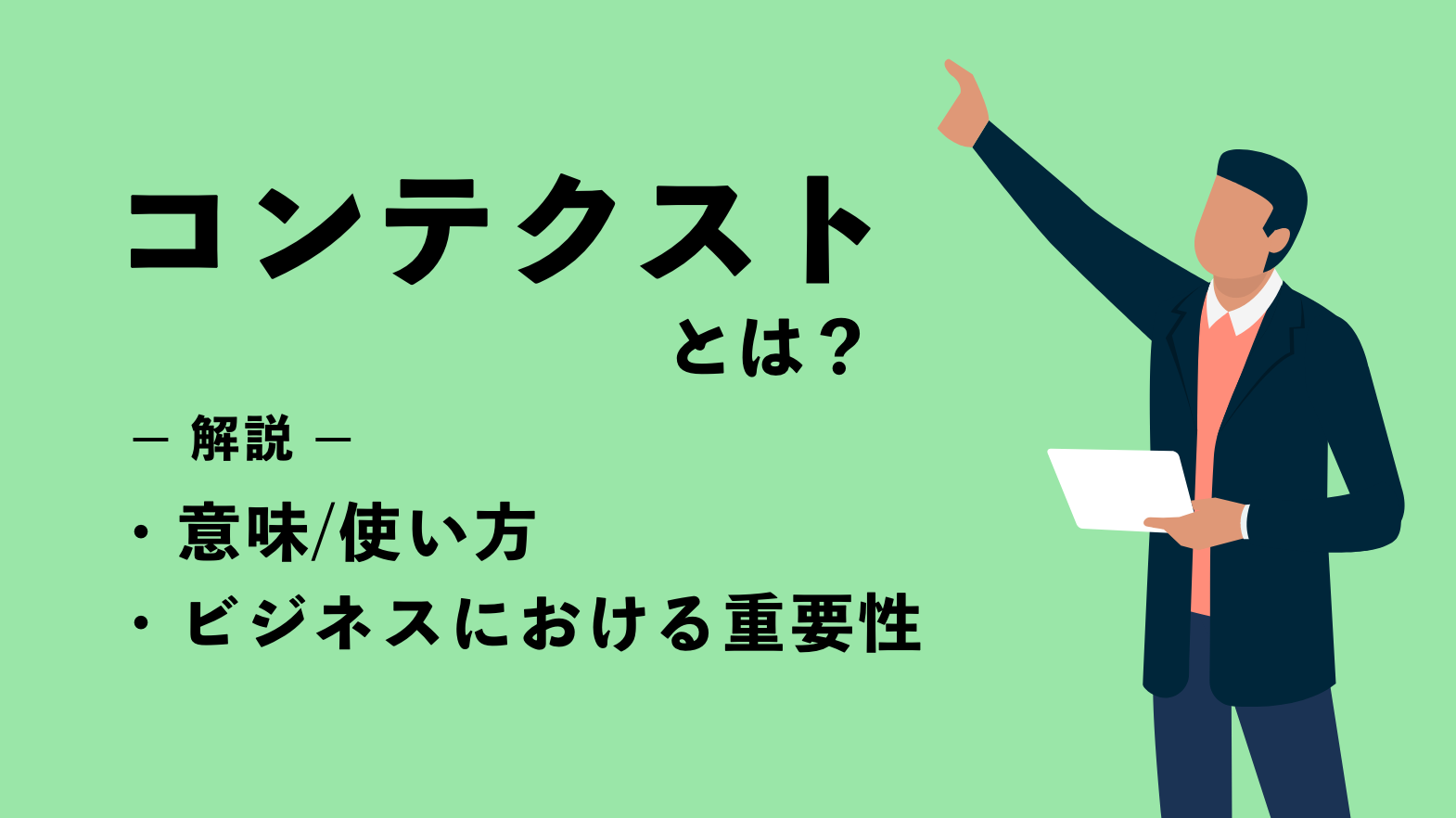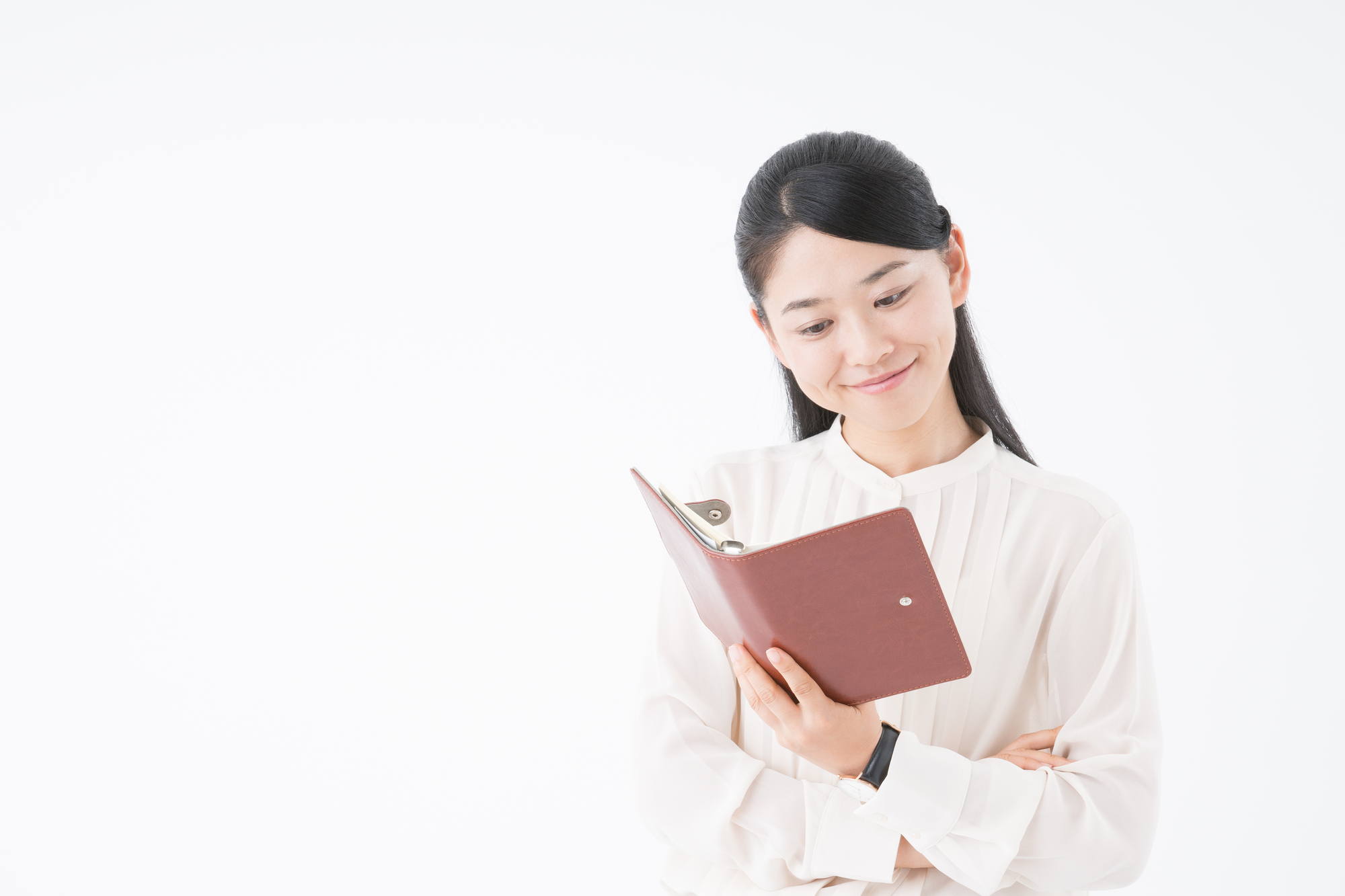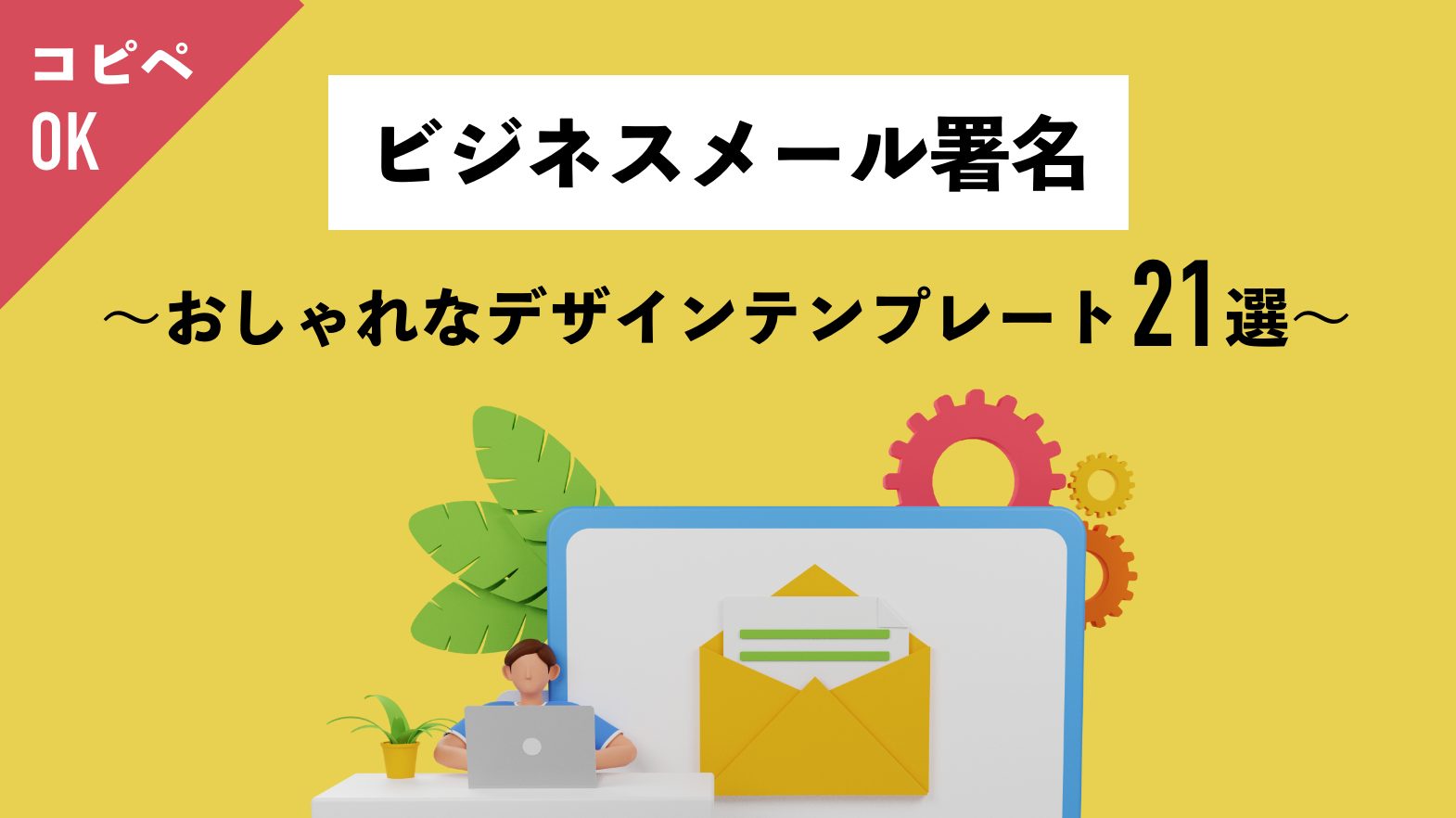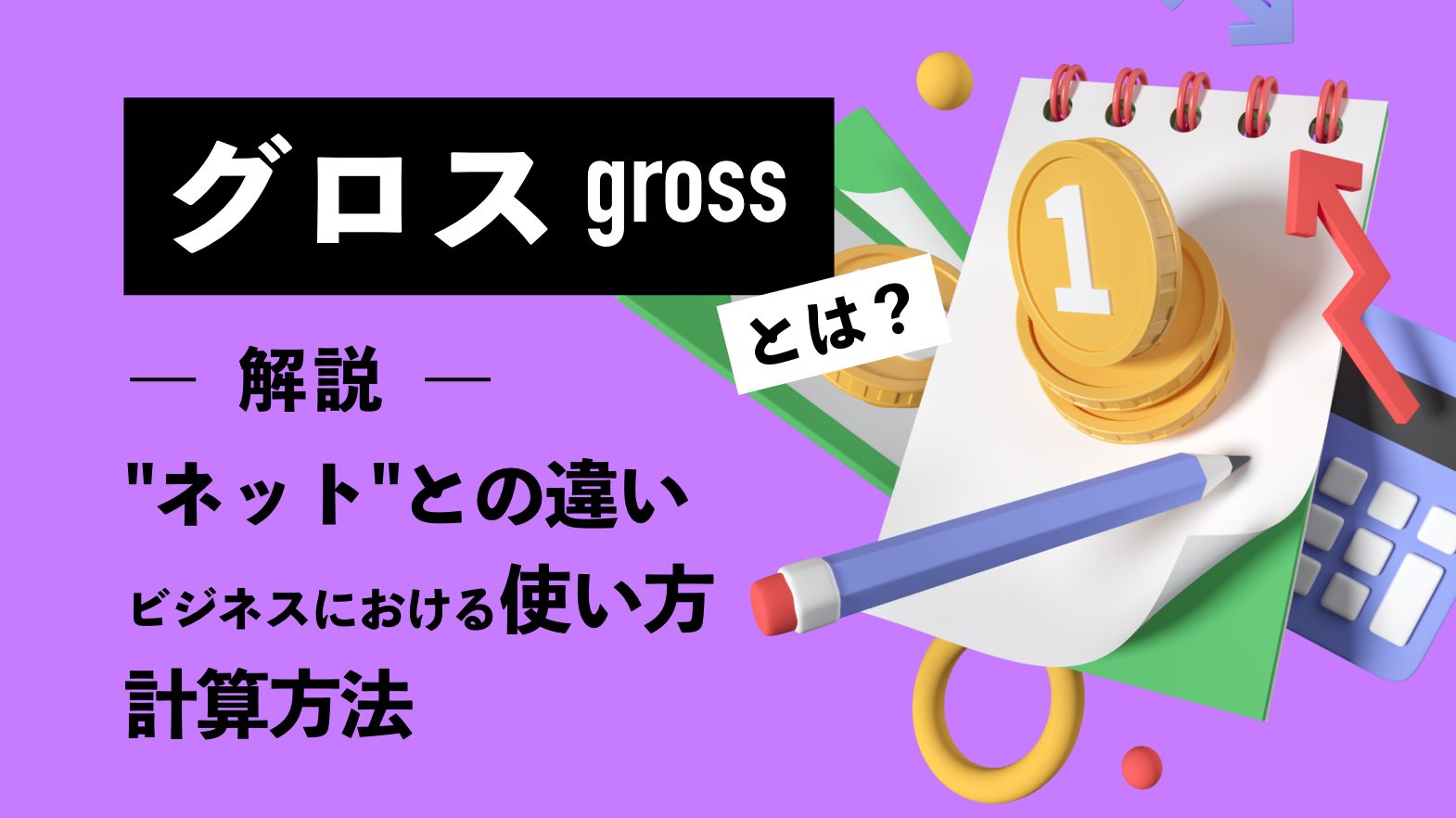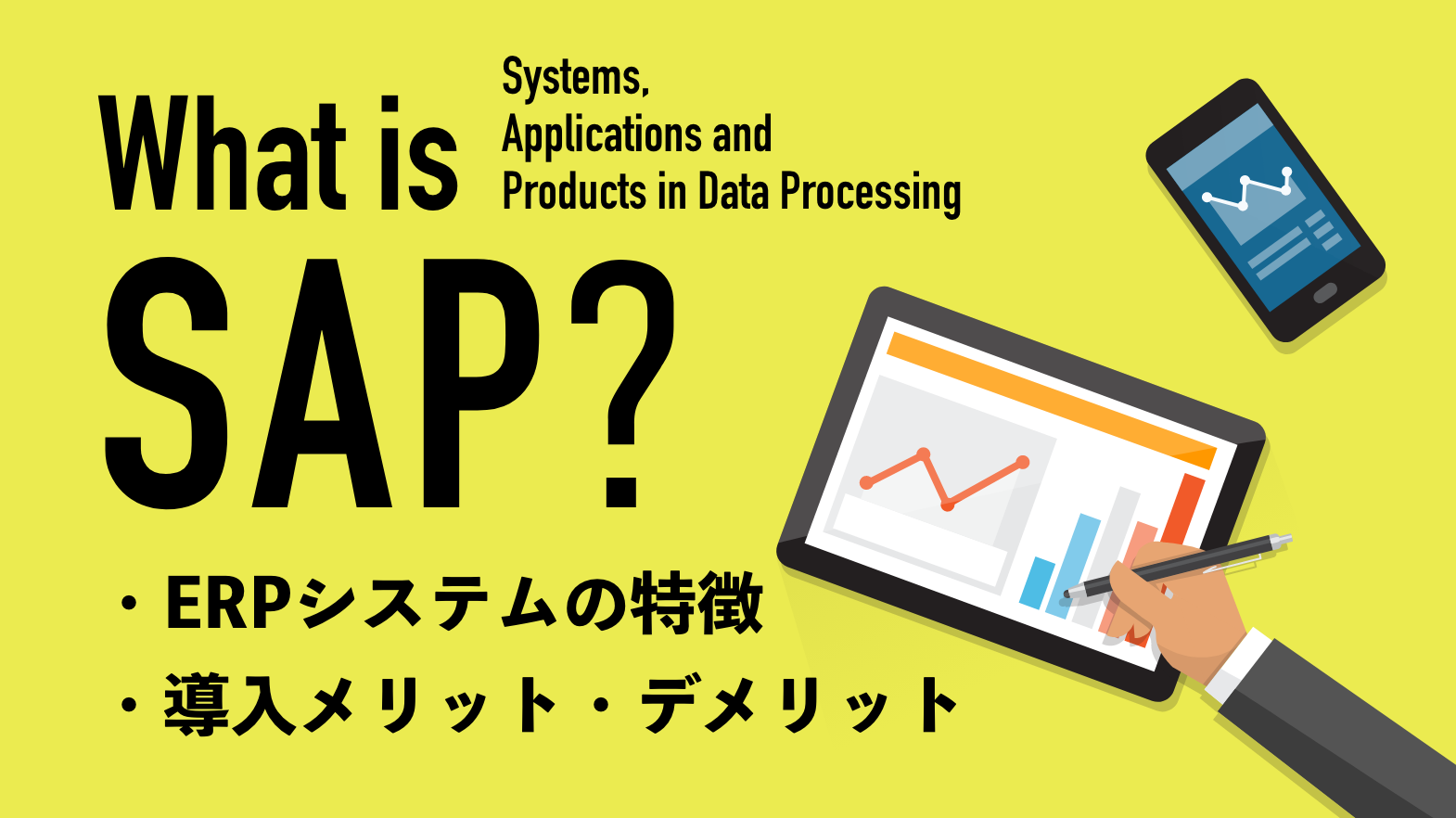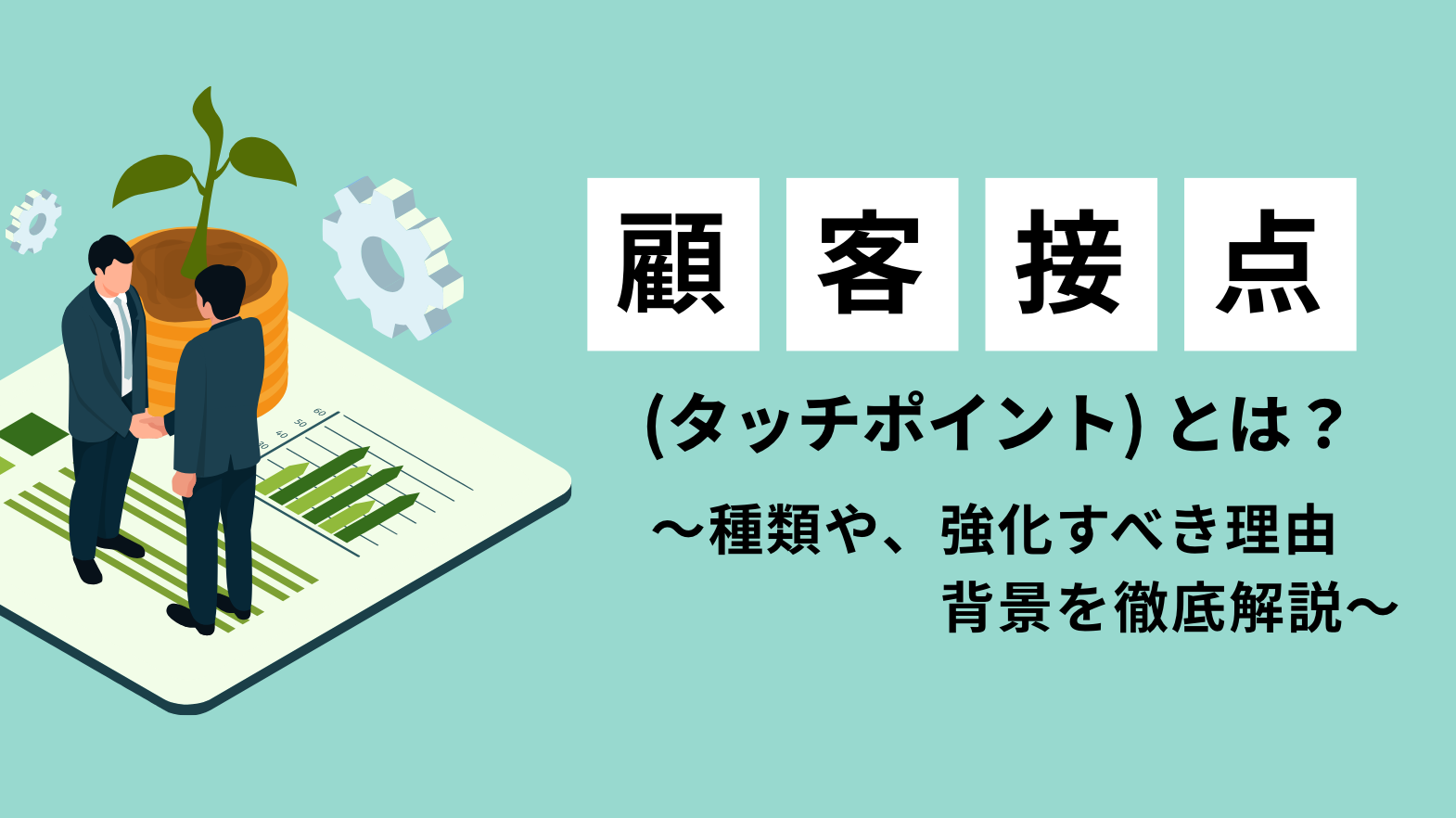パッケージ型顧客管理システム(CRM)のおすすめを比較!オンプレミス型やクラウドとの比較や製品選定について
ビジネスの現場において一般化しつつあるCRMツールによる顧客管理ですが、CRMツールには、おおまかに分けてオンプレミス型とクラウド型の2種類があります。
パッケージ型・オンプレミス型CRMとは、自社のサーバ内で構築・運用するタイプのCRMのことを指します。
これに対して、社外のサーバでCRMを利用する、クラウドサービスの利用が現在では進んでいます。
今回は、CRMを導入する場合の、クラウドとの比較選定ポイントを徹底解説いたします。
このページのコンテンツ
パッケージ型/オンプレミス型とは?

パッケージ型とは、ソフトウェアを購入して自社のPCやサーバーにインストールして利用するタイプのものを指します。
一方、オンプレミス型は自社のサーバにITサービスを構築・運用することを指します。
これに対して、インターネットを介して社外のサーバ上にあるITサービスを利用するクラウドサービスの普及が進んでいます。
しかし、実際に社内のITサービス全体を見ると、高度なセキュリティのレベルを求められるデータの取り扱いや、今まで利用していたレガシーソフトウェアを今後も使い続ける必要がある、といった理由で、クラウドに切り替えることが難しいITサービスもあるでしょう。
こうした理由で、クラウド型とパッケージ型はほとんどの企業で共存していくものと考えられます。
また、クラウドにアクセスしてデータを利用することにはパフォーマンスの問題があり、ビッグデータ時代においては、クラウドとパッケージ型とをうまく使い分ける必要もあるでしょう。
クラウド型についても知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
パッケージ型・オンプレミス型とクラウド型について

パッケージ型・オンプレミス型とクラウド型の違いについて
まず、パッケージ型とオンプレミス型の違いを説明しましょう。
最も大きな違いは、自社カスタマイズのしやすさです。
パッケージ型は、カスタマイズには追加コストがかかることが多いのに対し、オンプレミス型は、自社に合わせたカスタマイズがしやすい点が特徴です。
機能性も、パッケージ型は価格に依存しているのに対し、オンプレミス型は基本的に機能性が高いと言ってよいでしょう。
次に、クラウド型がパッケージ型・オンプレミス型と違う点ですが、最も大きな違いは自社サーバーが必要か否かです。
パッケージ型とオンプレミス型では自社サーバーが必要ですが、クラウド型ではインターネットを介してベンダーの提供するサービスを利用するため、自社サーバーは不要です。
また、新機能もアップデートにより自動で追加されるところが特徴です。
パッケージ型・オンプレミス型とクラウド型では、どちらがよいとは一概に言えません。
先述した通り、双方は共存する関係であり、この状況はしばらく続く見通しです。
しかし、個別のサービス・ソフトウェアの導入の場面では、どちらかに決めることが必要となるため、選定に悩むところでもあります。
※パッケージ型・オンプレミス型とクラウドを比較する前に、クラウド型CRMの特徴について詳しく把握したい方はこちらをご覧ください。
重要な比較対象11項目
選定に悩む場合は、パッケージ型・オンプレミス型とクラウドを11項目で対比し、判断材料とすることをオススメします。
比較検討の項目をあげてみます。
主に以下の部分で検討することが多いでしょう。
- 初期コスト …導入コストと、導入までの期間≒人件費の合計を検討対象とします。
- 利用コスト…数年間のトータルで考える必要があります
- インフラ調達期間…主にネットワークインフラの調達・サーバの調達が考えられます
- カスタマイズ・アップデート…カスタマイズが必要かどうか。また、サービスの中には常に最新の状態に更新されていることに意義があるものもあります
- 災害対策コスト…クラウドベンダーと自前とで、想定する災害にどれほどのコストがかかるか、比較が問題になります
- IT人員の配置…専門のIT人員が配置されていることで、クラウドよりも高度・自社の事情に合わせた施策・インフラ導入などが可能になることもあります
- 自社でのメンテナンスの要否…⑥と密接に関連するところなので、ワンセットで検討するのが適切でしょう。メンテナンス人員が足りなければ、メンテナンスを要するサービスの導入は一般的に難しくなります
- サーバのスペックアップ・ダウン…パッケージ型・オンプレミス型のアプリケーションを導入するとき、このことが問題になるケースがあります
- ロケーション変更…ネットワークの「場所」を変更することですが、ネットワーク構成変更に伴うものが代表的です。特に、オンプレミス型の場合に必要になることがあります
- 既存システムとの連携…④のカスタマイズの可否とも関係しますが、サービス内容に規定されるクラウドと、カスタマイズ次第になるオンプレとで可否に差が出ることがあります
- 障害対応…自社で行った場合と、クラウドサービス業者に行わせた場合のコストの問題に還元される場合が多いでしょう
これらを見てもわかる通り、どちらが絶対によい、ということではなく、サービス選定・導入の際に、自社ではどの要素を重視するかを検討して使い分けることが現実的です。
パッケージ型・オンプレミス型とクラウド データ管理におけるそれぞれの留意点

オンプレミス型とクラウドを比較する際には、それぞれのサーバに格納するデータの管理に関する留意点があります。
具体的には、日本の個人情報保護法・番号法や、EU居住者の個人情報に関するGDPR(EU一般データ保護規則)などの法規制を考えた場合に、安全管理策をどちらが取りやすいか、また、証明しやすいかという問題です。
オンプレミス型とクラウドを、データ管理を軸にして比較すると次のように整理できます。
パッケージ型・オンプレミス型の場合
パッケージ型・オンプレミス型は監督官庁や取引先への説明が比較的、容易です。
取引先の中には、ハードにクラウドを用いることは禁止する規則を採るところもいまだにあります。
また、証明のためのエビデンスを自社で揃えることが可能です。
しかし、体制を作るまでのコストはかなり負担となるでしょう。
クラウドの場合
業者からのエビデンスに依存するので、選定時にISOなどのエビデンスの入手ができるかどうかに留意する必要があります。
エビデンスが入手できれば、初期コストがかからない場合も多く見受けられます。
なお、パッケージ型・オンプレミス型とクラウド双方とも、法令・ガイドラインに定められた個別の安全管理策、例えば分離保管(マイナンバーの場合重要)・アクセスログの保管・ラベリング・廃棄などをクリアしていないといけません。
パッケージ型・オンプレミス型とクラウドどちらも安全管理策上の問題が残るので、最低限クリアするように注意しておきましょう。
CRMでのパッケージ型・オンプレミス型/クラウド型比較/選定ポイント
比較の視点
クラウド型CRM
クラウド型CRMの場合、11項目のうち初期コスト・メンテナンス・アップデート・既存システムとの連携・IT人員・障害対応の比較が重要になります。
パッケージ型・オンプレミス型CRM
パッケージ型・オンプレミス型CRMの場合、初期コスト・IT人員・障害対応の点でコストがかかりがちです。
また、既存システムとの関係でどうしても切り替えが難しい場合もあります。
そうした場合は、既存システムを入れ替えるコスト・数年スパンでの見通しなどを考えて、トータルコストの比較をクラウドサービスとの間で検討しておく必要があります。
データ管理上の留意点
CRMは、データをサーバに蓄積して利用します。
- オンプレミス型のアプリケーションの場合…自社サーバにデータを蓄積し、管理します。
- クラウドサービスの場合…アプリケーションに接続されているクラウドサーバにデータを蓄積し、自社ではなくサービス業者がデータを管理することになります。
個人情報の取り扱いがあるため、データ管理上の留意点を考えて、選定することが重要です。
オンプレミス型とクラウドを双方使う必要性とは?

クラウドに依存しすぎることの弊害
クラウドは、データをデータセンターに格納しますが、利用時に大量のデータの送受信が行われます。
そこで、パフォーマンスが重要になります。
実際、主要なサービスでパフォーマンスの面が問題になっており、データセンターの増設など、問題の解決が図られていますが、「いたちごっこ」が続きそうな模様です。
利用するクラウドサービスのパフォーマンスが良くない場合、自社のコントロール外のことになってしまいますが、自社のユーザーに対するサービスとしてパフォーマンスの質の低さは大きな問題となるでしょう。
また、データ管理には、法制度対応も問題になります。
おそらく今後、個人情報の管理は厳しくなることはあっても緩まることはないと考えられます。
クラウドサービスのアップデート・緊急のデータ保護が、現在、利用しているベンダーのクラウドサービスで今後も十分に賄えるかは、海外のクラウドサービスの場合はとくに不透明と言えます。
オンプレミス型でのデータの分散処理で弊害を回避
クラウドサービスのパフォーマンスが良くない場合の解決策としては、分散処理を採ることが考えられます。
たとえば、大量のデータを扱うのに、いちいちクラウドから引き出すのではなく、オンプレミス型のサーバに一定のデータを置いておき、分散して処理することも必要になるものと考えられます。
分散処理だけでなく、オンプレミス型サーバに一部の個人データなどの法規制の対象データを保管し、後はクラウドサーバに置いておく、という運用方法は、データの管理という観点からも有効な施策となるでしょう。
すべての個人データ等の要保護データが、同じ規制に服するとは限りません。
そのため、分別・分離など、安全管理策の実現に複数以上の手段をもつことと、その1つの実現手段として、オンプレミス型とクラウドを使い分けることは、合理性のある取り扱いであると考えられます。
まとめ:CRM導入では適切に選定/使い分けることが鍵

CRM導入でパッケージ型・オンプレミス型とクラウドを、どちらが良いというわけではない、ことを前提として比較の視点を提示してきました。
自社のIT環境とCRMの性質に応じて、双方を適切に使い分けることが必要であると同時に、いずれかにのみ偏るような運用は、特にクラウドの現状を考えると維持するのが難しいと考えられます。
双方をバランスよく利用して、社内のIT運用を安定的に行うために、この記事の比較の視点を活用することをおすすめします。