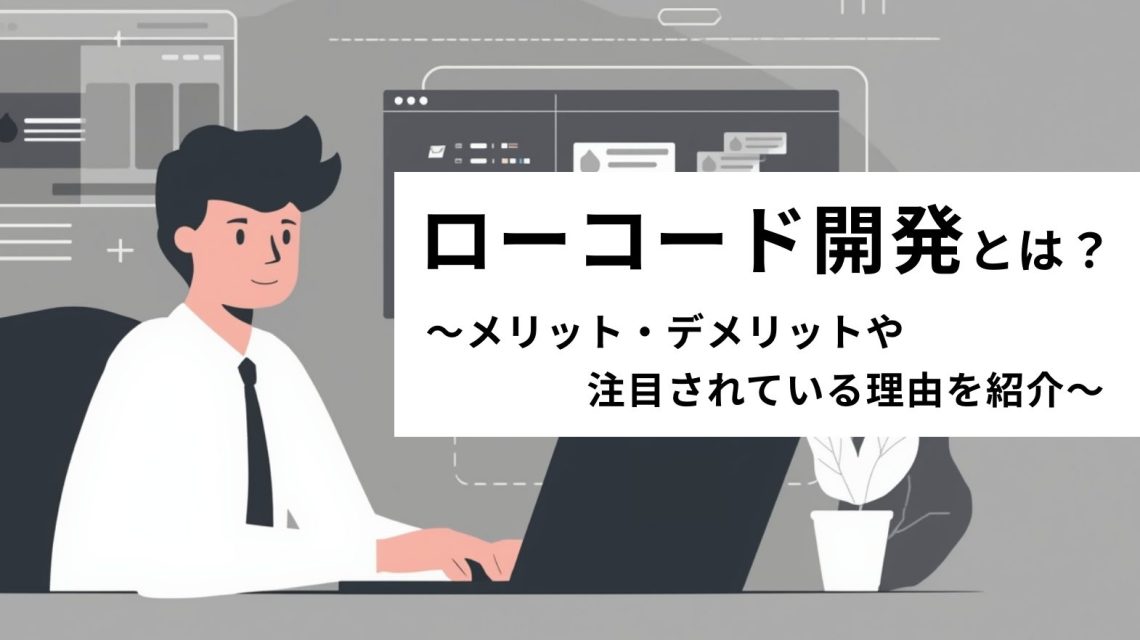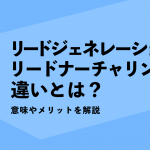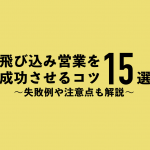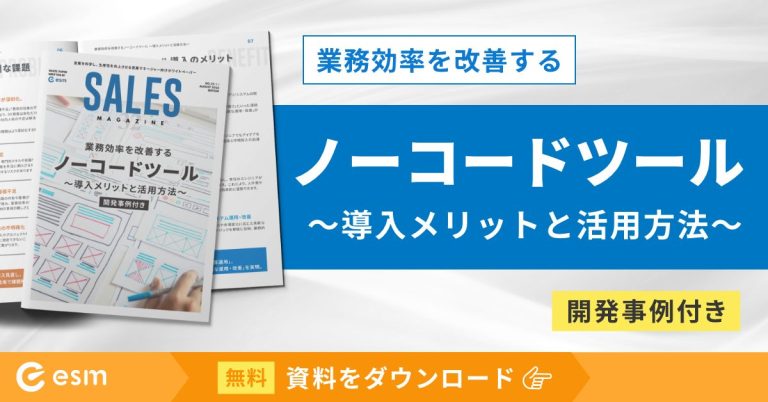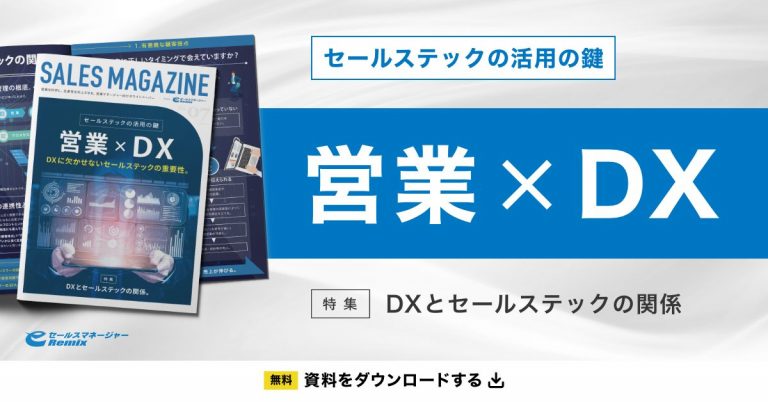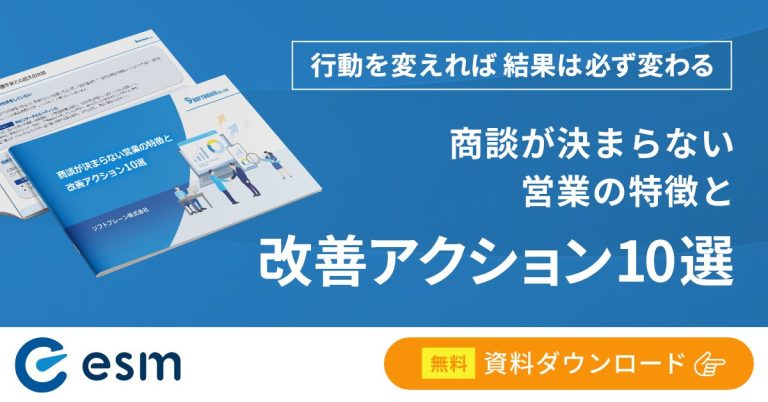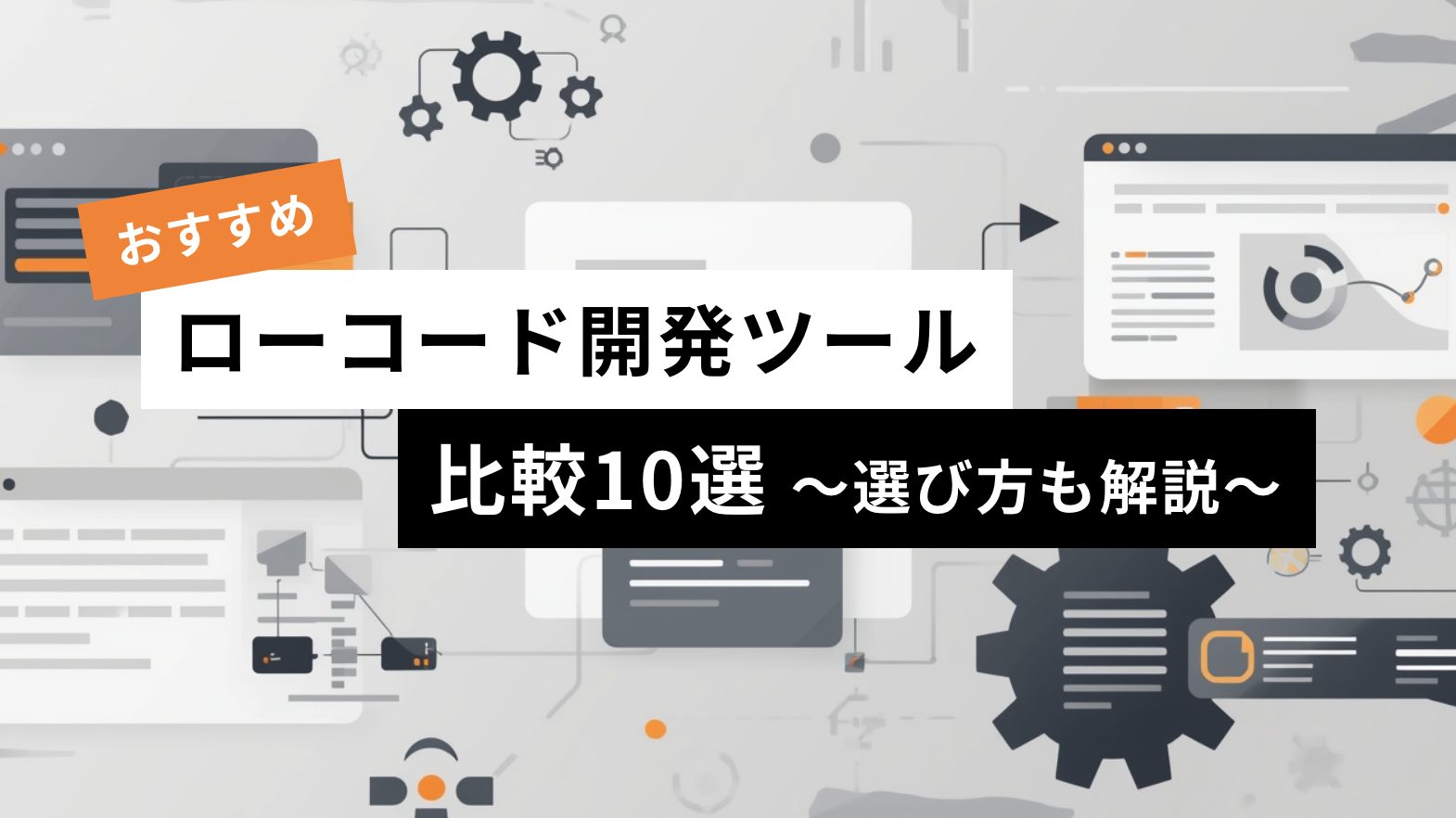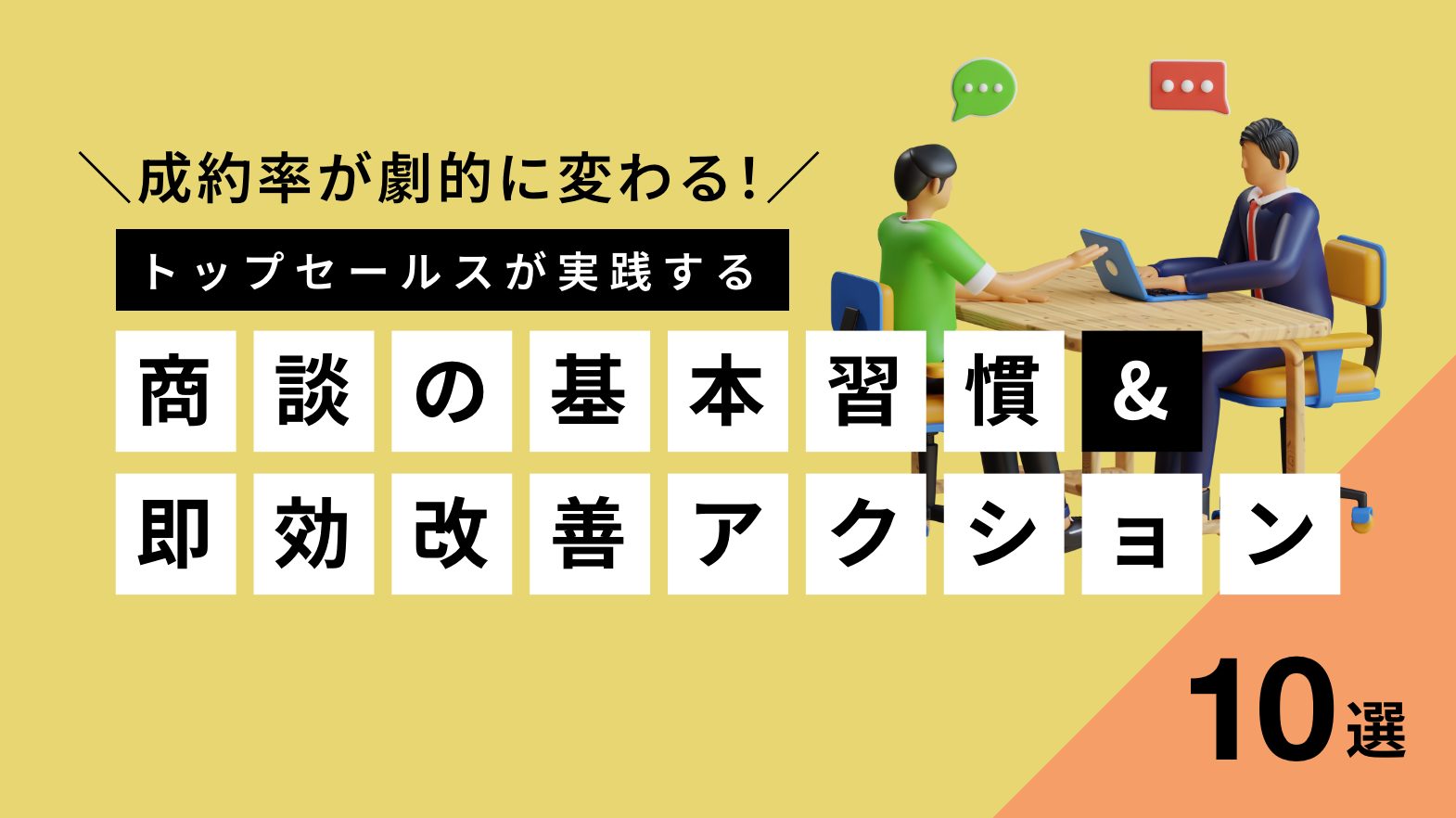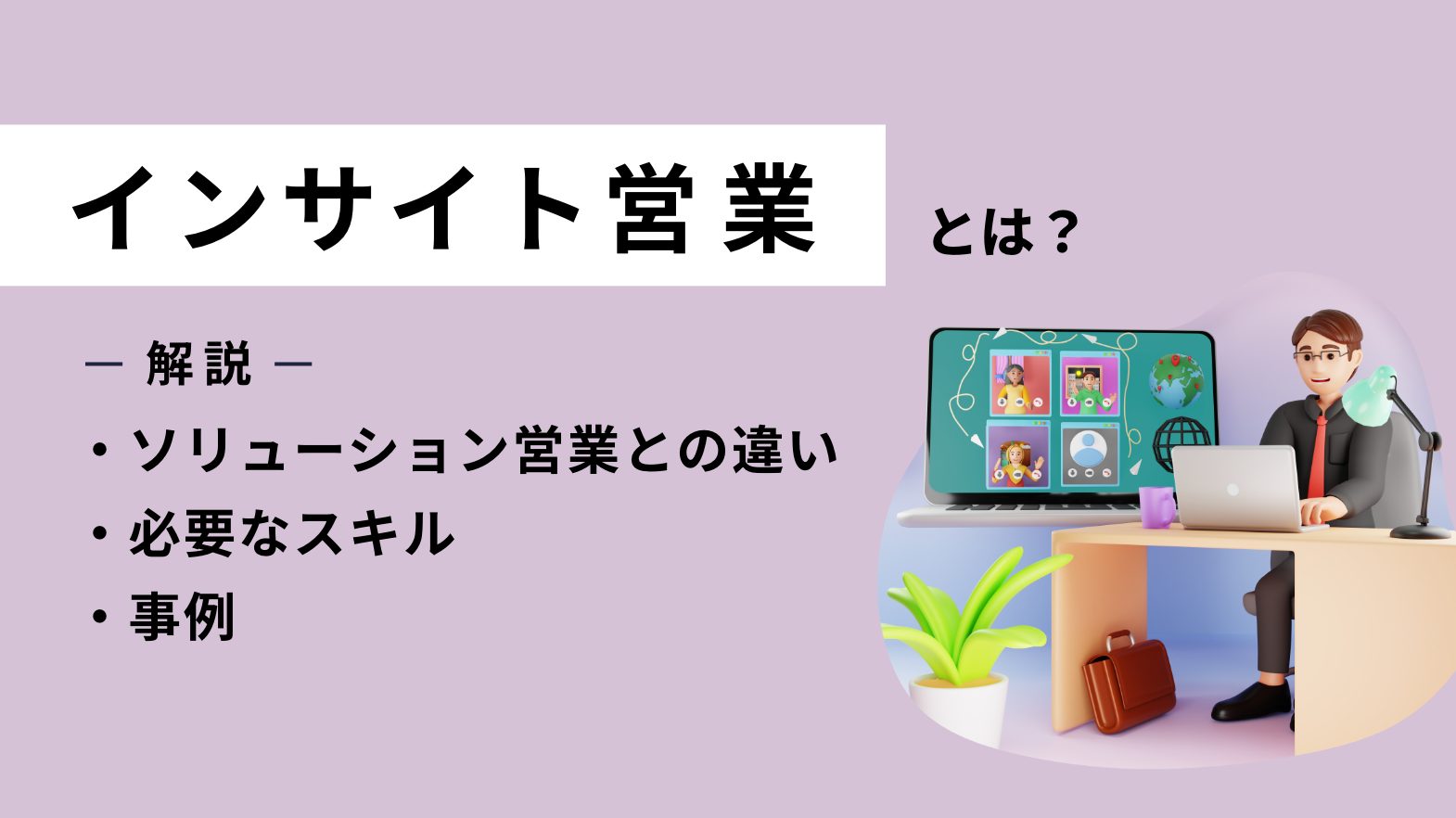ローコード開発とは?メリット・デメリットや注目されている理由を紹介
近年、ローコード開発が多くの企業から注目を集めています。IT人材の不足をカバーし、DXによる開発需要の増大に迅速にこたえられる開発手段になりうるためです。
とはいえ、具体的にローコード開発がどのようなものか、どのようなメリット・デメリットがあるのか分からず、導入を迷っている担当者の方もいるのではないでしょうか。
本記事では、ローコード開発の概要や注目を集める理由、ほかの開発手法との違い、導入手順などについて詳しく解説します。ぜひ参考にしてください。
このページのコンテンツ
ローコード開発とは
ローコード開発(Low-Code Development)とは、専門的なプログラミング知識を使わずにアプリケーションやシステムを開発する手法です。GUI(グラフィカルユーザーインターフェース)で、特定の機能を持つ部品を配置・設定して開発を進めます。画面上で操作することで、コードを書かなくても一定の品質のアプリケーションを短時間で作成できる開発手法です。
複雑な仕様が必要な場合などは、対応する言語でコードを書いて、カスタマイズしたり特定の機能を付加したりすることもできます。
ローコード開発が注目されている理由
ローコード開発が注目されている背景には、産業界におけるDXの加速とIT人材の慢性的な不足があります。一からコードを記述して行う従来の開発方法は、IT知識を持った多数の人材と時間が必要です。しかし、必要なIT人材が不足している企業も多く、時間をかけて開発していては、変化の速いIT時代に対応することはできません。
ローコード開発であれば、業務に必要なアプリやシステムが少人数かつ短時間で開発できます。また、プログラミングについて深い知識がない人材でも開発にかかわれるため、IT人材の不足を補うことも可能です。この2点が、ローコード開発が注目される大きな理由といえます。
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは
DXとは、ビッグデータやAIといったデジタル技術を活用し、事業内容や組織体制、業務プロセスなどを変革することです。変革を重視する点において、単にデジタル技術を活用して業務の効率化や生産性の向上を図るIT化とは異なります。DXは、デジタル技術によって従来では難しかった新しい価値を提供し、企業に付加価値をつけて市場での競争力を高めることまで含みます。
企業が時代の変化に合わせ柔軟に対応していくためには、DXの推進が欠かせません。企業にとってDXは喫緊の課題であり、そのために必要なのが、スピーディに開発できる環境です。
ローコード開発のメリット・デメリット
ローコード開発にはさまざまなメリットがある一方、いくつかのデメリットもあります。自社で導入を検討している場合は、良い点も悪い点も正確に理解しておくことが大切です。
ここでは、ローコード開発の主なメリット・デメリットについて解説します。
メリット
ローコード開発の主なメリットとしては、以下の点が挙げられます。
- エンジニアでなくても業務に必要なアプリが開発できる
- 工程を簡略化でき、開発にかかる時間を大幅に短縮できる
- 属人化しにくい
ローコード開発では、コードを書かなくてもベーシックなシステムであれば構築可能です。エンジニアではない現場の人間でもアプリを開発できるため、IT部門の負担を軽減できます。
また、コードを書く必要がないことで、短期間での開発が可能です。要件定義から実装まで数か月やときに数年かかっていた従来の方法に比べ、リリースまでの期間を大幅に短縮できるのは、大きなメリットといえます。
属人化しにくいのも、ローコード開発のメリットです。あらかじめ用意された部品を組み合わせてシステムを構築するため、開発担当者のスキルによらず、一定の品質を保てます。
デメリット
一方、デメリットとしては以下の2点が挙げられます。
- カスタマイズ性や拡張性に限界がある
- ほかの製品への乗り換えが難しくなることがある
開発の自由度が高い従来の方法とは異なり、機能の範囲内で設計するローコード開発では特殊な仕様に対応できない場合があります。
また、特定のローコード開発製品に依存しすぎると、ほかの製品への乗り換えが難しくなる点もデメリットです。サービス元の事業者が提供をやめてしまうと、構築したアプリやシステムが使えなくなる恐れがあります。契約の際は、事業者の将来性や安定性を十分にチェックしたほうがよいでしょう。
ローコード開発プラットフォームとは
ローコード開発製品のなかには、ローコード開発ツールのほかに、ローコード開発プラットフォームと呼ばれるものもあります。ローコード開発ツールは、文字どおり、自分でコードを書かずに視覚的な操作だけでアプリやシステムが開発できるツールのことです。
ローコード開発プラットフォームも、コーディングなしでの開発が可能な点はツールと同じです。プラットフォームの場合は、さらに、デプロイやソースコードの管理、保守といった幅広い範囲にも対応している点が異なります。いわば、ローコード開発全般を進める際の土台や基盤となる環境です。
ローコード開発プラットフォームの多くは、PaaS(Platform as a Service)の形式で提供されています。利用者は、開発用の専用ソフトをインストールする必要がありません。手間がかからず、スムーズに開発に取りかかれるのが大きな利点です。
ローコード開発プラットフォームが注目される理由
ローコード開発プラットフォームは、必要な開発環境が実現できるとして多くの企業から注目を集めています。ほかの開発環境にはない特徴があるためです。
ここでは、ローコード開発プラットフォームが注目を集める主な理由について具体的に解説します。
開発のスピードが速い
ローコード開発プラットフォームが注目されている主な理由として、開発スピードが速い点が挙げられます。ローコード開発では、あらかじめ用意された特定の機能を持つ部品を組み合わせ、必要な要件を実現します。そのため、従来の開発手法に比べて大幅に運用開始までの期間を短縮することが可能です。
従来であれば長期間かかっていたシステムが、数週間で開発できたといったケースもみられます。ローコード開発プラットフォームがあれば、DX推進に伴って増加する開発需要にスピーディに対応できます。
また、高度な専門知識を持つエンジニアだけでなく、非エンジニアでもある程度のアプリの構築が可能です。現場の担当者が自分たちの求めるシステムを形にできるようになれば、IT部門の負担は軽減するでしょう。その結果、全社でDXを推進しやすくなります。
運用・保守までスムーズにできる
アプリを構築して終わりではない点も、ローコード開発プラットフォームが注目されている理由です。従来の開発環境では、構築したあとのアプリを運用したり、不具合修正やバージョン更新などの保守をしたりする場合、IT部門や開発者が個別に行う必要があります。運用や保守は手作業で行うため、時間もコストもかかることは避けられません。
ローコード開発では、クラウド上で、開発だけでなく公開、運用、保守まで一元的に管理できます。ワンクリックでアプリを更新したり、バックアップやバージョン管理を自動で行ったりできるため、IT部門や開発者の手間がかかりません。その分、より重要な業務に時間を割くことが可能になります。
設計開発だけでなく、保守まで管理できる点も、ローコード開発プラットフォームが注目されている理由です。
ローコード開発におけるシチズンデベロッパーが果たす役割
シチズンデベロッパーとは、ローコードやノーコードの開発プラットフォームを使ってアプリ開発を行う現場担当者のことです。プラットフォームを活用してアプリを開発する非エンジニアのシチズンデベロッパーは、DX推進に不可欠な存在といえます。
ローコード開発においてシチズンデベロッパーが果たす役割は、主に以下の2点です。
- 現場視点で実用的なアプリを構築する
- IT人材の不足をカバーする
現場視点で実用的なアプリを開発できる点は、シチズンデベロッパーならではの強みです。現場の外にいるIT部門のエンジニアは、どれだけヒアリングを重ねても、業務における課題を完全に把握することは難しいでしょう。
現場で働くシチズンデベロッパーであれば、業務の内容に精通し課題も把握していることから、どのようなアプリが必要か分かります。
多くの企業が直面しているIT人材の不足を補うのも、シチズンデベロッパーに期待される役割です。近年、IT需要が大きく拡大し、専門知識やスキルのある人材の不足に悩む企業は少なくありません。
シチズンデベロッパーがいれば、IT部門に頼ることなく、ローコード・ノーコードで業務効率に必要なシステムやアプリが作成できます。
IT部門は業務負担が減り、基幹システムの保守や運用といったより重要度の高い業務に集中できるようになるでしょう。現場も、IT部門に依頼してリリースまで長く待たされることなく、迅速に現場の状況にマッチしたシステムを用意できます。
ローコード開発プラットフォームへの批判とは?
ローコード開発プラットフォームに対しては、「部品を組み合わせるだけで自由度が低く、つまらない」など、一定の批判があるのも事実です。主な批判としては、以下のようなものがあります。
- ローコード開発プラットフォームが自動で処理するため中身が分かりにくい
- カスタマイズに制限があり、細かい業務要件を満たすのが難しい
- 企業やIT部門が把握していないアプリやソフトウェアが乱立する恐れがある
ローコード開発は手軽な反面、構築したアプリやシステムがどのような仕組みで動いているのか分かりづらい側面があります。これが批判されるのは、不具合発生時に原因が特定しにくかったり、修正や拡張がしづらかったりするためです。
とはいえ、最近では自動生成されたコードを直接確認したり編集したりできる仕様が組み込まれるなど、プラットフォームの見えない仕組みを減らす工夫が進んでいます。連携機能や拡張性も向上しつつあるため、今後はカスタマイズの自由度も上がるでしょう。
野良システムが乱立するのを防ぐためには、IT部門などがルールを明確にし、セキュリティの重要性を共有することが大切です。
ローコード開発プラットフォームが提供している主な機能
製品により細部は異なりますが、ローコード開発プラットフォームが提供している基本機能には、主に以下があります。
- ビジュアルモデリング
- API連携・外部サービス接続
- ワークフロー設計
- アプリの運用管理
ここでは、それぞれの機能を紹介します。
ビジュアルモデリング
ビジュアルモデリングは、ローコード開発プラットフォームの軸となる機能です。コードを書く代わりに、用意されているテンプレートをカスタマイズしたり、コンポーネントをドラッグ&ドロップしたりすることでアプリケーションを構築します。
コンポーネントとは、特定の機能を持ったボタンやデータテーブルなどの部品のことです。テンプレートでは、顧客管理や在庫管理といった業務に応じたひな形が用意されています。これらをうまく組み合わせることで、必要な業務アプリがスピーディに完成します。
コードの記載が不要で直感的に操作できるため、高度なプログラミング知識がない従業員でも開発可能です。視覚的に設計できる点も大きな強みで、必要な機能と構築中のアプリにずれが生じたときも気づきやすいです。
API連携・外部サービス接続
API連携や外部サービスとの接続機能も、ローコード開発プラットフォームの重要な機能の一つです。ローコード開発プラットフォームで開発したアプリを、すでに使用しているCRMや会計ソフトといった重要なシステムと連携できます。データのやり取りを自動化でき、業務効率を高められるでしょう。また、外部のコミュニケーションツールやAIサービスなどと接続すれば、より柔軟で拡張性の高いアプリも構築できます。
社内の既存システムと連携することで、これまで蓄積してきた重要な社内資産であるデータを有効に活用できるアプリも作れます。また、外部サービスと連携して機能を実装することで、新しい価値を付加したり利便性を高めたりすることも可能です。
ワークフロー設計
ワークフロー設計は、申請・承認・通知といった一連の業務プロセスを、アプリ上で可視化し自動化する仕組みです。たとえば、「申請者が経費精算を申請」→「上長が承認」→「経理担当者が承認」→「経理担当者が清算処理し通知」といった流れを、システム上でスムーズに実現できます。
このようにワークフローを明確に設計することで、「誰が・いつ・何をすべきか」の可視化が可能です。承認の抜け漏れや処理の遅延といったトラブルを、未然に防ぐのに役立つでしょう。
また、ワークフロー設計機能では、条件分岐や例外処理といった複雑な設定もでき、実際の業務に即した柔軟なフローの構築も可能です。業務の標準化や効率化を促進することにつながります。
アプリの運用管理
ローコード開発プラットフォームには、開発したアプリを安全かつ安定的に運用するために必要な機能もそろっています。たとえば、自動デプロイ、モニタリング、ユーザー認証や権限管理、バックアップやバージョン管理などです。部門ごとに閲覧や編集権限を細かく設定するといったことも可能です。
運用管理機能があることで、アプリを開発したシチズンデベロッパーやIT部門のエンジニアが、時間を取って管理する必要がありません。シチズンデベロッパーは、アプリが安定して稼働しているかどうかを心配することなく、アプリの開発に集中できます。
管理に人手を割かずに済むため、アプリを安定して稼働できるだけでなく、運用にかかるコストを削減することにもつながります。
ローコード開発とその他の開発の違い
アプリケーションを開発する方法は、ローコード開発以外にもノーコード開発やフルコード開発(従来の開発)などがあります。
ローコード開発の特性を理解するためにも、ほかの開発方法との違いを知っておきましょう。
ノーコード開発との違い
ローコード開発と対比されることが多いのが、ノーコード開発です。ノーコード開発では、コードを一切書かず、視覚的な操作のみで開発します。コードを記述しないため、プログラミングの知識がない人材でも手軽にアプリやシステムを設計できる点が大きなメリットです。
ただし、コーディングができないためカスタマイズ性や拡張性には乏しく、現場の状況に合わせた特有の処理をさせたい場合には向いていません。ほかのシステムや外部サービスとの連携や接続の自由度もあまり高くないでしょう。
ノーコード開発に対して、ローコード開発ではコーディングによって固有の処理をさせることが可能で、ある程度柔軟に開発できます。ただし、ノーコード開発よりも一定の知識が必要です。
従来の開発との違い
従来の開発(フルコード開発)では、仕様書に基づいて一からコードを記述し、システムやアプリを構築します。ゼロからコーディングするため開発の自由度が高く、任意の機能が実装でき、複雑な設計も可能です。とはいえ、工数がかかるため、リリースするまでに長い時間がかかることは避けられません。また、高度なプログラミングの知識を持つエンジニアが必要です。
ローコード開発は、コードを書く部分が少なく短時間で開発できる点で異なります。また、フルコード開発よりも実装できる仕様に制限があります。
超高速開発との違い
超高速開発は、コーディングやテスト工程の一部を自動化するなどの処理により工数を削減してスピーディに開発するアプローチのことです。
ローコード開発も結果的に超高速開発ができるため、現在ではほぼ同じものとして扱われていますが、もともとは別物でした。ここでは、両者の違いを中心に解説します。
とらえ方の違い
「超高速開発」の言葉は、2010年代から使われ始めました。当時は、超高速開発ツールを用いてテンプレートの活用や工程の自動化、プロセスの省略といったスピード化の工夫を図り、開発全体を高速化することを意味していました。できるだけ少ない手間や設定で、アプリやシステムの構築を目指すスタイルです。
プロジェクト全体の時間短縮やコスト削減に焦点をあてており、コーディングに限らず幅広い開発プロセスを対象としています。「超高速開発」とは、開発スタイルそのものや高速化した結果を重視した用語といえるでしょう。
ローコード開発は、ツールやプラットフォーム上に用意されたテンプレートやコンポーネントなどを利用することで、最小限のコーディングでアプリを開発する手法です。プラットフォームを使えば、開発だけでなく公開や運用、保守までプラットフォーム上で開発者や業務担当者が担うこともできます。つまり、ローコード開発の大きな目的は、コーディングの範囲を減らして開発効率を上げることです。
超高速開発が「どれだけ早く開発できるか」という目的や成果に焦点をあてているのに対し、ローコード開発は具体的な開発手法である点で異なります。
対象ユーザーと活用シーンの違い
超高速開発とローコード開発では、対象となるユーザー層や開発するシステムの種類にも違いがあります。
超高速開発ツールが普及し始めた際は、利用の主体はITエンジニアやプログラマーでした。当時の超高速開発ツールは、社内の基幹システムや複雑な情報システムを、手間やコストを減らしつついかに早く確実に作り上げるかという需要にこたえるものだったためです。超高速開発ツールの利用は、高度な知識やスキルを前提としていました。
ローコード開発プラットフォームは、高度な知識がない非エンジニアでも活用できるように設計されています。そのため、特定の業務を効率化するアプリや部署内で使用する情報共有システムなど、現場主体のシンプルなアプリやシステムを構築するケースが多いでしょう。
つまり、本来、超高速開発はプロが最速で結果を出す開発スタイルであり、ローコード開発は誰でも開発できる環境・手法を指すものでした。ただし、繰り返しになりますが、近年はローコード開発と超高速開発を同じものとして扱うケースも多く、どちらも広い層が利用する開発手法として認識されています。
ツールの性質と導入目的の違い
ローコード開発プラットフォームは、開発から運用や保守まで行う総合的な環境として、クラウドで提供されることが一般的です。サーバーの構築やインストールなどの手間がかからないため、シチズンデベロッパーでもスムーズに開発に取りかかれ、運用や保守まで一連のサイクルを管理できます。ローコード開発プラットフォームは、IT人材の不足をカバーし、開発効率を向上させるものといえます。
一方、超高速開発は、開発環境そのものではなく、開発プロセス全体の進め方や成果を出すスピードに着目した概念です。従来の超高速開発ツールは基幹システムや複雑な情報システムをターゲットとしており、オンプレミスによる提供が中心です。
とはいえ、現在ではローコード開発と超高速開発を同じように見なすケースが大半です。今後は、超高速開発ツールも、オンプレミス型からクラウド型へと移行していくでしょう。製品を選ぶ際は、ローコード開発プラットフォームか超高速開発ツールかを気にするのではなく、自社にあった機能やサービスを備えているものを選ぶことが大切です。
ローコードツールの導入手順
ローコード開発ツール・プラットフォームを導入する手順は、基本的にほかの開発ツールと大きく異なることはありません。とはいえ、いくつか注意点もあります。
ここでは、4つのステップに分けて、ローコード開発ツール・プラットフォームの導入の手順を紹介します。
1. 導入する目的を明確化する
まずは、ローコード開発ツール・プラットフォームを導入する目的を明確にします。単に「開発スピードを速める」とするのではなく「現場主導で業務改善できる体制づくり」「シチズンデベロッパーを育成しIT部門の負担を軽減」といった具体的な目的を定めましょう。目的をあいまいにしたまま導入しても利用の必要性やメリットが理解されず、形骸化しかねないためです。
次に、導入の対象となる業務も決めます。最初は、規模が小さい領域からスタートするのがおすすめです。
2. 複数の製品を比較検討し選定する
次に、目的を達成するのに適切なツール・プラットフォームを選定します。ツールやプラットフォームは多様な種類が存在し、業務アプリ作成に特化しているもの、大規模開発に向いているもの、特定の外部サービスと連携しやすいものなど得意とする分野はさまざまです。
そのため、それぞれの特徴を押さえたうえで、複数の製品を比較・検討する必要があります。拡張性やセキュリティ体制、サポート範囲などさまざまな観点からチェックして自社に最適なものを選びましょう。
3. 試験導入を実施する
ローコード開発ツール・プラットフォームが決定したら、試験導入を実施しましょう。パイロットプロジェクトとして、日常的に行われている業務を切り出し、小規模なアプリやシステムを構築します。試験導入は、操作性を確認し運用上の課題点を見つけて改善することが目的です。
また、社内で開発に携わる人材を選び、育成する教育や研修を行うことも必要です。パイロットプロジェクトが順調に進んだら、ローコード開発を全社的に展開します。
4. ルールを整備し全社展開する
全社展開に先だって、パイロットプロジェクトで得た知見も踏まえて開発担当者が遵守すべき運用ルールや開発手順を整備します。ルールや手順を決めておかなければ、各担当者がそれぞれのやり方で開発を進める恐れがあるためです。
手順が統一されていなければ、後任に引き継ぐことになったり、改修やほかのシステムとの連携が必要になったりしたときに、混乱を招きかねません。誰が作っても一定の品質になるよう、最初にルールをきちんと整備しておくことが不可欠です。整備できたら、全社展開を進めましょう。
ローコードツールの選び方
ローコード開発ツール・プラットフォームは、製品によって特徴が異なります。自社に最適なものを選ぶためには、複数の製品をさまざまな観点から比較・検討することが大切です。
ここでは、選定の際に特に押さえておくべきポイントを紹介します。
機能の拡張性・連携性
自社ですでに使用しているシステムやツールと連携できるかどうかは重要なポイントです。たとえば、これまではエクセルで在庫を管理していたが限界があり、新たにシステムを開発するとしましょう。その場合、エクセルと連携できればデータをそのまま取り込むことが可能です。また、コミュニケーションツールと連携できれば、通知や承認などがスムーズにできるようになります。
現時点では特に連携するシステムやサービスがない場合でも、将来は必要になる可能性があります。連携性や拡張性がどの程度あるかは、しっかり確認しておきましょう。
セキュリティ
充分なセキュリティ対策が講じられているかどうかも、かならずチェックしたいポイントです。ローコード開発ツール・プラットフォームはクラウドで提供されることが多いため、データの保存先やアクセス権限の管理が適切でなければ、情報漏洩のリスクが高くなります。
セキュリティ体制をチェックする場合は、以下のポイントを確認しましょう。
- ユーザー認証
- アクセス権限の管理
- 通信の暗号化
- データのバックアップ
- 監査ログの有無
ISOやプライバシーマークなどのセキュリティ認証を取得しているかも大切です。
サポート体制
ローコード開発ツール・プラットフォームを選ぶ際は、サポート体制もチェックしておきましょう。導入当初は、設定方法が分からなかったり思ったように動かなかったりすることはよくあります。そのため、サポート体制について確認しておく必要があります。以下の点をチェックするとよいでしょう。
- 初期設定のみ、運用後もフォローがあるなど、サポート範囲はどこまでか
- 電話やメール、チャットなど複数の問い合わせ方法があるか
- 質問への回答は迅速か
チュートリアル動画やマニュアル、オンラインセミナーといった自発的に学べる環境が整っていると、導入や運用をスムーズに進めやすくなります。
まとめ
ローコード開発とは、ツールやプラットフォームを使い、コードをほとんど書かずにアプリやシステムを構築する開発手法です。開発効率を大幅に向上させられ、エンジニアでなくても業務に必要なアプリが設計できるため、多くの企業から注目を集めています。
ローコード開発プラットフォームを導入する場合は、まずは目的を明確にし、複数の製品を比較検討して自社に合ったものを選定することが大切です。自社の状況や課題の解決に役立つローコード開発プラットフォームを選んで必要な開発を進め、業務効率や生産性の向上に役立てましょう。