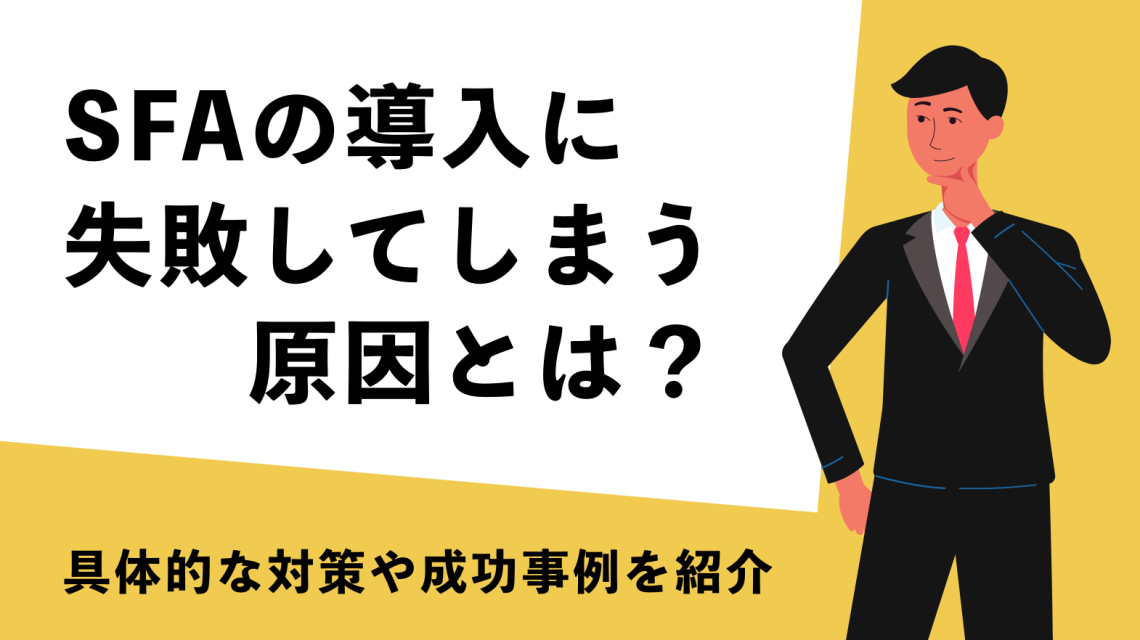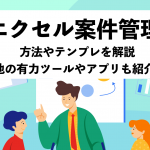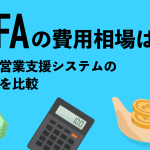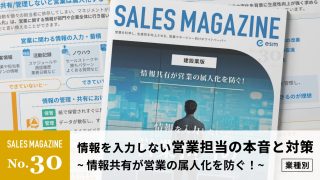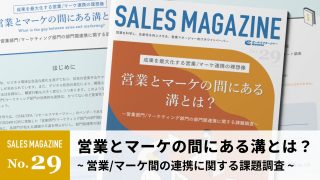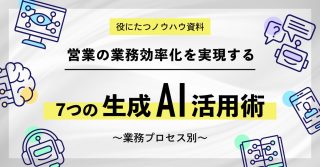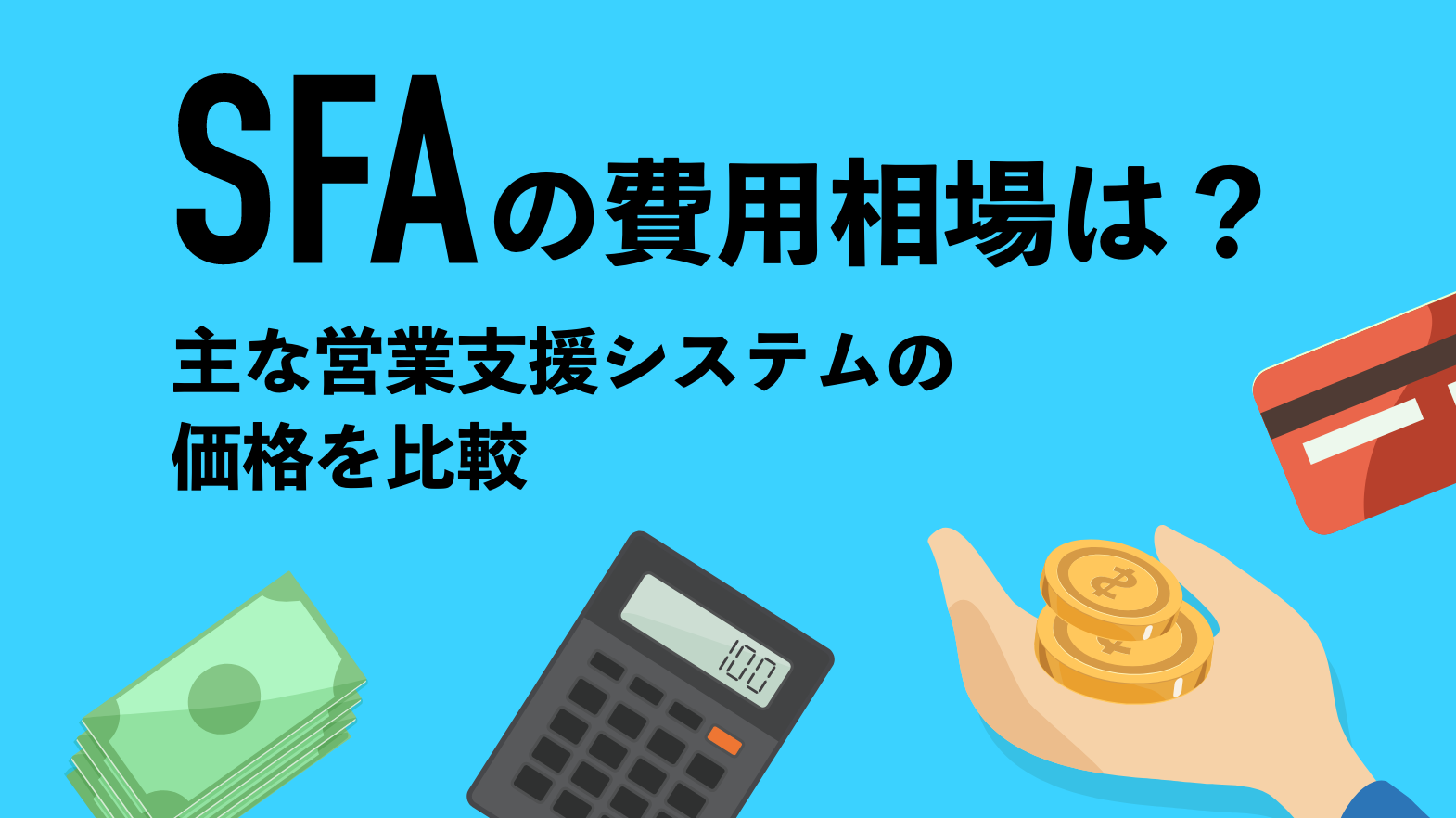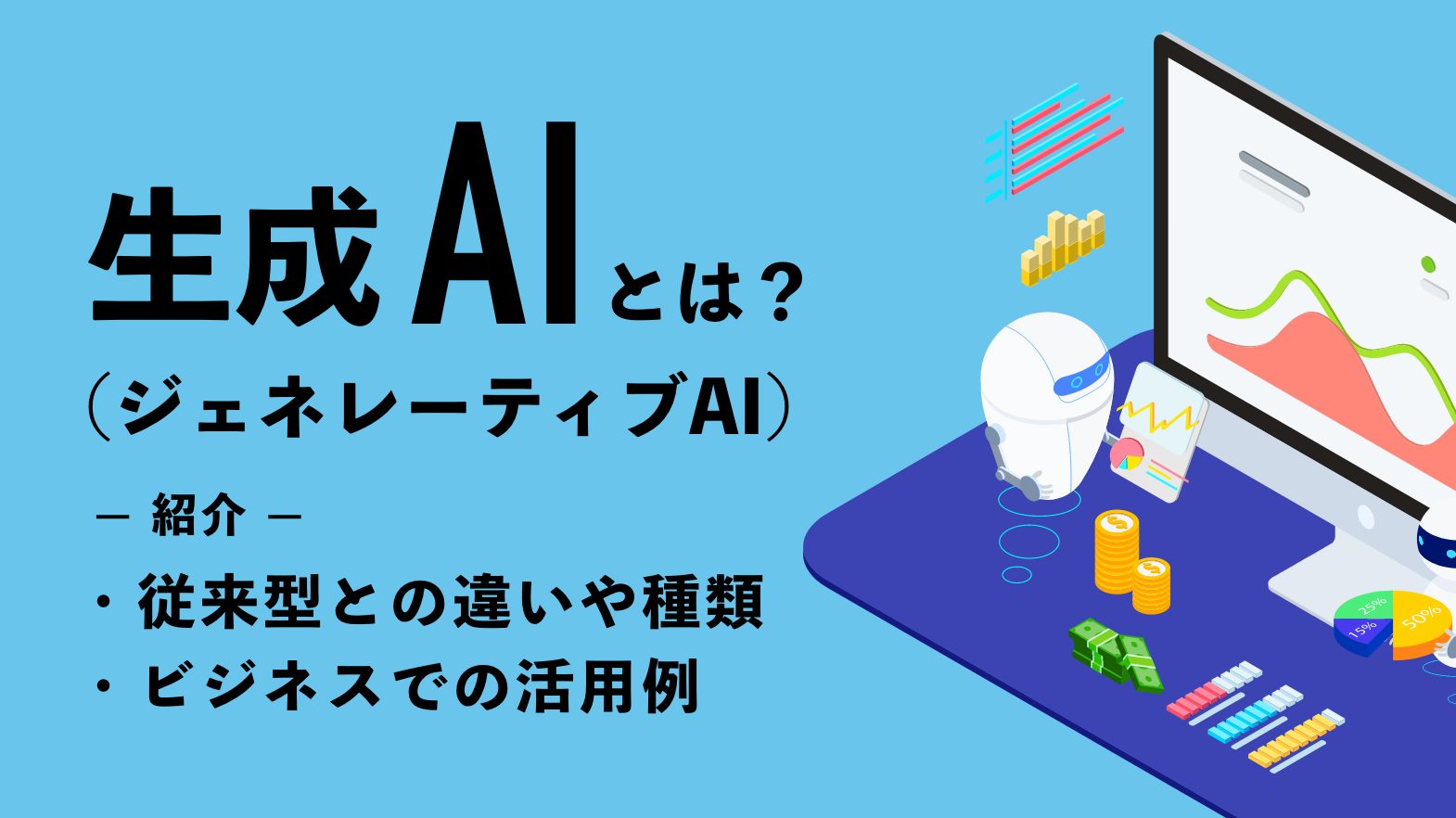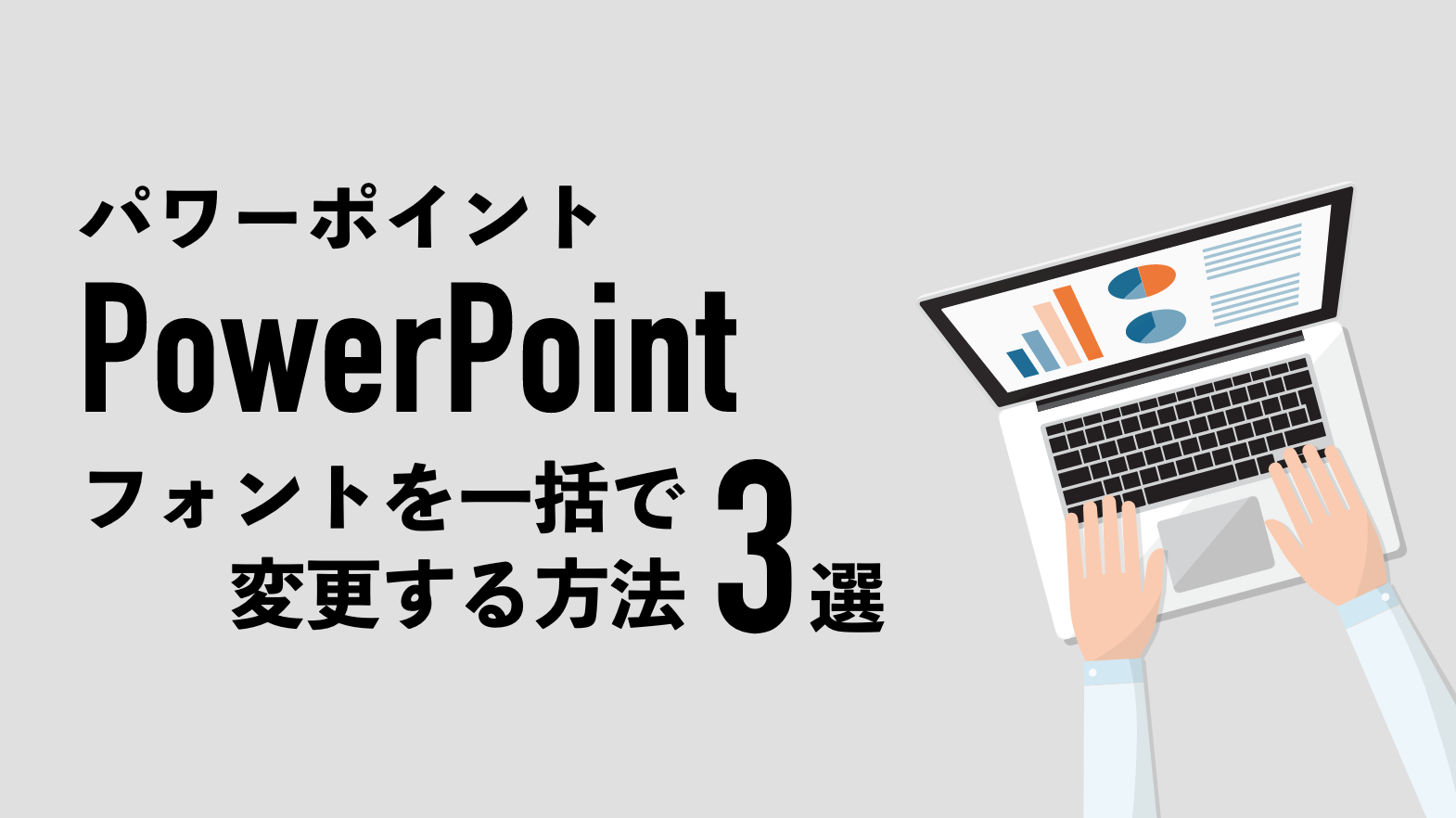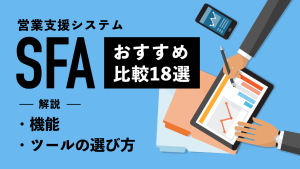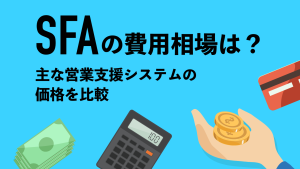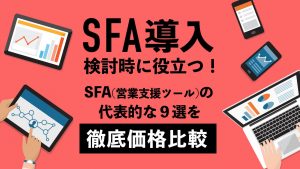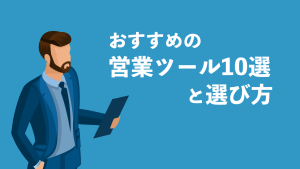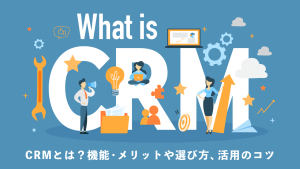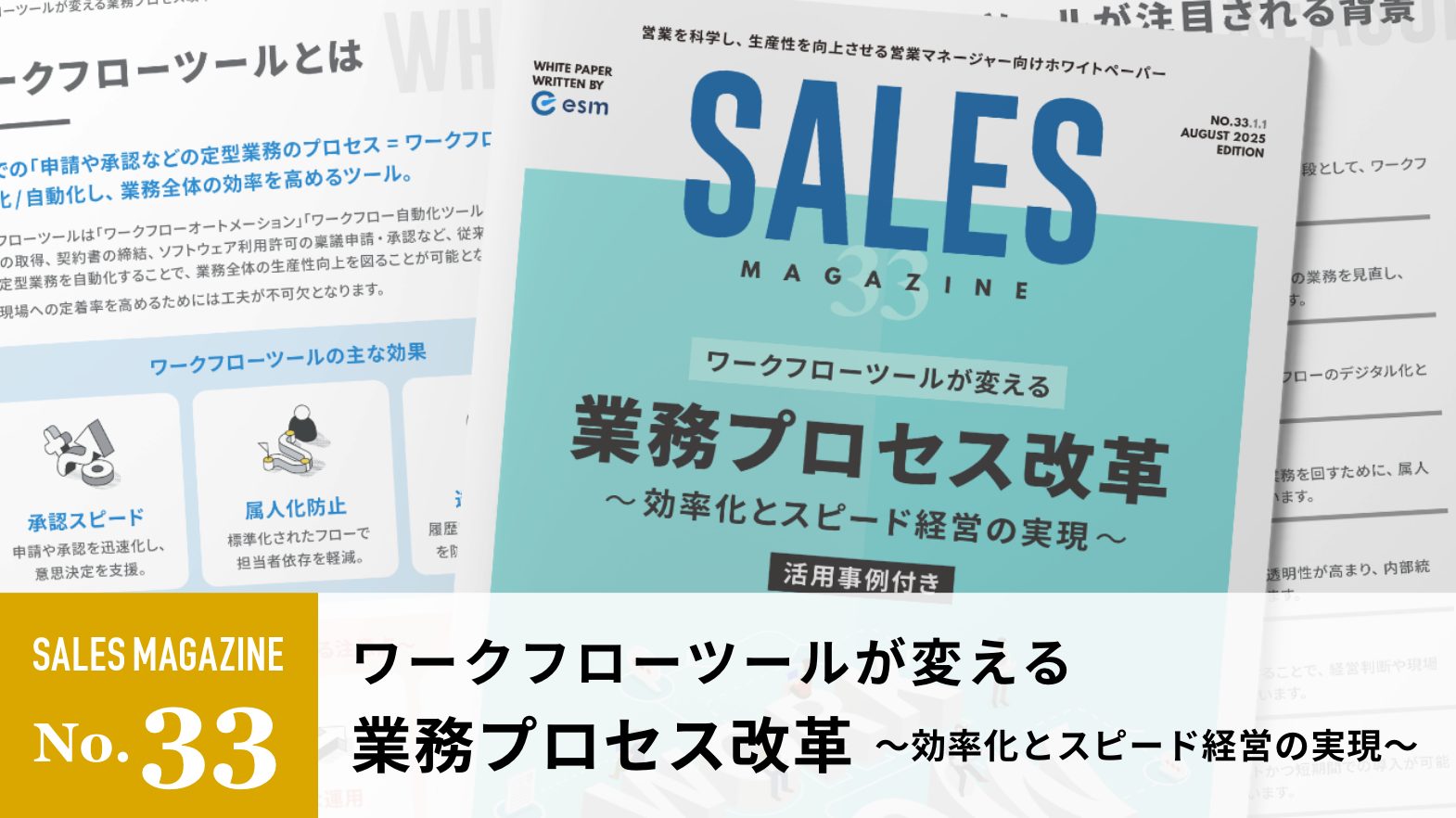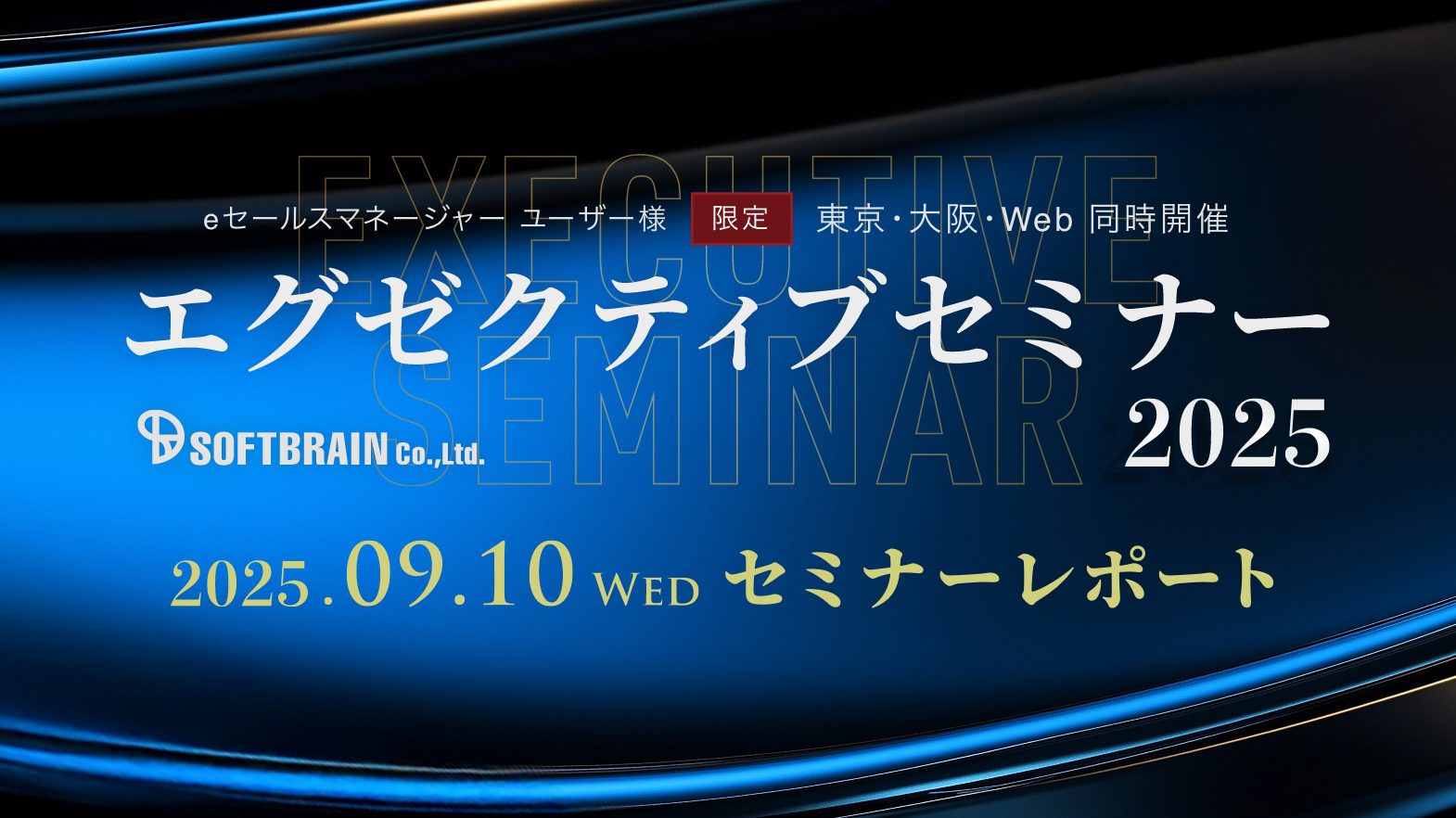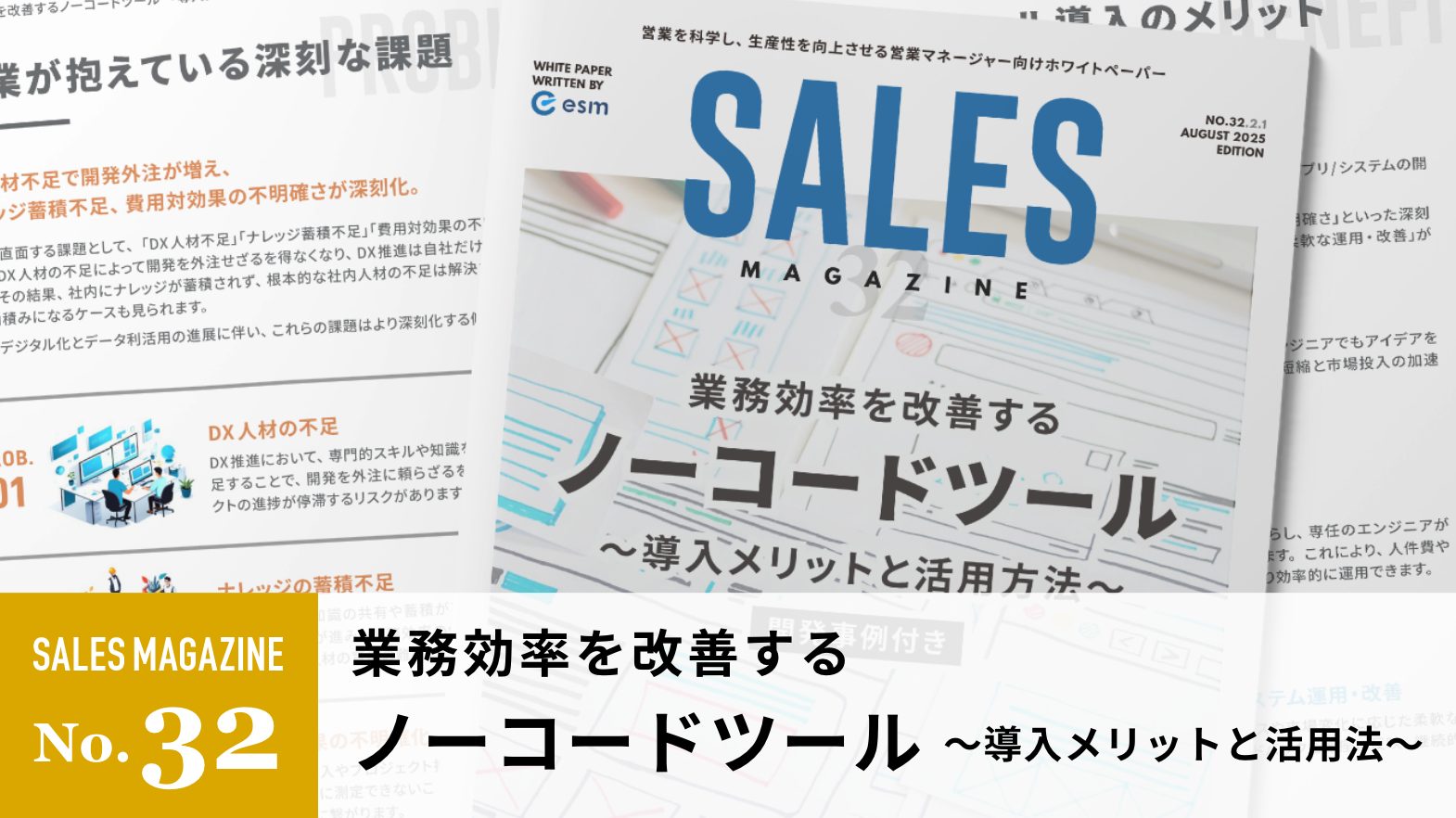SFAの導入に失敗してしまう原因とは?具体的な対策や成功事例を紹介
営業部門の責任者として、SFAの導入を検討されている方も多いのではないでしょうか。SFAは営業プロセスの効率化や情報共有の改善にとても効果的ですが、その一方で導入に失敗するケースも珍しくありません。
「SFAを導入したのに、現場が使いこなせない」
「期待した効果が出ない」
このような悩みを抱える企業は、珍しくありません。本記事では、SFA導入の失敗原因を深掘りし、具体的な対策と成功事例を紹介します。ぜひ参考にしてみてください。
このページのコンテンツ
SFAを導入しても失敗に終わる原因
SFAは、魅力的なソリューションである一方で、活用に成功している企業よりも失敗している企業のほうが多いとされています。
世界的に有名なリサーチ&アドバイザリ企業である英・ガートナー社は、「SFAを導入した企業の約80%が失敗している」という調査データを公表しています。つまり、ほかのITツールと同じように導入しようとすると、失敗する確率が高いといえるでしょう。
ここでは、SFA導入に失敗する原因を3つ紹介します。なお、SFAの失敗要因やベンダー選定に進め方についてより詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてみてください。
参考:SFA(営業支援システム・ツール)導入やベンダー選定を成功させる為に 〜導入が失敗する要因とその解決策〜
目的が不明確なまま導入している
SFAを導入する際に避けるべきなのは、明確な目的を持たずに進めてしまうことです。「とりあえず導入すれば何かが変わる」という漠然とした期待は、高額な投資を無駄にしかねません。
成功への第一歩は、自社のニーズを十分に把握することから始まります。営業プロセスの可視化や顧客データの一元管理など、SFAを導入する目的を設定しましょう。
また、経営層と現場の両方の視点から、SFA導入によって得られる具体的なメリットを洗い出すことが重要です。目的を明確にすれば、導入後の効果測定も容易になり、継続的な改善につながるでしょう。
操作が複雑で使いづらい
現場で使う営業メンバーがSFAに使いづらさを感じてしまう場合、期待した効果を得られません。とくにITリテラシーの低い営業担当者にとっては、複雑な操作は大きな障壁となるでしょう。
操作方法の習得に時間がかかると、本来の営業活動に支障をきたしかねません。また、操作性の悪さが原因でシステムの利用頻度が下がると、データ蓄積の不足につながり、分析や活用が難しくなります。
このような問題を避けるには、使いやすさと必要な機能のバランスを考慮した製品を選択することが大切です。導入前のトライアルで操作性を試したり、ユーザーインターフェースの評価を重視したりして慎重に製品を選定しましょう。
運用ルールが確立されていない
SFAを導入しても、その使用方法や情報入力のルールが明確でなければ、期待した効果は得られません。たとえば、顧客情報の入力形式が統一されていないと、重複データや不正確なデータが蓄積してしまいます。
また、どのような情報をいつ入力するべきかが不明確だと、担当者によって入力内容にばらつきが生じます。
このような問題を防ぐには、明確な運用マニュアルの整備が不可欠です。入力ルールの標準化や、定期的なデータクリーニングなど、一貫した運用体制を確立しましょう。
SFA導入を成功させるには、システムを入れるだけでなく、効果的に活用する体制づくりに取り組む必要があります。
SFAを導入する際に失敗しないためのポイント

SFAの導入は営業プロセスの効率化や顧客管理の向上に大きな可能性を秘めています。しかし、多くの企業がその導入に苦戦しているのが現状です。ここでは、SFA導入の主な失敗原因とその対策について見ていきましょう。
使いやすいシステムを選ぶ
SFAの導入を成功させるには、ユーザーが使いやすいシステムを選ぶ必要があります。直感的な操作性と簡潔なインターフェースを備えたSFAは、営業担当者の負担を軽減します。
選定時は以下の点に注意しましょう。
- 実際に使用する営業チームの意見を積極的に取り入れる
- 無料トライアル期間を活用し、操作性を十分に確認する
- モバイル対応や他システムとの連携性など、実務に即した機能の有無を確認する
- 直感的な操作が可能で、学習コストの低いシステムを優先的に選ぶ
使いやすさを重視すれば、導入後の活用率が高まり、期待する効果を得やすくなります。SFAの選び方や具体的なサービスについて知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
参考:SFA(営業支援ツール)おすすめ比較12選!機能や違い・選定ポイントを解説
現場の理解と協力を得る
SFA導入の成否は、実際に使用する営業部門の理解と協力にかかっています。トップダウンの一方的な決定ではなく、現場を巻き込んだ導入プロセスが重要です。
具体的には以下のアプローチが効果的です。
- 導入の目的や期待される効果を丁寧に説明し、共通認識を形成する
- 営業担当者の懸念点や要望を積極的にヒアリングし、対応策を検討する
- システム選定や運用ルールの策定に現場の意見を反映させる
現場の協力を得ることで、組織全体でSFAを有効活用する雰囲気を醸成できます。
必要最小限の機能から始める
SFA導入の初期段階では、機能を絞り込んでスタートすることが賢明です。全機能を一度に導入すると、ユーザーの混乱を招き、定着が困難になるおそれがあります。
段階的にSFAを導入する流れは、以下のとおりです。
- 基本的な顧客管理や商談管理など、最重要機能に絞ってスタートする
- ユーザーが新システムに慣れるための十分な時間を確保する
- 定期的に利用状況を評価し、必要に応じて機能を追加していく
段階的にアプローチすれば、ユーザーの負担を軽減しつつ、長期的な成功につながる基盤を築けます。なお、SFAの機能と導入費用には密接な関係があります。SFAの導入費用については、以下の記事を参考にしてみてください。
参考:SFAの費用相場はどのくらい? 主な営業支援システムの価格を比較
入力ルールを明確にする
SFAを効果的に活用するには、一貫性のあるデータ入力が不可欠です。まず、データ入力の基準や運用ルールを明確に定義し、組織全体で統一された使用方法を確立しましょう。
このとき、入力項目を必要最小限に絞り込むことで、ユーザーの過度な負担を避けられます。入力フォーマットや選択肢の標準化も、データの一貫性を確保するうえで重要です。
たとえば、顧客名や住所の入力形式を統一しておけば、データの分析や活用をスムーズに進められるでしょう。
入力ルールを決める際は、システムを操作するときに過度な負担がかからないように、実際にSFAを使う営業担当者の意見も積極的に取り入れることが大切です。
教育・サポート体制を整える
SFAを円滑に導入し、定着させるには、充実した教育とサポート体制が欠かせません。利用者向けの詳細な研修プログラムを実施し、システムの基本操作から高度な活用法まで、段階的に学べる環境やコンテンツを整備できると理想的です。
この際、単なる操作説明にとどまらず、SFA活用が営業活動にもたらす具体的なメリットを伝えることで、ユーザーのモチベーション向上にもつながります。
また、いつでも参照できる操作マニュアルの作成や、社内ヘルプデスクの設置も有効です。とくに、導入初期はユーザーからの質問が数多く寄せられる可能性があるため、迅速な対応ができる体制を整えておくとよいでしょう。
ベンダーが提供するサポートサービスも、積極的に活用しましょう。専門家のアドバイスを参考にすれば、より高度な活用方法や最新の機能について学べるだけでなく、SFAの価値を最大限に引き出せます。
SFAを導入してすぐに取り組むべきこと【失敗を防ぐ】

SFAの活用を浸透させるためには、導入直後の取り組みが重要です。ここでは、SFAを導入してすぐに取り組むべきことを紹介します。
運用ルールを明確化する
SFA成功の鍵は、明確な運用ルールの確立にあります。
まず、データ入力基準を決めて、顧客情報や商談情報をいつ・どのように入力するかを明確にしましょう。次に、日報作成や顧客情報更新など、具体的な利用シーンごとの操作方法を決定します。操作方法をマニュアルなどに明記しておけば、誤記や誤操作が起こる確率を下げられるでしょう。
また、セキュリティと利便性のバランスを取るために、情報へのアクセス権限のレベルを役職ごとに設定することも大切です。
重要なのは、SFAの運用ルールを一度決めて終わりにしないことです。定期的に効果を検証し、現場の声を取り入れながらルールを改善しましょう。明確で実践的な運用ルールは、SFAを効果的に活用し、定着を促進するために欠かせない取り組みです。
入力項目を少なくする
SFA導入初期の大きな課題となるのは、過剰な入力項目によって現場の負担が増えることです。そのため、作業量を減らすために、入力項目を必要最小限に抑えましょう。
まず、本当に必要な情報のみを必須項目とし、それ以外は任意入力とします。入力項目に優先順位をつけ、ユーザーが効率的に情報を入力できるよう配慮することも大切です。さらに、他システムとの連携やAI機能を活用して手動入力を減らす工夫も、作業量を削減する効果があるでしょう。
このような施策により、ユーザーの負担を軽減しつつ、質の高いデータ蓄積を実現できます。
利用状況をモニタリングする
SFAの効果を最大化するには、ユーザーの利用状況を継続的に監視することが不可欠です。ログイン頻度や利用時間、データ入力の量、機能ごとの使用状況などを定期的に確認しましょう。
同時に、ユーザーからのフィードバックを積極的に収集します。このモニタリングにより、SFAの活用度や問題点を早い段階で把握し、改善につなげられます。
定期的なモニタリングによって利用が低調なユーザーや部門を特定し、追加のトレーニングや支援を提供すれば、SFAを活用する意識を向上させられるでしょう。
KPIを設定し効果を測定する
SFA導入の効果を客観的に評価するため、適切なKPI(重要業績評価指標)を設定し、定期的に測定することが重要です。
まず、SFA導入の目的に沿った、具体的かつ測定可能なKPIを選定します。
SFAの効果や定着率を評価するには、以下のような指標を追跡するとよいでしょう。
| 指標 | 概要 |
| ログイン率 | 営業チームメンバーの日次/週次のSFAログイン率 |
| データ入力率 | 顧客情報、商談情報、活動記録などの入力完了率 |
| レポート/ダッシュボード閲覧率 | マネージャーや営業担当者によるレポート・ダッシュボードの閲覧頻度 |
定期的なデータ収集と分析を行い、結果を可視化しましょう。これにより、SFA導入による具体的な成果を把握できます。
分析結果にもとづいて改善策を立案・実施すれば、SFAの効果を継続的に高められるでしょう。
SFA導入の成功事例
株式会社クレディセゾンはBtoB事業強化のため、弊社ソフトブレーンのSFAである「eセールスマネージャー」を導入しました。eセールスマネージャーの導入を成功させるために、いくつかの工夫を施しています。
まず、マネージャーが部下の活動を可視化できる帳票を作成し、既存の管理をすべてSFAに集約しました。加えて、営業現場の使い勝手がよくなるように、何度も意見交換を重ねたうえでSFAのカスタマイズにも着手しています。
結果として、マネジメントスタイルが「受動的」から「能動的」に変化し、案件推進のスピードが向上しました。
今後は、業務時間削減や他システムとの連携を進め、SFAを中心とした業務の効率化と高度な情報活用を目ざしています。
SFA導入の失敗を防ぐために自社にあったツールを選ぼう
SFA導入の成功は、自社の営業プロセスを変革し、業績向上につながる大きな機会です。ただし、SFAを導入する際の失敗を防ぐには、明確な目的設定と自社に適したツール選びが不可欠です。
使いやすさやカスタマイズ性・サポート体制など、多角的な視点で選定しましょう。導入後も、明確な運用ルールの策定や継続的な改善努力を怠らないことが重要です。
SFAは単なるツールではなく、営業力強化の戦略的パートナーです。自社の成長戦略に合わせて最適なSFAを選んで活用すれば、競争力の向上と持続的な成長を実現できるでしょう。