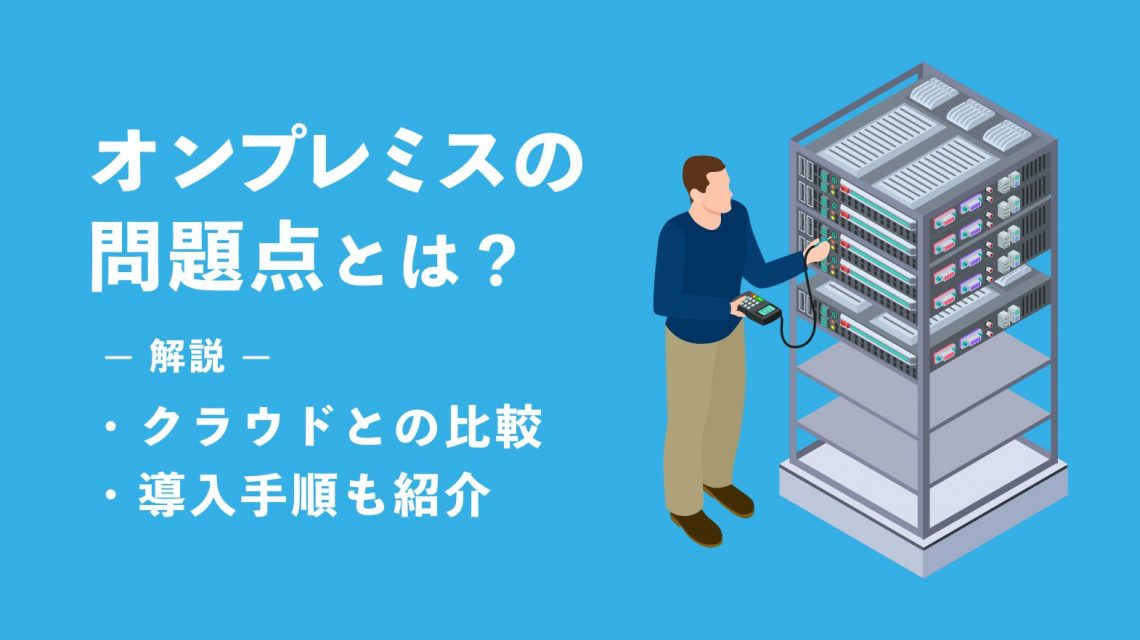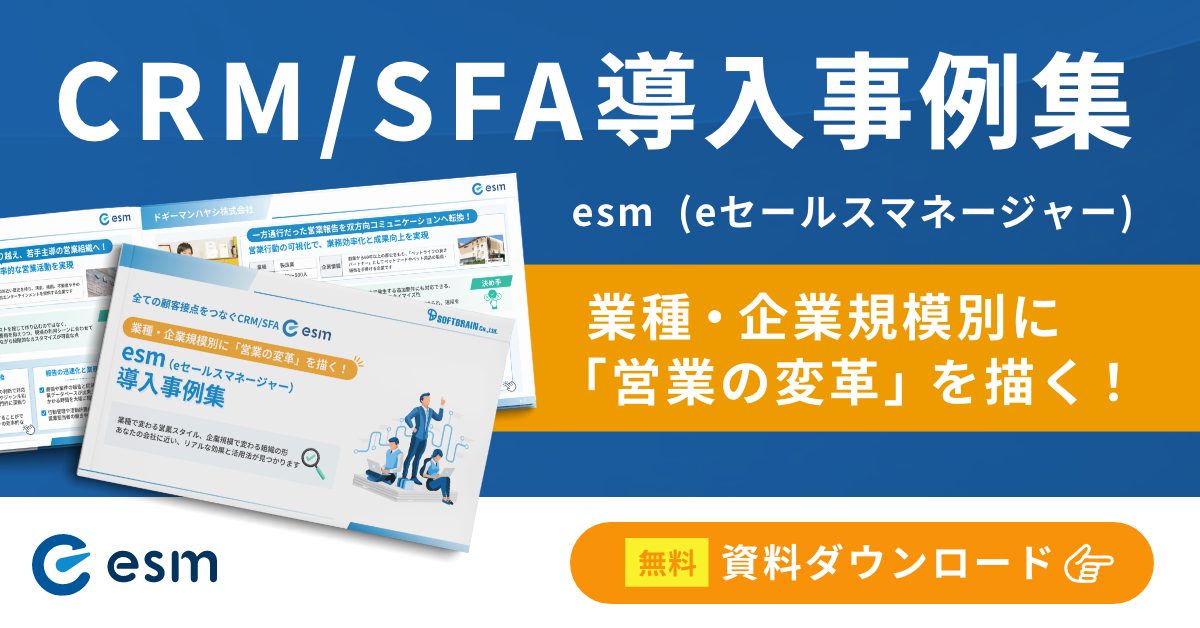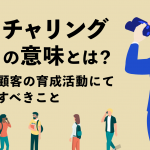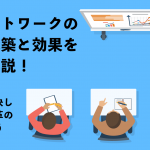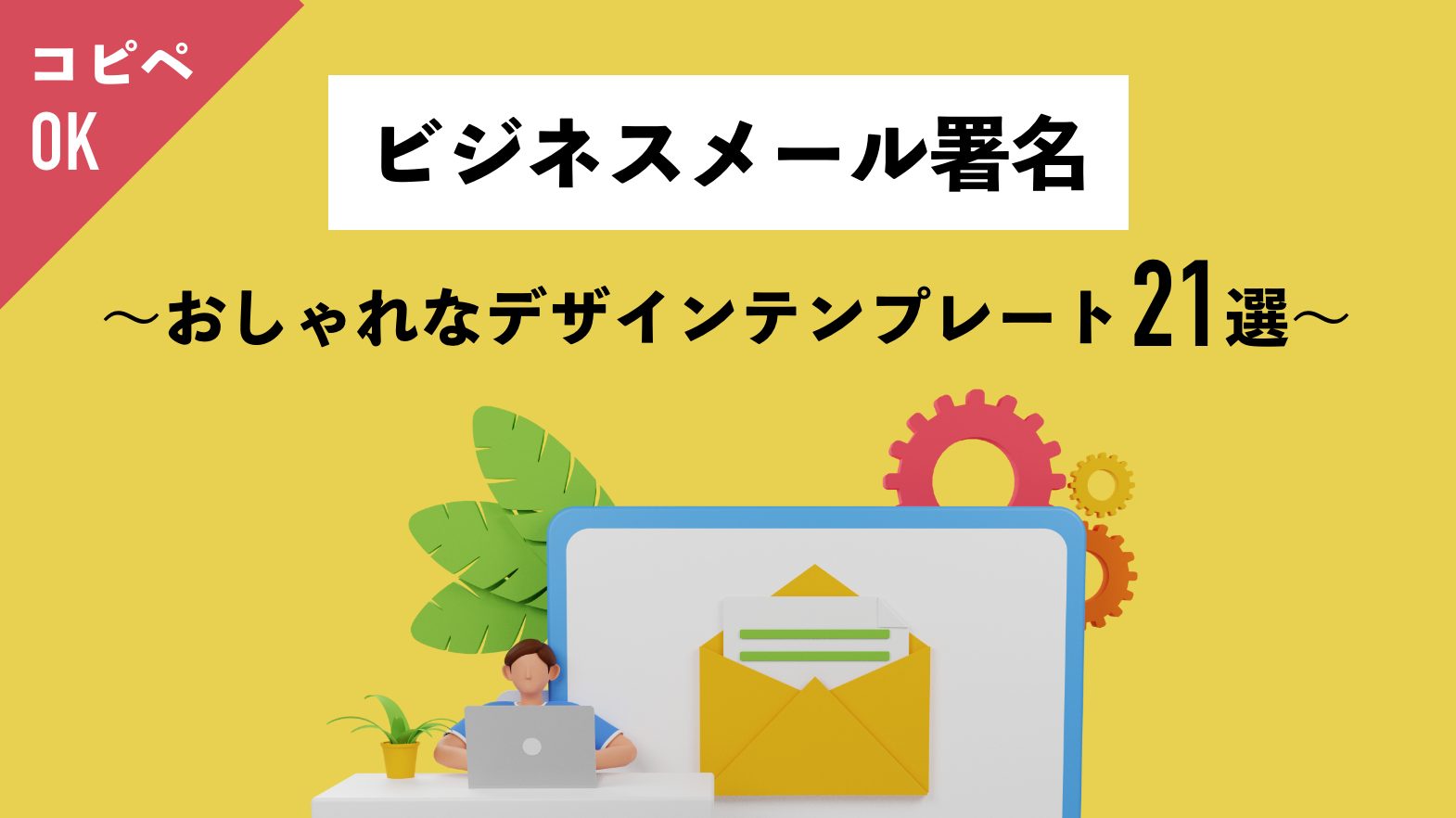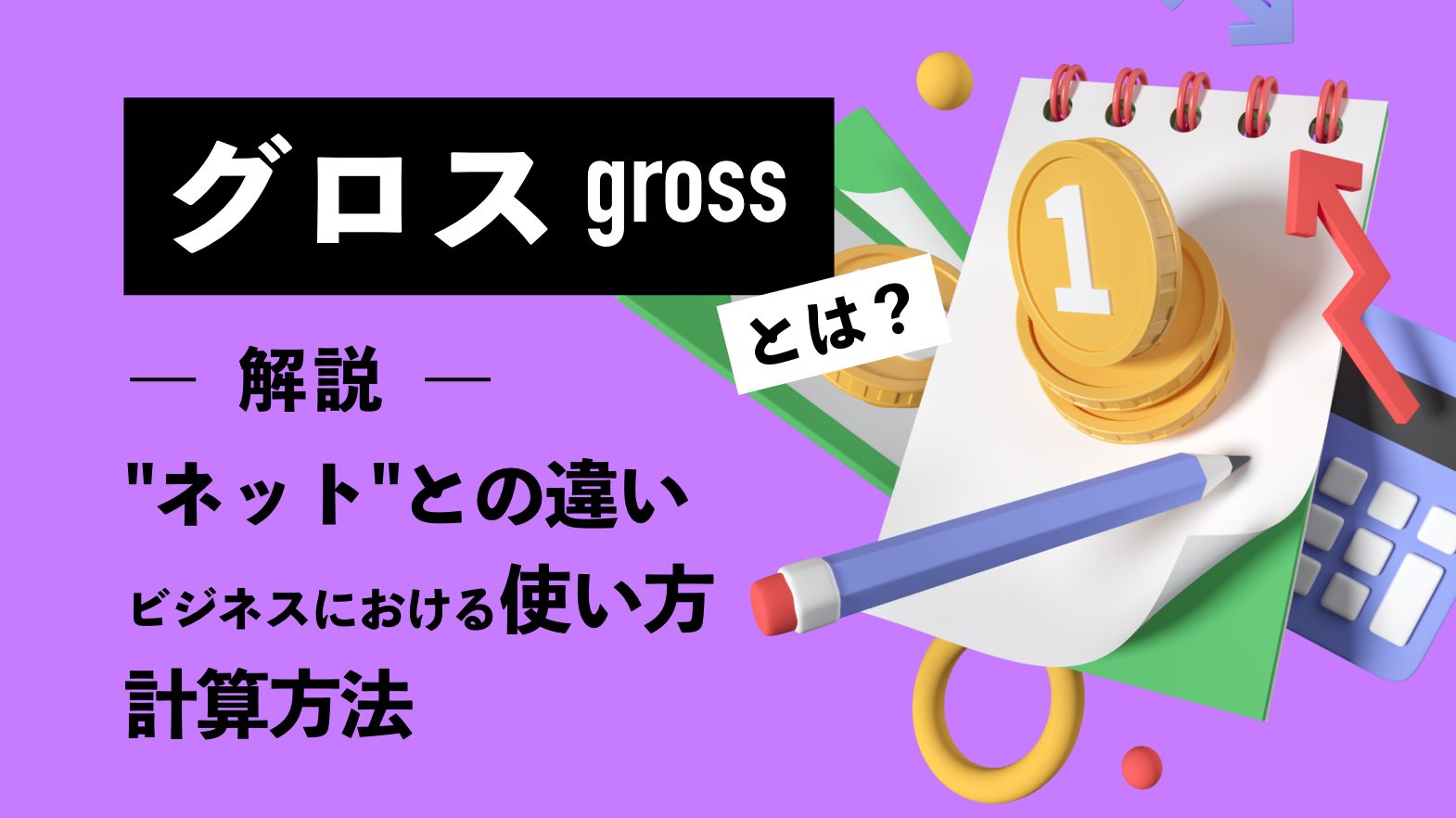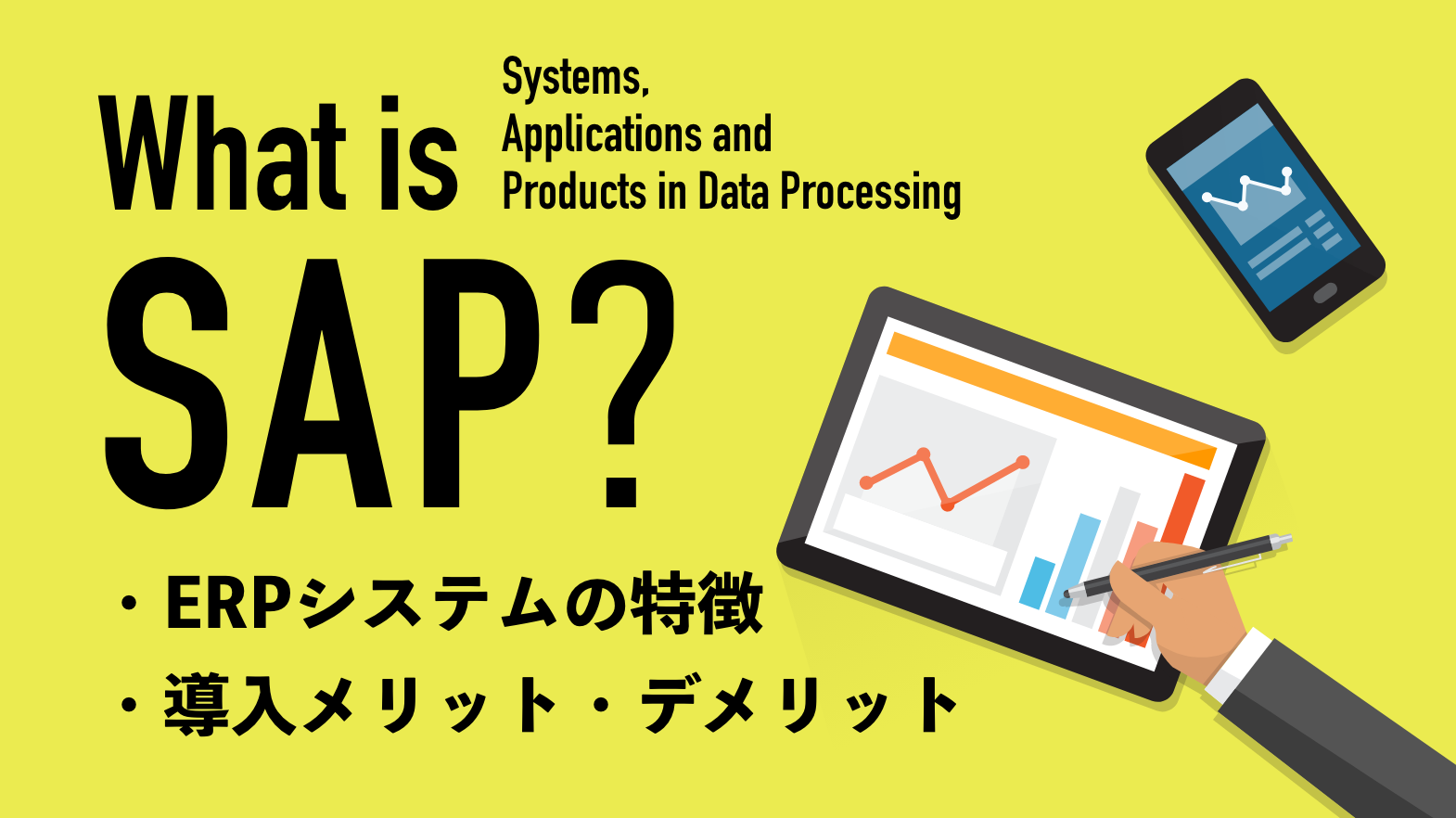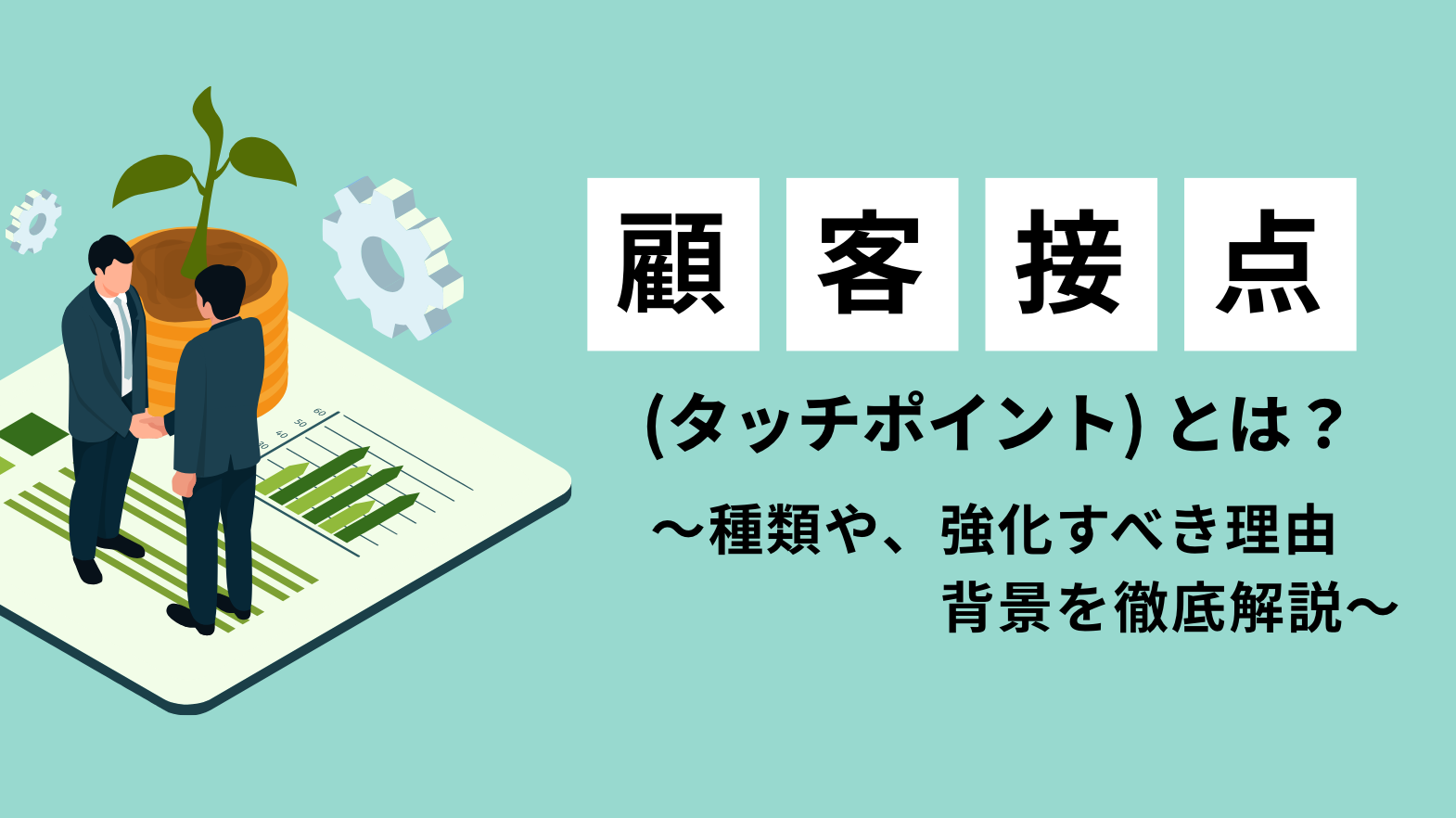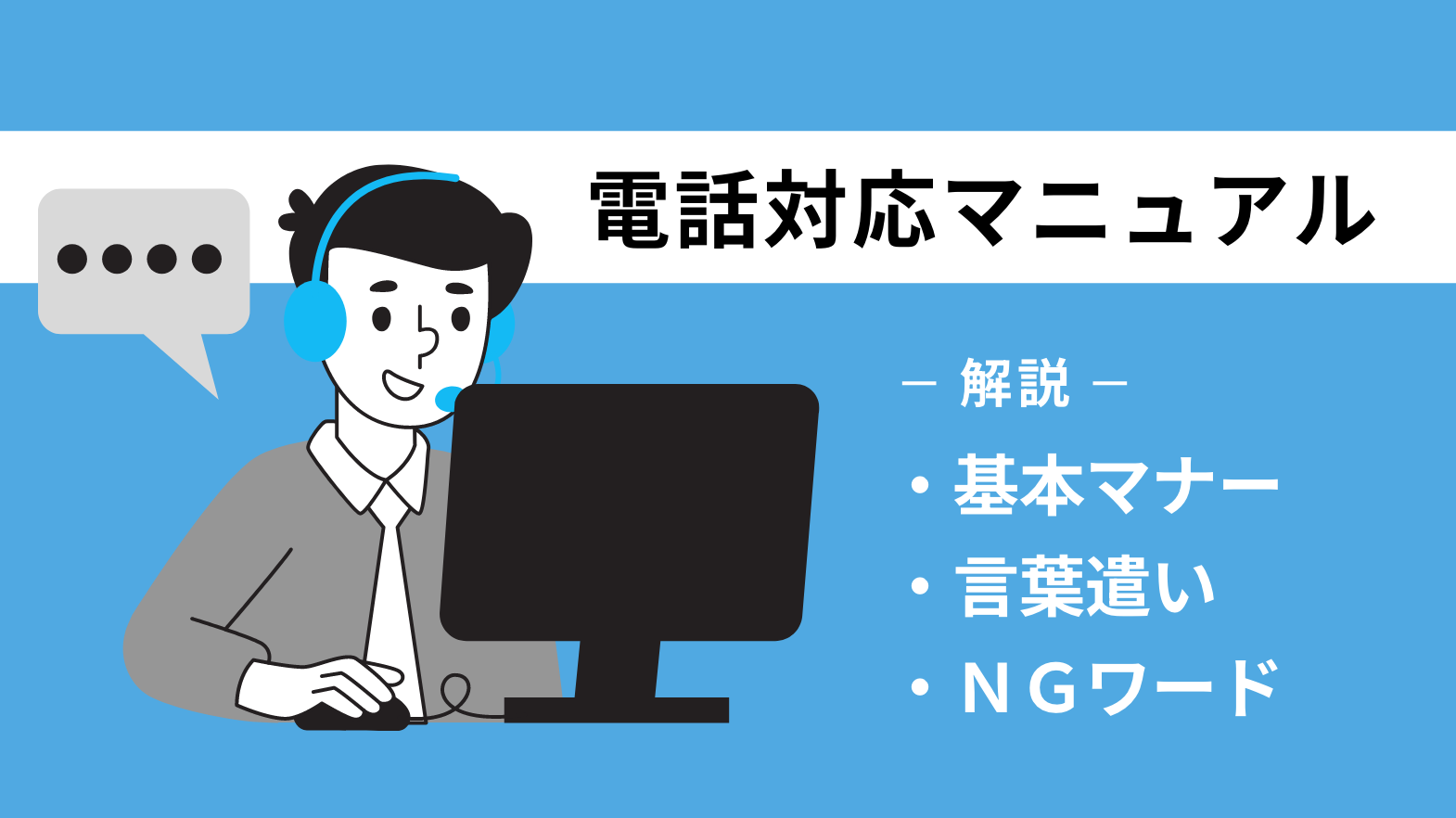オンプレミスの問題点とは? クラウドとの比較や導入手順も紹介
情報システムにかかわるハードウェアと設備を所有し、企業内で運用・管理することをオンプレミスといいます。クラウドコンピューティングが普及する前はオンプレミスの環境で情報システムを構築することが一般的でした。
クラウドサービスへの移行が進むトレンドのなかで、レガシーシステムといったニュアンスでオンプレミスという言葉が使われることがあります。一方で、海外を中心に「オンプレミス回帰」の動向も伝えられており、オンプレミスのメリットが見直されていることも事実です。
この記事では、オンプレミスの意味について正しく理解するとともに、クラウドサービスと比較のなかでのメリット・デメリットについて解説します。
オンプレミスとは

オンプレミスとは、サーバーのハードウェアやネットワーク設備などをすべて所有し、システムを構築して管理するためのリソースをすべて自社でまかなう情報システムの運用形態のことです。
さまざまな情報システムがクラウドサービスとして提供されるようになった現在、クラウドと区別するためにオンプレミスという言葉が使われます。
たとえば、自社のWebサイトを運営する場合に、Webサーバーを購入し自社内に設置して管理・運用を行うのがオンプレミスです。
レンタルサーバーを利用してWebサイトを運営している場合はクラウドを使っているということになります。Webサイトのホスティングのようなサービスに限らず、さまざまな業務システムがクラウドを通じて提供されるようになってきています。
一方で、金融機関の勘定系システムはセキュリティ面での安全基準が定められており、それに沿った情報システムを自社で構築するオンプレミスでの運用がほとんどの割合を占めています。
クラウドとは
クラウドとは、情報システムを構築するためのハードウェアとソフトウェアをサービス提供事業者が保有し、インターネットを通じてユーザーがそれを利用する形態です。
オンプレミスとクラウドの比較を考える場合、クラウドには種類があることを知っておく必要があります。
レンタルサーバーを借りてWebサイトを構築するケースをクラウドの例として上げましたが、サーバーやストレージなどのインフラだけを利用できるクラウドサービスと、GmailやchatGPTのようなソフトウェアの機能だけを利用できるサービスではクラウドの種類が異なります。
オンプレミスとクラウドサービスの種類の比較
| オンプレミス | クラウドサービス | |||
|---|---|---|---|---|
| laaS | Paas | SaaS | ||
| データ | ユーザー | ユーザー | ユーザー | ユーザー |
| ソフトウェア (チャットツール、会計ソフトなど) | ユーザー | ユーザー | ユーザー | 事業者 |
| プラットフォーム ( OS、データベースなど) | ユーザー | ユーザー | 事業者 | 事業者 |
| インフラ (サーバー、ストレージなど) | ユーザー | 事業者 | 事業者 | 事業者 |
情報システムはサーバーやネットワーク機器などのハードウェアで構成されるインフラとOSやデータベースなどのプラットホーム、ユーザーが直接操作を行うアプリケーションソフトウェアで構成されます。
情報システム全体を上の図のように切り分けた場合に、どの部分を提供するかによってクラウドサービスは以下の3つに分けられます。
| 種類 | 詳細 |
|---|---|
| SaaS(Software as a Service) 呼び方:サース、サーズ | ソフトウェアの機能を提供するサービス。個人で利用できるメールやオフィスソフトから、ビジネスで利用するオンラインストレージやグループウェアなど、必要な機能のみを手軽に利用できる |
| PaaS(Platform as a Service) 呼び方:パース | インフラに加えて、OSやミドルウェアといったインフラを使うために必要なソフトウェア環境まで含めて提供するサービス。開発環境が用意されているため、開発工数を削減できる |
| IaaS(Infrastructure as a Service) 呼び方:アイアース、イアース | ハードウェアリソースをネットワークを通じてユーザーに提供するサービス。システムの規模を拡大させる場合でも容易に対応可能 |
参考:SaaSとは?メリットやPaaS・IaaSとの違い、サービスの代表例をわかりやすく解説
オフプレミスとクラウド
プレミス(premises)には、土地、敷地、構内、建物、施設といった意味があり、オンプレミスは情報システムのすべてを、自社が所有する範囲の中に置くということを指しています。
それに対し、オフプレミスは自社の範囲外に、所有する情報システムを置くという意味であり、自社の保有するサーバーを通信会社のデータセンターを間借りして設置する「ハウジング」や「コロケーション」といったサービスを利用するケースが該当します。
一般的にはオフプレミスもクラウドの同義として用いられますが、ハウジングやコロケーションはクラウドとは区別されます。
オンプレミスとクラウドの比較
ERPなどの基幹システムもクラウドサービスで提供されるものが増えており、政府もシステムの導入をする際の第一候補としてクラウドサービスを検討する方針として「クラウド・バイ・デフォルト」を掲げるなど、これまでオンプレミスで構築してきた情報システムをクラウド化する流れが進んでいます。
オンプレミス環境からクラウドへの移行、あるいは、新たに情報システムの導入を検討する際には、さまざまな角度から両者を比較してみることが必要があります。
| オンプレミス | クラウド | |
|---|---|---|
| 初期投資 | ハードウェア・設備、システム構築の費用など高額な初期投資が必要 | インフラ部分の費用がかからない |
| ランニングコスト | 保守・管理のための人員コストが発生 | 定額課金、または、従量課金の利用料が発生 |
| 管理・保守 | 管理・保守のための人員の確保が必要 | サービス提供事業者が行う |
| 自由度・拡張性 | 情報システムに求められる自社の要件を前提として自由に構築することが可能 | 自社の要件に合う事業者の選定が必要 事業者のシステムによる制約が生じる可能性がある |
| セキュリティ・対障害性 | 社内ネットワークのセキュリティは高い 災害等インターネットが遮断した場合でも、重要なデータにアクセス可能 | 事業者のセキュリティ対策に依存 障害が発生した場合、対応・対策は事業者に依存することになる |
一般的には、ハードウェアへの初期投資が不要なクラウドがコスト面で有利な場合が多いと考えられます。しかし、クラウドは情報システムの構築と運用を部分的にアウトソースすることと同じであり、クラウド事業者と同じ水準で情報システムを内製化することが可能であれば、そのほうがコストを抑えることができます。
これまで、クラウドサービスのセキュリティは不安視されることが多かったのですが、クラウド環境でのセキュリティ技術も日々向上していることから、オンプレミスのセキュリティ面での優位性はなくなってきています。
参考:パッケージ型顧客管理システム(CRM)のおすすめを比較! オンプレミス型やクラウドとの比較や製品選定について
クラウドの導入・移行の手順例
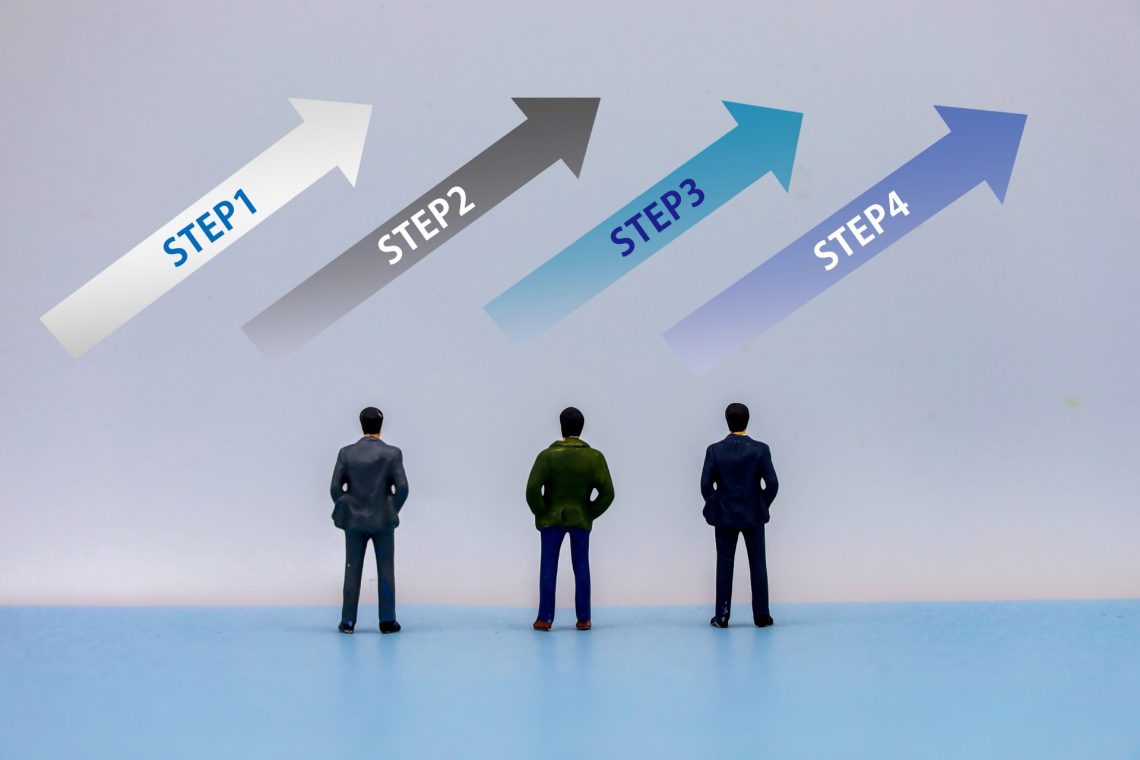
クラウドを導入するにあたり、手順をしっかりとイメージしておくことで作業がスムーズになります。
ここでは、クラウドの導入や移行の手順例で、具体的イメージを固めていきましょう。
1.利用方法を明確にする
クラウドを利用するためには、まず自社の利用方法を明確にする必要があります。
クラウドのファイルサーバーを利用したいだけなのに、ECサイトまで構築できるサーバーを契約すれば、それはオーバースペックです。
「クラウドサービスに何を期待するのか」を明確にし、適したクラウドサービスの選定基準を作りましょう。
2.利用計画(すでにオンプレミスなら移行計画)を立てる
クラウドサービスを導入した際に、どのように利用するかを計画しましょう。
たとえばファイルサーバーならば、どのようなデータをクラウドへアップするのか、社外秘データの扱い方も含めて決めておきましょう。
すでにオンプレミスで運用しているサーバーがある場合は、どのタイミングでどのようにクラウドへ移行するのがスムーズであるかを、計画書として明確にしておくことをおすすめします。
3.予算の概算
利用方法と利用計画が決定したら、利用するクラウドサービスもある程度しぼられてきます。
それぞれの利用料金を比較し、ランニングコストも含めた費用を算出しましょう。
4.利用するクラウドサービスの決定
予算まで決まったら、利用するクラウドサービスを決定します。
できれば「初月無料」などのキャンペーンを行っているクラウドサービスを選定したいところです。
無料期間があれば、少人数で運用テストを行えます。
5.既存データのバックアップ(※オンプレミスからの移行の場合)
すでにオンプレミスで運用しているサーバーがある場合は、確実にデータのバックアップを取っておきましょう。
外付けのハードディスクなどにデータを取っておくことで、クラウドサービス移行時に万が一のトラブルがあっても対処できます。
6.少人数での導入テスト
無料期間のあるクラウドサービスであれば、少人数での導入テストを行いましょう。
一気に全社導入をすると、高確率で混乱を招きます。少人数で運用しながら、導入後にサポートすべき事項やスムーズな運用手順を固めていきましょう。
7.クラウドの導入(オンプレミスからのクラウド移行)
十分なテスト運用ができたら、全社でのクラウド導入を行いましょう。
最初は利用メンバーに対するサポートが多く発生しますが、苦労して導入したクラウドが社内に定着するか否かは、ここでのサポートにかかっています。
オンプレミス回帰の動向について
2000年代に入りクラウドに移行する動きが急速に高まりました。しかし、クラウドの稼働実績が積み上がる中で、デメリットも多く指摘されるようになり、「オンプレミス回帰」や「脱クラウド」といった言葉が聞かれるようになっています。
以下のような点がその理由として挙げられます。
予想外の費用がかかる
SaaSの場合は月極の定額料金であることが多いのに対して、PaaSやIaaSではストレージの使用量やトラフィックの量に応じた従量課金の料金体系が取られます。
使用状況に急激な変動があった場合に想定以上の費用が発生することに加えて、外資系の事業者のサービスを利用する場合はドル建てで決済されるため、為替の変動もコストに影響することになります。
クラウドには運用コストが大きく変動するリスクがあります。
サービス品質の変動
クラウドサービスは、事業者が用意するサーバーやネットワークなどのリソースをユーザーが共有して使う形です。この点がオンプレミスに対するクラウドのコスト面での優位性となりますが、他のユーザーの使用状況によってサービス品質に影響を受ける場合があります。
同じサービスを利用する他のユーザーへの急激なアクセス集中により、サービスのパフォーマンスが低下するといったことが考えられます。
セキュリティの確保
クラウドサービスの事業者は、セキュリティ認証の取得状況などの対策への取り組みを公表していますが、機密性の高い情報を扱う場合に求められるセキュリティ要件を、事業者の対策では満たすことができないケースもあります。
また、重要度の高いデータをクラウド上に置いた場合に、パブリックネットワークの障害でアクセスできない状況が想定されるほか、災害等でデータが消失するといったリスクも負うことになります。
オンプレミスとクラウドそれぞれの特性を考慮したシステム構築を
オンプレミス環境で情報システムを構築・運用する利用形態があらためて見直されてきていることなども踏まえ、さまざまなサービスが提供されているクラウドと合わせて、TCO(総保有コスト)を把握することが重要です。
eセールスマネージャーRemixではオンプレミス版とクラウド版の両方を用意しています。自社の利用目的に合った適切な導入を検討しましょう。