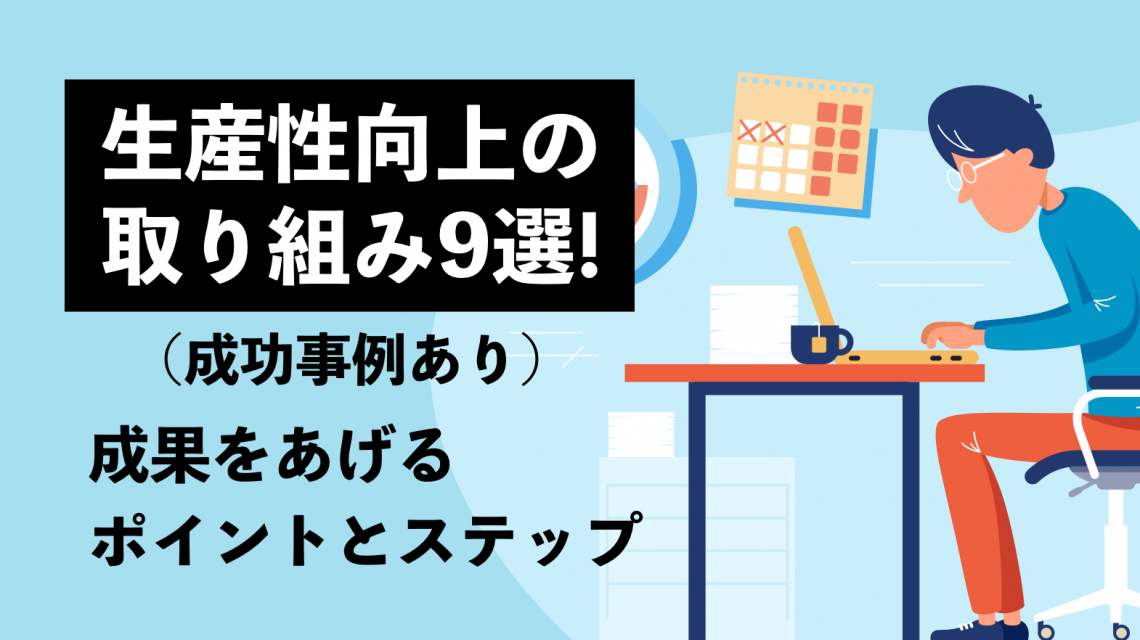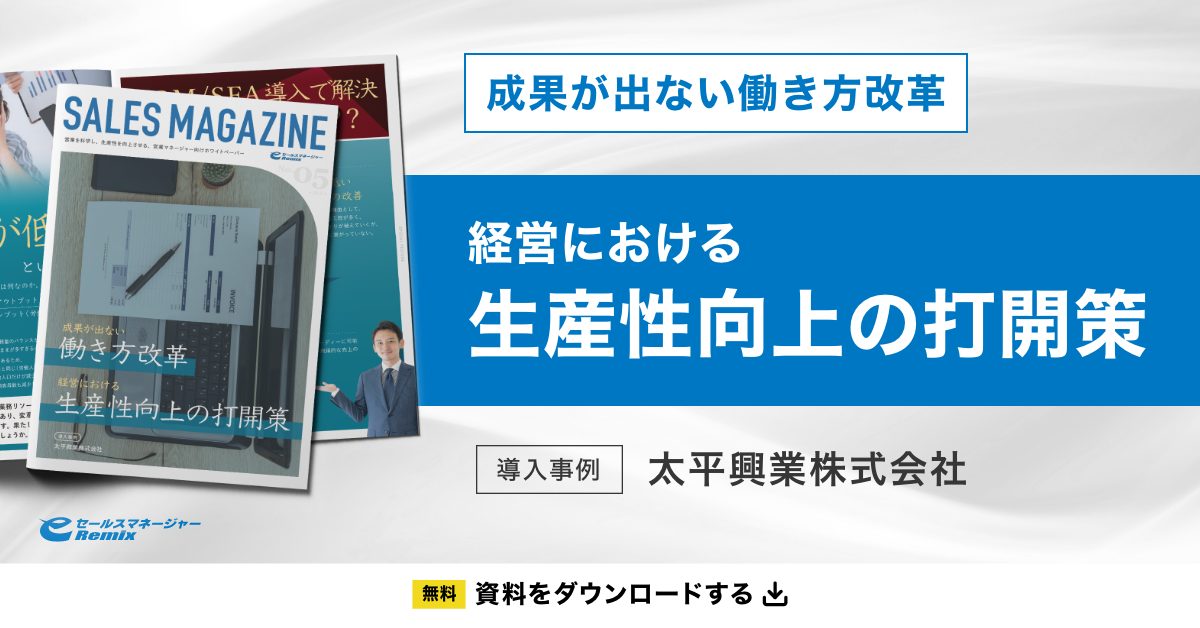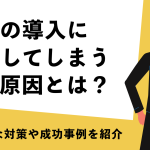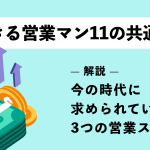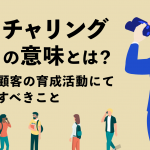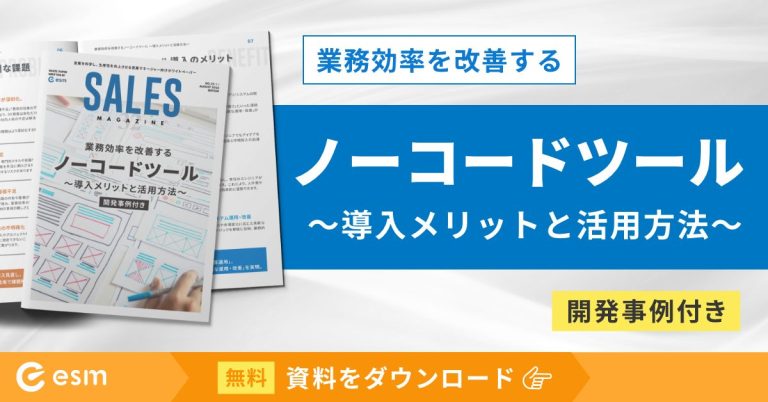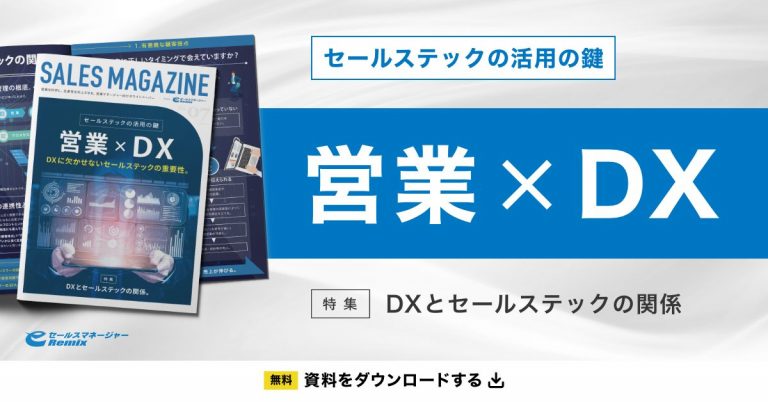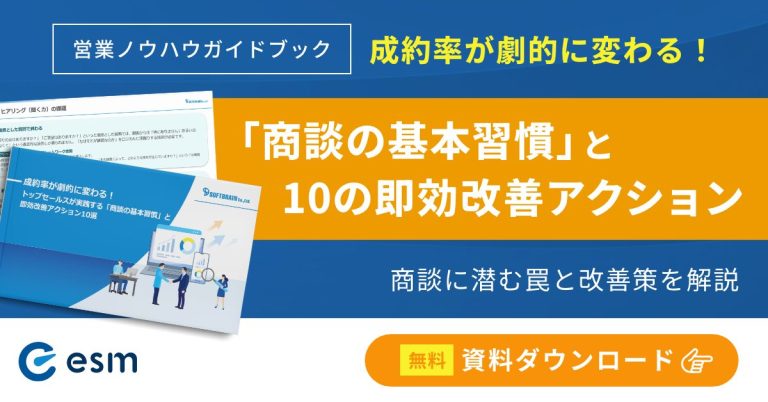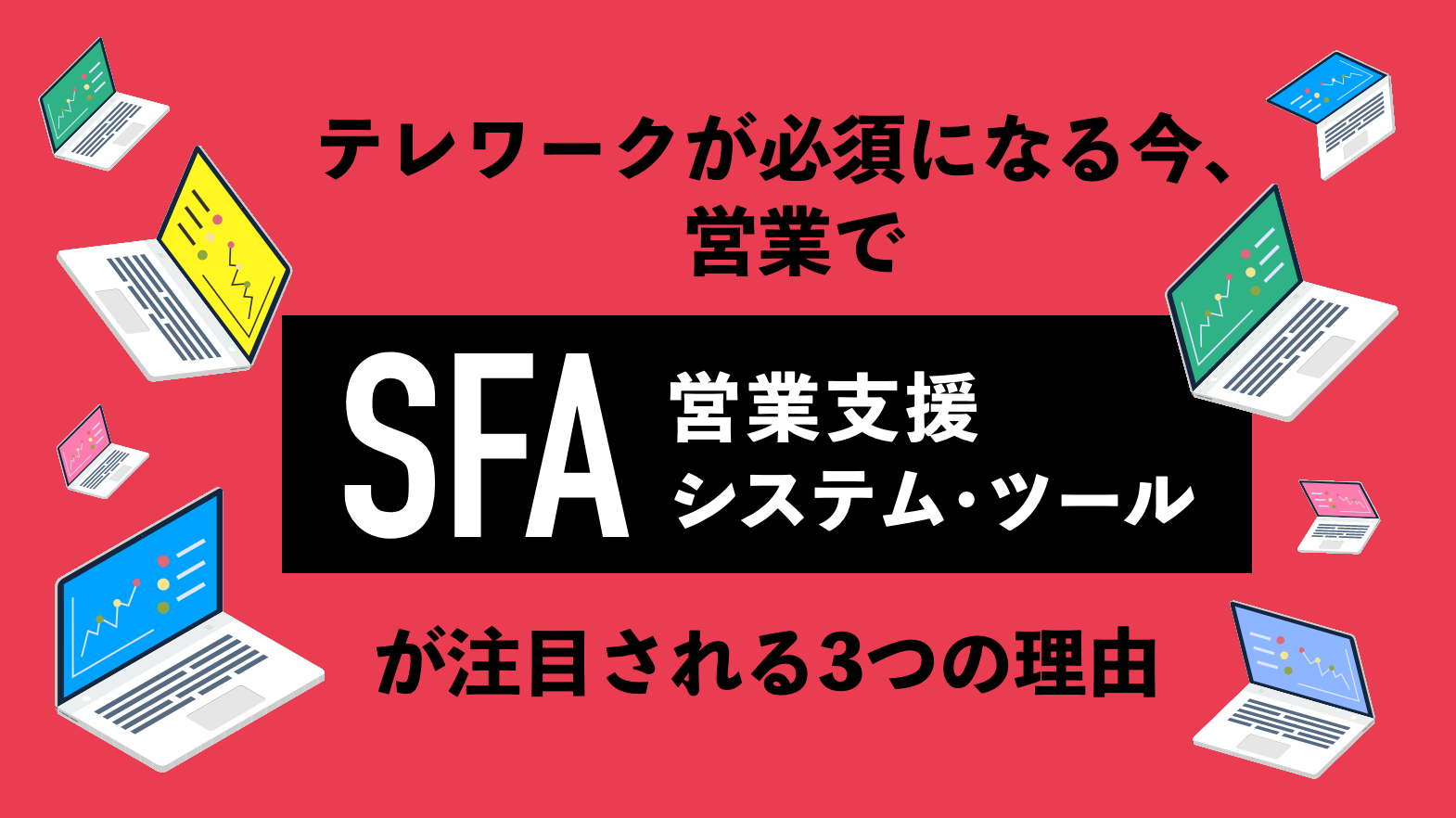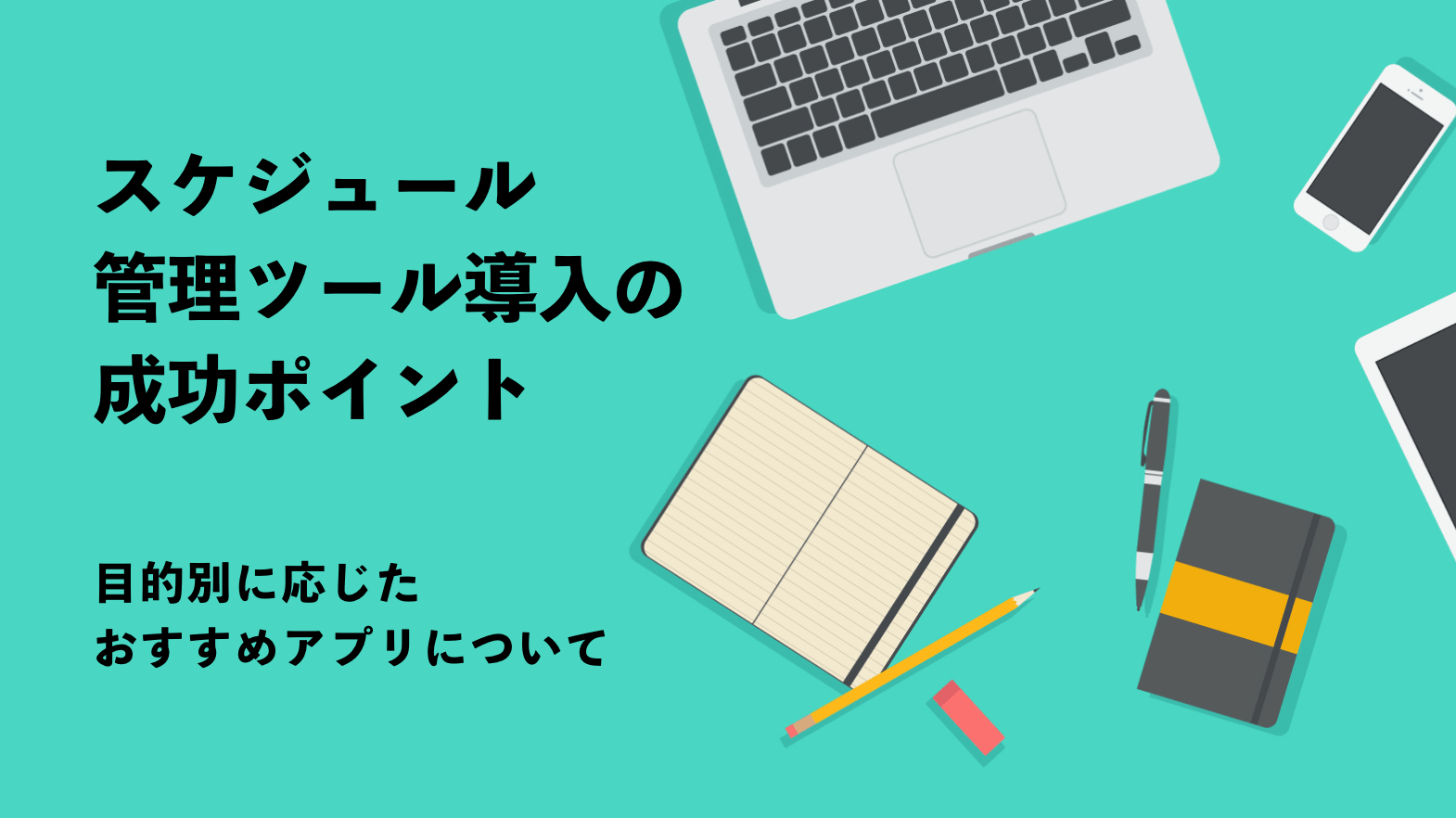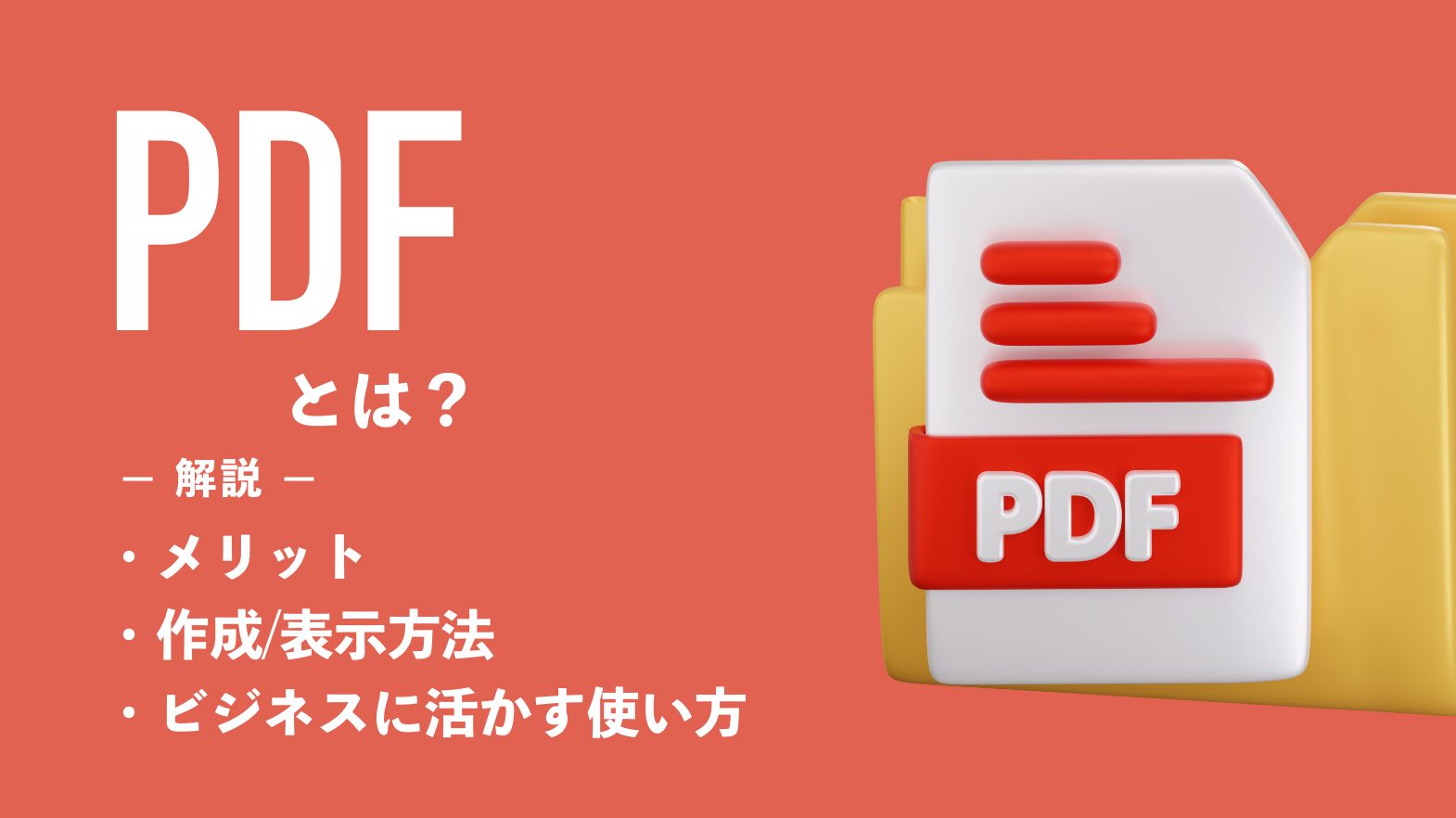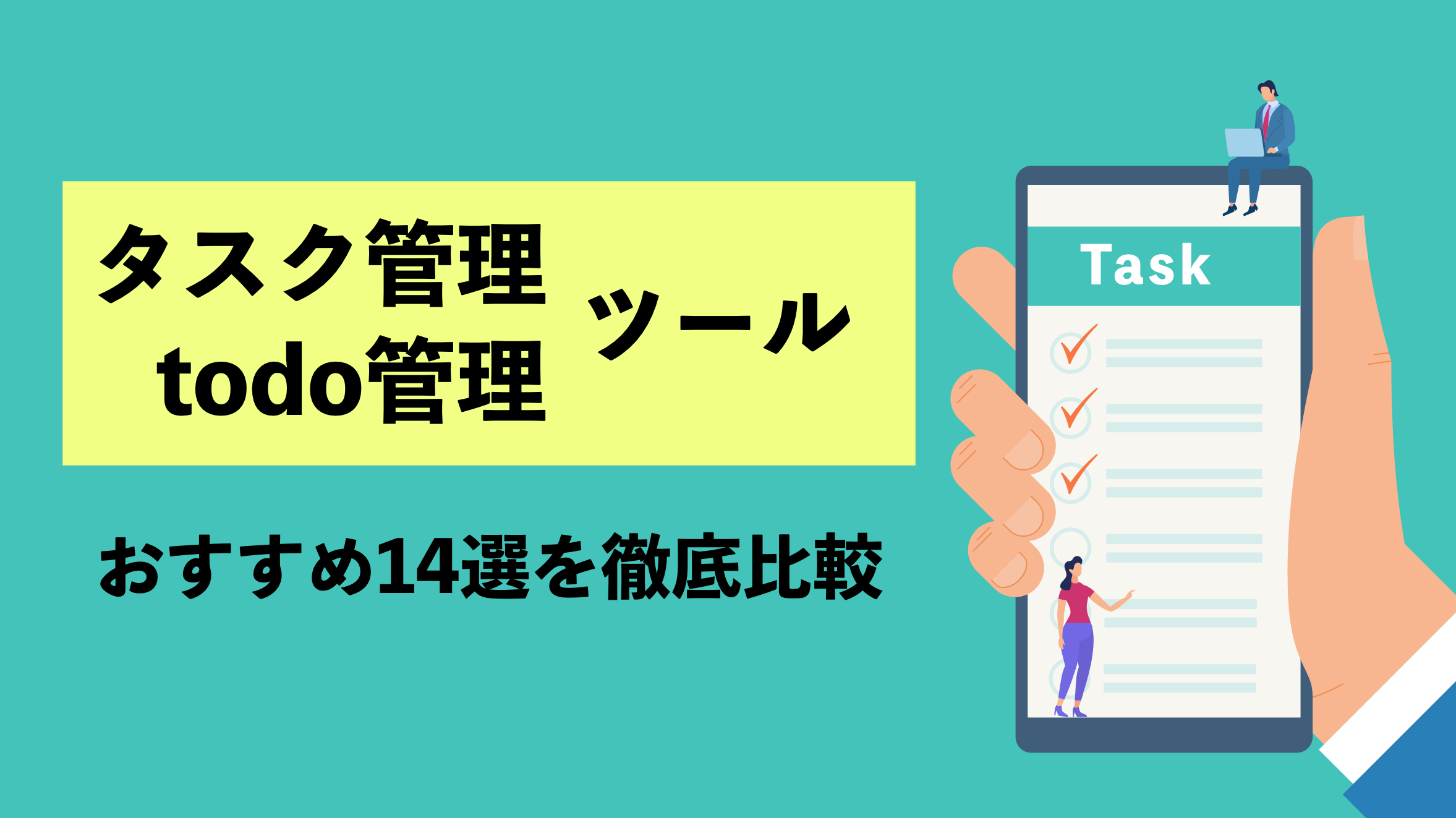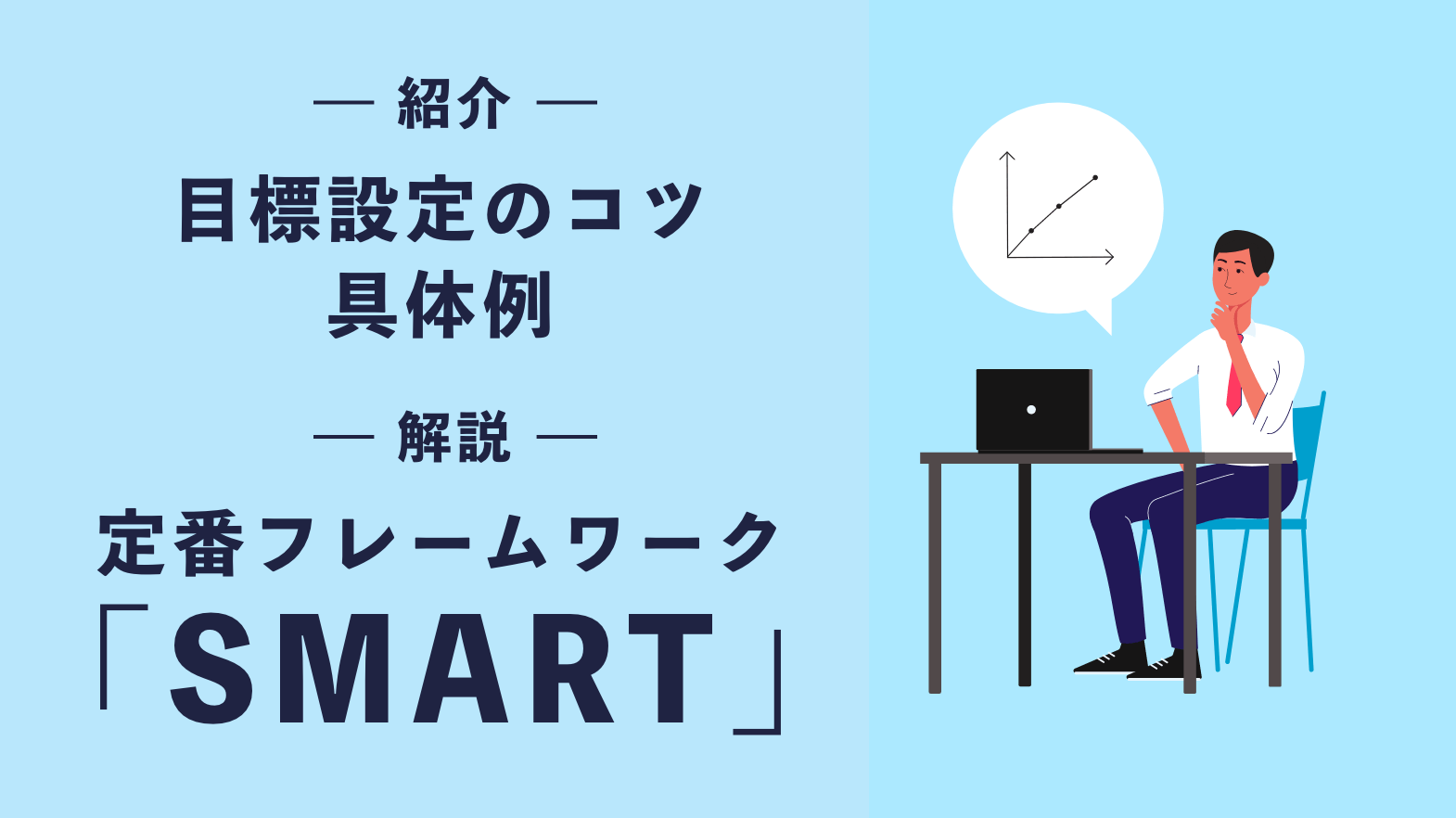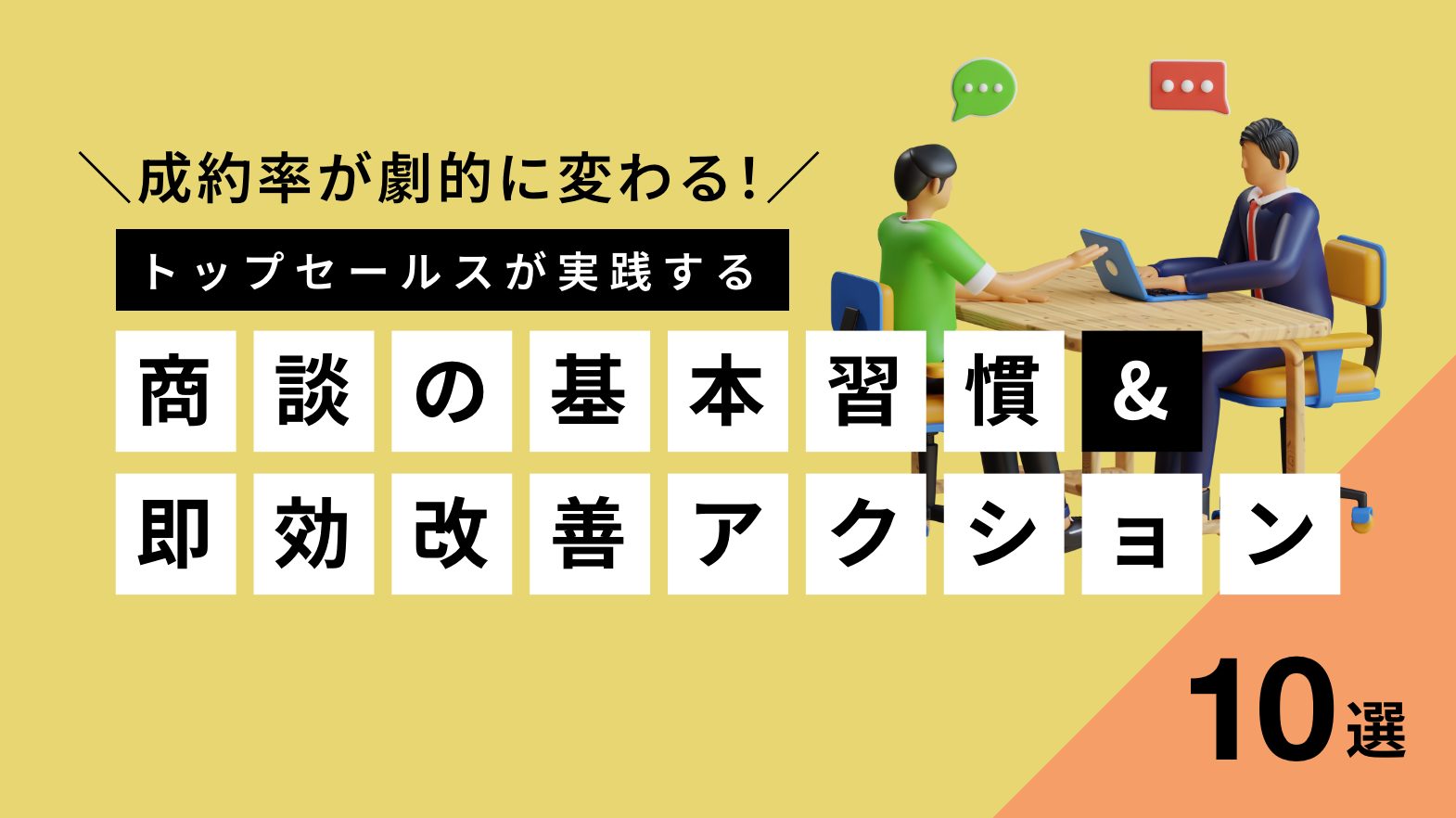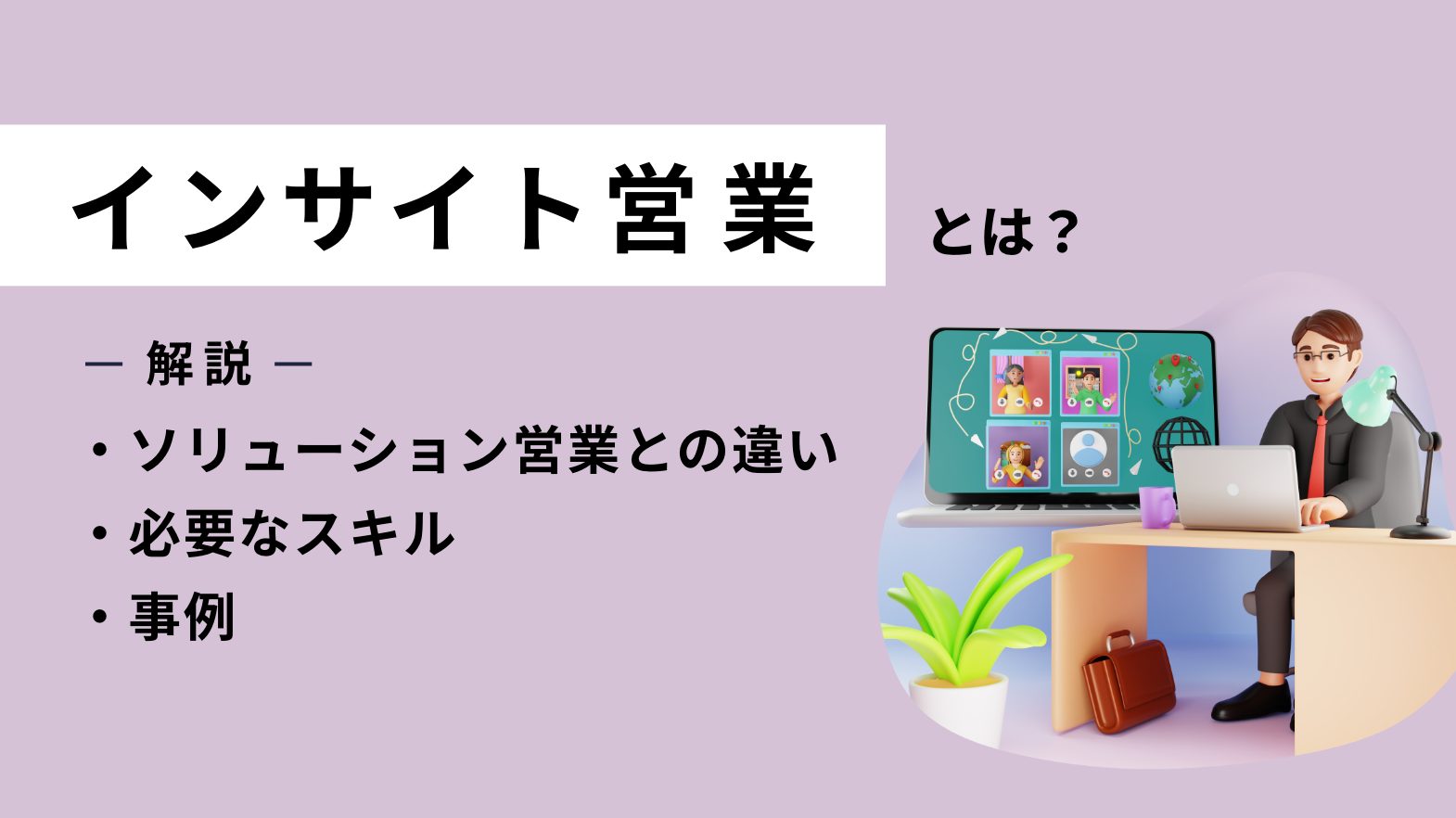【成功事例あり】生産性向上の取り組み9選! 成果をあげるポイントとステップを解説
日本の労働力人口が減少していく中で、企業は社員一人ひとりの生産性向上の取り組みに力をいれなくてはいけない時代がきています。
企業の生産性が上がれば、顧客だけでなく社員にもよい影響が与えられます。企業の成長によって給与アップやライフワークバランスの改善につながっていく可能性があるからです。
本記事は、生産性を向上させるために苦慮している企業に向けて、具体的な取り組みについて解説しています。
5~10年後も企業を存続させるには何からすればよいか、頭を悩ませている企業担当の方は、ぜひ参考にしてみてください。
このページのコンテンツ
生産性向上がうまくいかない理由とは? 取り組みの基本を解説
多くの企業が生産性向上に取り組んでいますが、達成できずにいる企業も少なくありません。
取り組み方法を間違ってしまうと、時間や労働力、予算などの投資(インプット)に対して成果(アウトプット)が上回らないため、思うような成果が出にくいでしょう。
生産性向上を実現するには、2つの考え方があります。
- インプットを増やし、それ以上にアウトプットを大きく増やす
- インプットを減らし、アウトプットを維持、あるいはいま以上に増やす
どちらの取り組みが適しているのかは、企業によって異なります。
企業の特徴や現状をしっかり把握したうえで、自社に合った生産性向上の方法を見つけましょう。
生産性向上で得られる6つのメリット
コスト削減
企業全体が生産性を向上できた場合に得られるメリットに、コスト削減があります。
たとえば、残業時間が削減できると、人件費や光熱費などのコストも同時に削減できるでしょう。社員規模の大きな企業であれば、それだけメリットも大きくなります。
削減できた分の予算は研修や教育面の強化に回したり、力をいれるべき事業への資源投資に回したりできます。その結果、さらに生産性向上へつながるでしょう。
人材不足の解消
社員の数を増やせなくても、一人ひとりの生産性を上げられれば、人材不足は解消に近づけます。
生産性向上の取り組みがうまく回り始めることで、売上額や粗利率が向上し、持続的な成果(アウトプット)を得られるでしょう。
競争力向上
生産性が向上し、少ない資源(インプット)に対して大きな成果(アウトプット)が出せれば、企業競争力の向上につなげられるメリットがあります。
その結果、企業価値が上がれば、新しいビジネスに挑戦したり、既存商品のバージョンアップも可能になり、あらたな資源(インプット)を確保できるでしょう。
その中で、自社独自のオリジナル商品を開発していければ、さらに競争力向上につながります。
顧客満足度向上
生産性向上によって、1つの製品を完成させるまでのムダな作業や工程を改善できれば、高品質な製品やサービスを届けられます。結果として、自分たちの製品やサービスを利用してくれる顧客の満足度向上につながるでしょう。
顧客満足度が向上すれば、自社製品やサービスが注目を浴び、社会的需要が拡大する可能性もあります。
ライフワークバランス改善
生産性向上によって売上や粗利率だけでなく、社員のライフワークバランスを改善できるのもメリットです。
休日出勤や残業時間の削減により、仕事とプライベートの切り替えがうまくできるようになります。近年、推進されている働き方改革の根底部分といえるでしょう。
新しい人材確保においても、ライフワークバランスは企業が重視しておきたい部分です。必要な時間で成果(アウトプット)を多く出せれば、昇給や昇格にもつながり、さらにライフワークバランスが充実します。
モチベーション維持
生産性と社員のモチベーションは密接につながっています。
ムダに感じられる業務や多すぎる残業は、社員のモチベーションをいちじるしく低下させます。ムダな業務や残業の削減によって社員の負担を軽減し、本当に必要な業務に集中できるようになれば、やりがいも感じられるようになるでしょう。
また、企業が生産性向上によって大きな成果(アウトプット)を得られれば、賞与などで社員に還元したり、有給が取りやすくしたりと、モチベーション維持の施策をとりやすくなります。
今後は人手不足により、ますます人材確保がむずかしくなっていきます。生産性向上の取り組みによる職場環境の改善で、社員一人ひとりのモチベーション維持を継続していきましょう。
生産性向上を実現する取り組み9選

ここでは、実際に生産性向上を実現するための取り組みについて解説します。
1.業務を可視化し課題を抽出する
現在の業務内容を全体的に俯瞰し、一つひとつを可視化していきます。
具体的には、業務に関わる社員同士が意見を出し合い、「ムリ・ムダ・ムラ」の3Mを洗い出していきます。
業務の流れや作業の工程は適切であるのか疑問を持ちながら、あらゆる視点から意見を出して課題の抽出作業をしましょう。
2.コア業務とノンコア業務を選別する
業務の可視化をしていくと、コア業務とノンコア業務が明確になります。
コア業務とノンコア業務とは、自分たちがやる必要のある業務と、やらなくていい業務のことです。やらなくていい業務は社員の負担軽減につながる可能性のある工程部分といえます。
ノンコア業務は必要に応じてアウトソーシング化することで、業務整理にもつながります。また、自社が苦手としている業務はアウトソーシングしたほうが効率よく回ることもあります。
アウトソーシング化や工程軽減できた分の人材と時間を本来のコア業務にあてられると、生産性向上につながります。
3.取り組み方を検討する
可視化によって、自社の注力すべき業務を明らかにしたら、実際に取り組む手法を決めて、動き出します。
以下の4つの手法から、自社に合うものを見つけていきましょう。
| インプット縮小型 | 投資資源(インプット)を減らしながら、生産量や付加価値額を維持して生産性向上を図る取り組み方 |
| インプット大幅縮小型 | ・インプット縮小型よりもさらに大幅に削減する方法 ・事業の見直し、リストラ、不採算部門の縮小・撤退・売却など、経営全体を見直す方法 |
| アウトプット拡大型 | ・投資資源は変えずに生産量や付加価値額の増加を目指す方法 ・デジタル化などで生産プロセスを変えて効率化を図ったり、従業員の教育によってスキルアップを図ったりする ・労働あたりの成果(アウトプット)の増加を狙う |
| アウトプット大幅拡大型 | ・投資資源(インプット)を増やしながら成果(アウトプット)を大幅に増やすことを目指す方法 ・生産性の高い主力事業に集中投資したり、新しい人材を採用してエリアを拡大したりして、大幅なインプット増を目指す |
大きく分類すると、インプット縮小型とアウトプット拡大型に分けられています。
自社の環境を考えた場合、どの手法が適しているか検討してみてください。そのうえで、生産性向上に向けて取り組んでいきましょう。
4.適切な人材配置を行う
社員の能力と業務内容がマッチングした適切な人材配置が、企業の生産性向上へと繋がっていきます。
社員一人ひとりについて、配置された場所で求められている品質や量のアウトプットが可能か確認しましょう。効果的に能力が発揮できれば、高いアウトプットが期待できます。
そのためには、社員一人ひとりの強みや希望を踏まえて選定するのが重要です。
5.社員のスキルアップを図る
社員一人ひとりの持つスキルを上げられると、将来的な生産性向上につながります。
たとえば、同じ時間で製品を作る際、ミスを減らしスピードが上がることで、生産量を増やしたり、2人で行っていた工程を1人でこなせるようになります。
企業全体が拡大していくためには、社員の成長が必要不可欠です。同じ作業を漫然とくり返すだけになっているとスキルアップはむずかしいので、定期的な研修やセミナーを開催していく取り組みが重要でしょう。
営業組織のメンバーのスキルアップを図るうえでは、「セールスイネーブルメント」という取り組みが近年注目を集めています。
6.社員のモチベーションを高める
社員のモチベーションを高めることは、生産性向上を実現させるために重要です。仕事に対するモチベーションが下がってしまうと、ダラダラと残業をして業務効率が低下したり、離職につながったりするからです。
また、昨今は柔軟な働き方を求める社員も増えているため、テレワークやフレックス勤務を積極的に取り入れるなど、業務効率アップや離職率を下げる工夫も重要になります。
たとえば、会議室に集まって行なっていた週に1度の定例会議をリモートに切り替えると、移動にかかっていた時間を他の業務にあてて効率よく働くことが可能です。
メリハリをつけた働き方の取り組みは、長期視点で社員のモチベーションを高め、生産性向上へとつながっていきます。
7.社員同士のコミュニケーションの機会を作る
いつでも気軽にミーティングできるスペースを設けたり、きっちりテーマを決めず会話を楽しむ時間を作ったりすることは、長期的視点で、生産性向上につながります。
社員一人ひとりのつながりが企業全体で大きな輪になると、助け合いや支え合いが生まれます。社員同士が気軽にコミュニケーションを作れるといった角度から、生産性向上へとつなげていきましょう。
8.ITツールを導入する
これからの時代、少子高齢化に向けて企業のITツール導入は必須です。人材確保のむずかしい環境下では、思いきってツールに任せることで生産量があがったり、ヒューマンエラーが減ったりします。
人力からITツールに少しずつ切り替えることで、長期的に生産性向上へと進んでいく企業もあります。ただし、人にしかできない業務ももちろんあるため、自社の環境や予算に合わせてITツール導入を検討してみてください。
9.業務をマニュアル化する
生産性向上のためには、属人化している業務をマニュアル化していく必要もあります。
ある業務を長く担当していた人が長期休養になったり、退職してしまったりすることは、どの企業でも起こりえることです。
特定の社員しか把握していない作業があると、他の社員が任された場合、業務効率や品質低下が起こる可能性があきらかです。
マニュアル化できる業務については早めに実施し、リスクヘッジを行っていきましょう。
生産性向上の成功事例3選
弊社では営業の生産性を向上させるツールを提供しています。成功事例も数多くありますので、ぜひ参考になさってください。
GMOメイクショップ株式会社様
SFAによる顧客情報の一元化で、売り上げは192%を達成、会議時間も大幅に短縮した事例です。顧客満足度の向上と「案件の取りこぼしゼロ」も達成されています。
詳細はこちらからご確認ください。
参考:CRM/SFA導入事例|GMOメイクショップ株式会社 様
株式会社ベネフィット・ワン様
SFA導入により受注が3.6倍、SFAのタイムライン機能で若手の育成も促進することができた事例です。若手の育成にも成功しています。
詳細はこちらからご確認ください。
参考:CRM/SFA導入事例|株式会社ベネフィット・ワン 様
メディキット株式会社様
製造業での事例で、営業のセルフマネジメントを促したケースです。
SFAを導入してから「いつ、誰と会うか」といった営業活動における情報が視覚的に把握できるようになりました。結果、営業担当者が自分で訪問先のバランス調整をするなど、セルフマネジメントができるように。
SFAの導入で、お客様を失わないようにこれからの営業活動を緻密に行いたい、という会社のニーズをかなえることができました。
詳細はこちらからご覧ください。
なお、生産性に課題があった事例一覧はこちらのリンク先にあります。御社の課題解決のために、よろしければ参考になさってください。
生産性向上の取り組みにおけるポイントと注意点

優先順位を明確にする
現状の業務の洗い出しを行い、取り組む内容が可視化できたら、優先順位を明確にしましょう。同じ目標に向かう場合でも、部署や個人ごとに役割があり、それぞれの考える優先順位が異なります。
目標達成までの優先順位を考えず、むやみに始めてしまうと、足並みが揃わなくなり、可視化した意味がなくなってしまいます。最短かつ効率的に成果を出すためには、優先順位を明確にしてから取り組むよう注意しましょう。
長期的視点で考える
生産性向上を目指した場合、短期的に成果につながることもありますが、ほとんどの場合はすぐには成果が見えてきません。なかなか成果が出ないため、「取り組んでいることに意味がない」と感じてしまう人もいるでしょう。
しかし、企業全体で現状を把握し、資産(インプット)に対して成果(アウトプット)を出すために、PDCA(Plan:計画、Do:実行、Check:評価、Action:改善)サイクルを何度も回しながら、少しずつ成長することが重要です。
さまざまなデータを蓄積させながら、慌てずに長期的視点で成果を出していきましょう。
企業の目標を見失わない
さまざまな視点から生産性向上の施策を行っていると、本来の目標を見失い、違う方向へ進んでしまうことがあります。取り組んでいる内容が企業の目標に正しく進んでいるか、定期的に確認しておきましょう。
万が一、進む方向がズレてしまっていると気がついた場合、取り組む手段や最初の「業務の洗い出し」が間違っている可能性があります。
間違った方向に進まないために、最初に企業の目標をしっかり把握して、洗い出しを行いましょう。
生産性向上の取り組みは現状確認から! メリットを出すためのポイントにも注目しよう
企業の生産性向上のために行う取り組みは、1つだけではうまくいきません。
業務の可視化やコア業務の選定、人材配置、社員のモチベーションなど、現状確認からしっかり行うことが重要です。
少子高齢化による人材不足は、企業が生き抜くための大きな課題であり、効率よく成果を出す手法が求められています。
いま取り組んでいる手法で成果が出ず悩んでいる企業は、ぜひ本記事を参考にして生産性向上のための取り組みを行ってみてください。