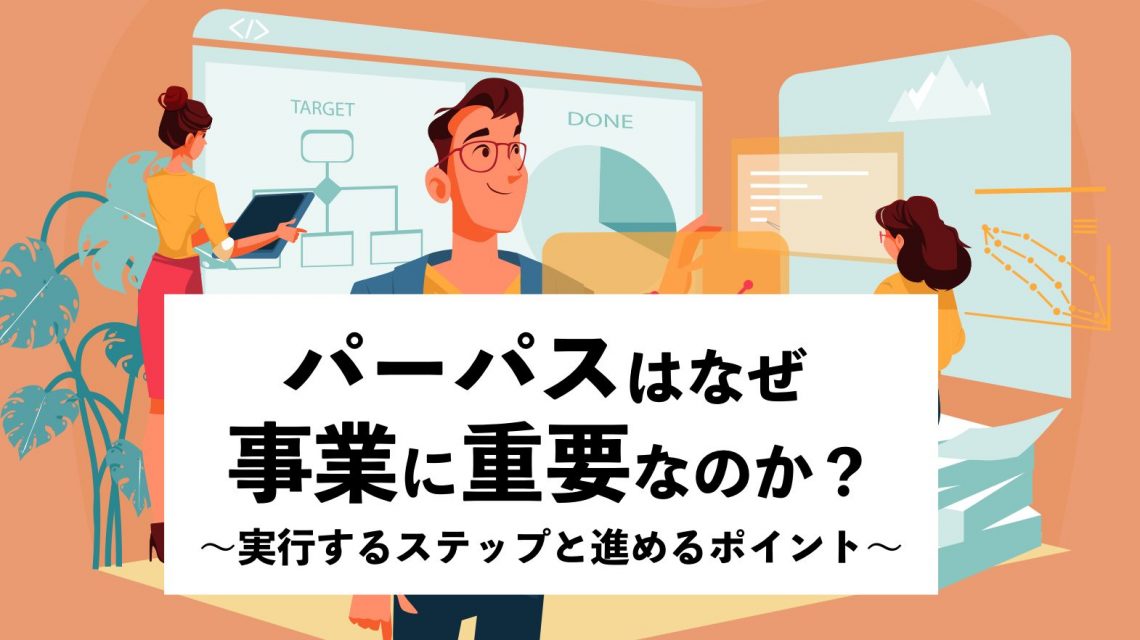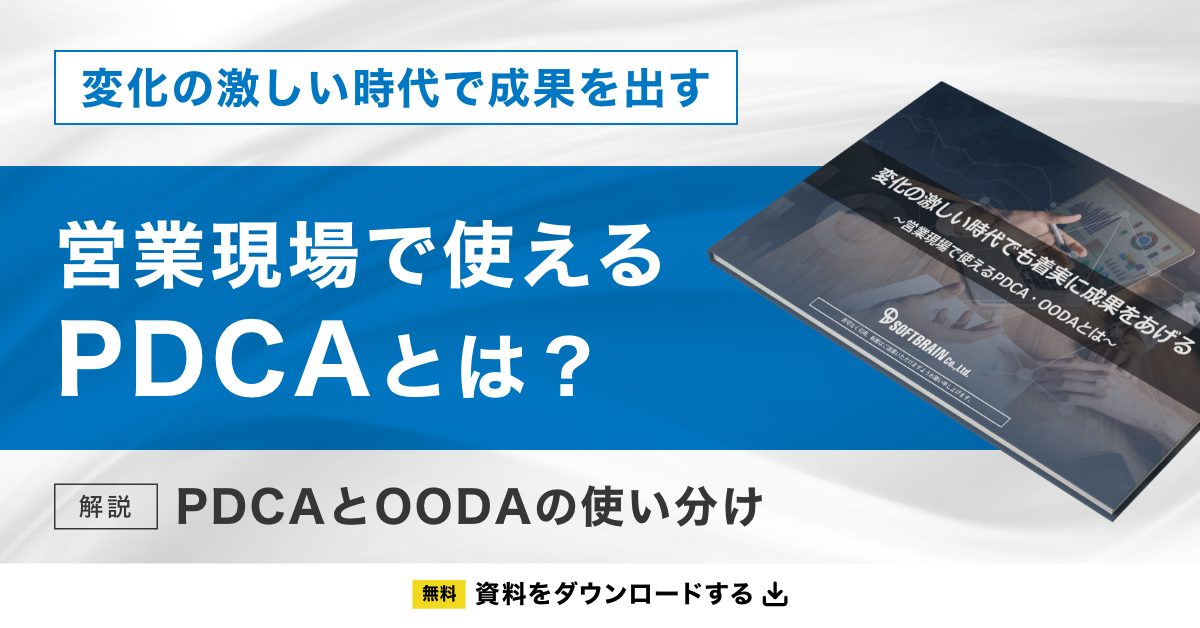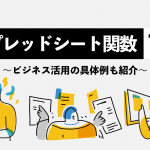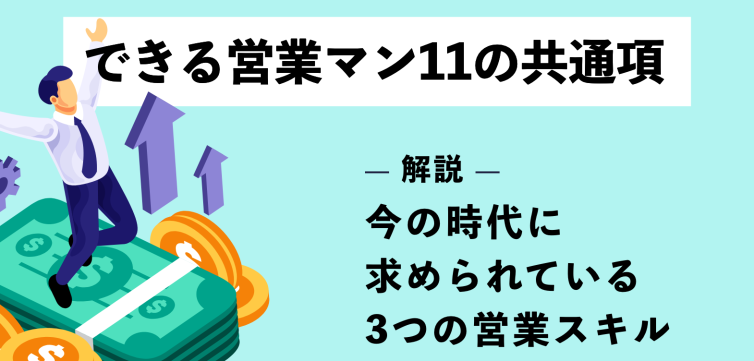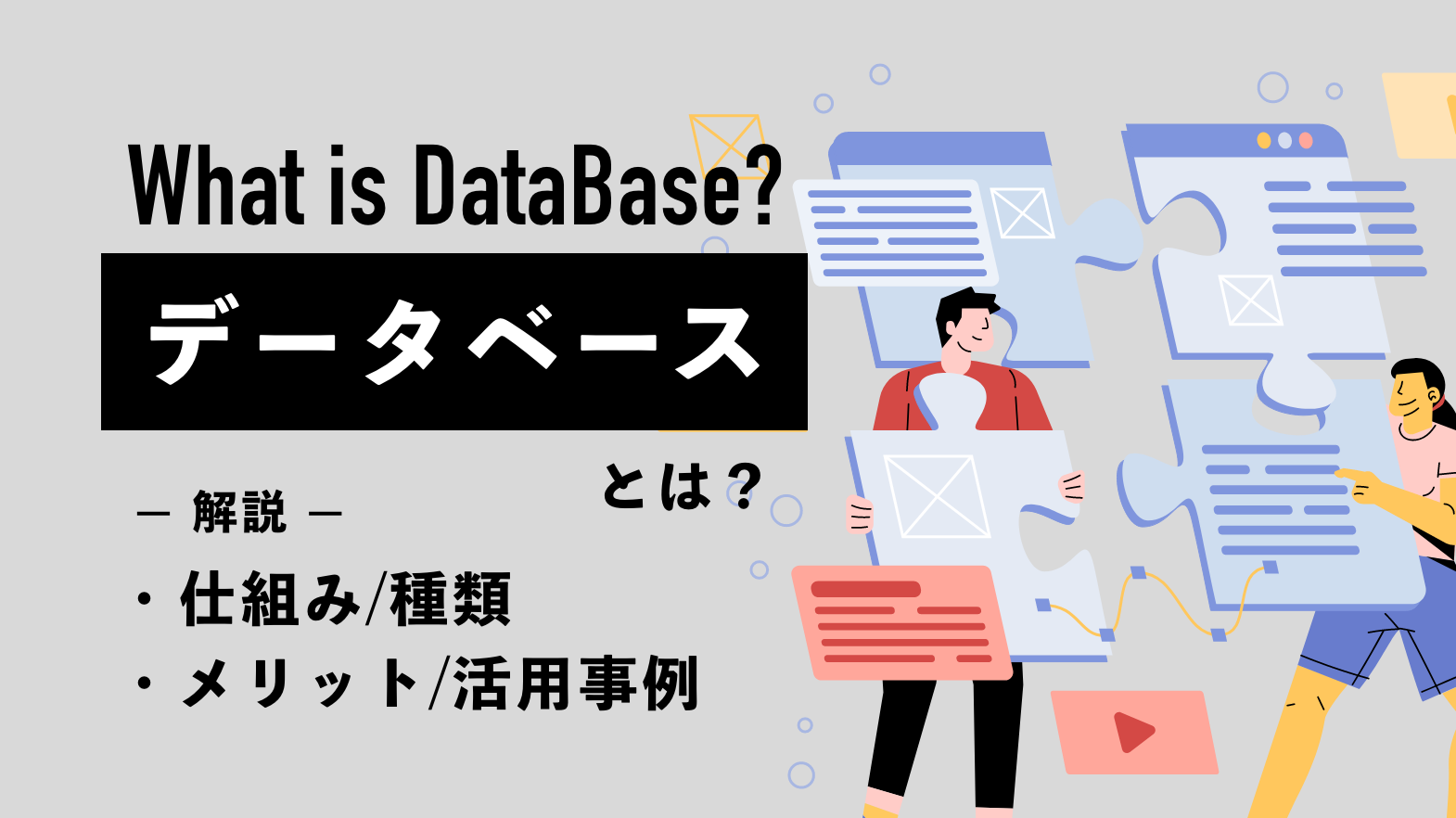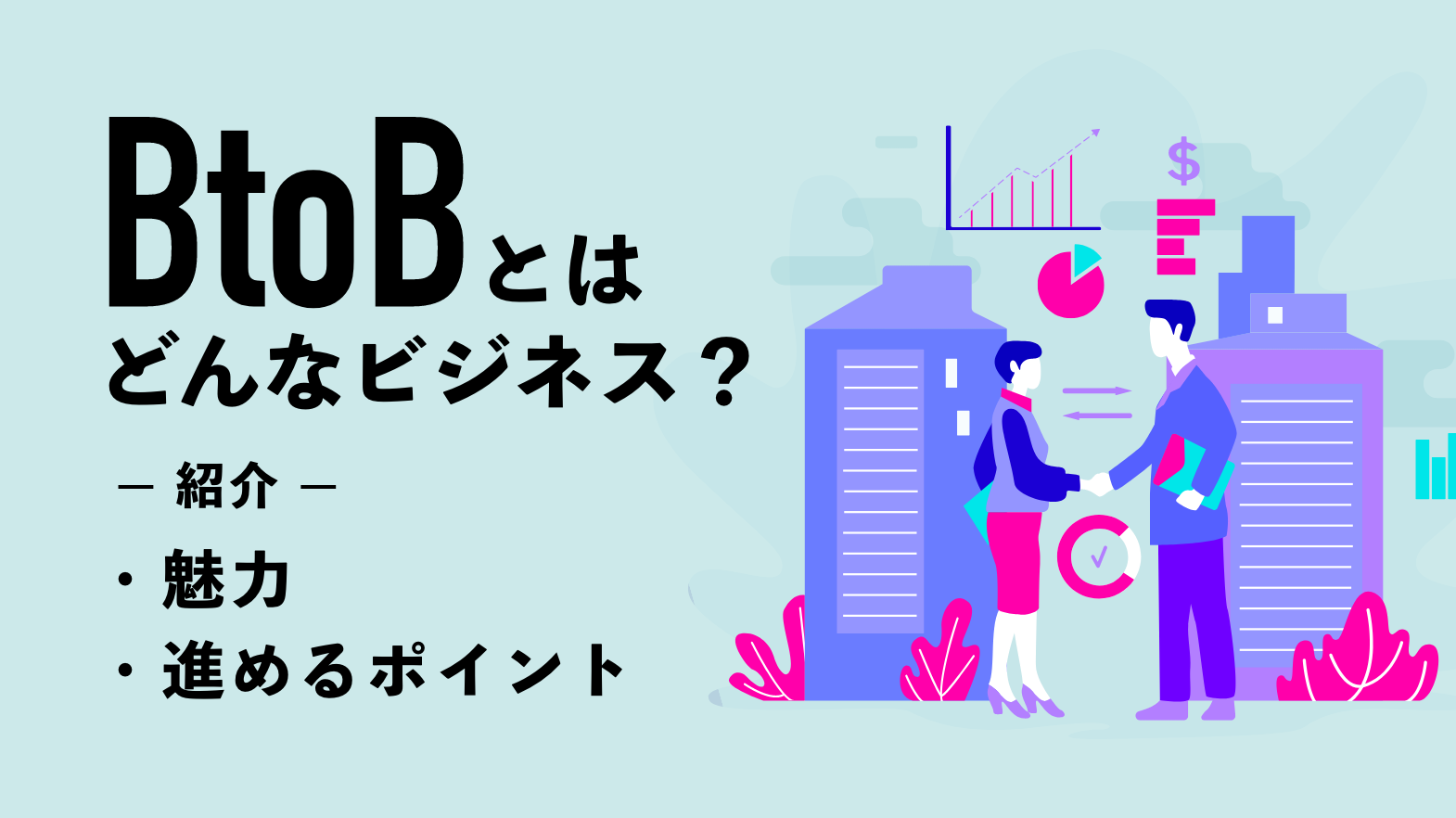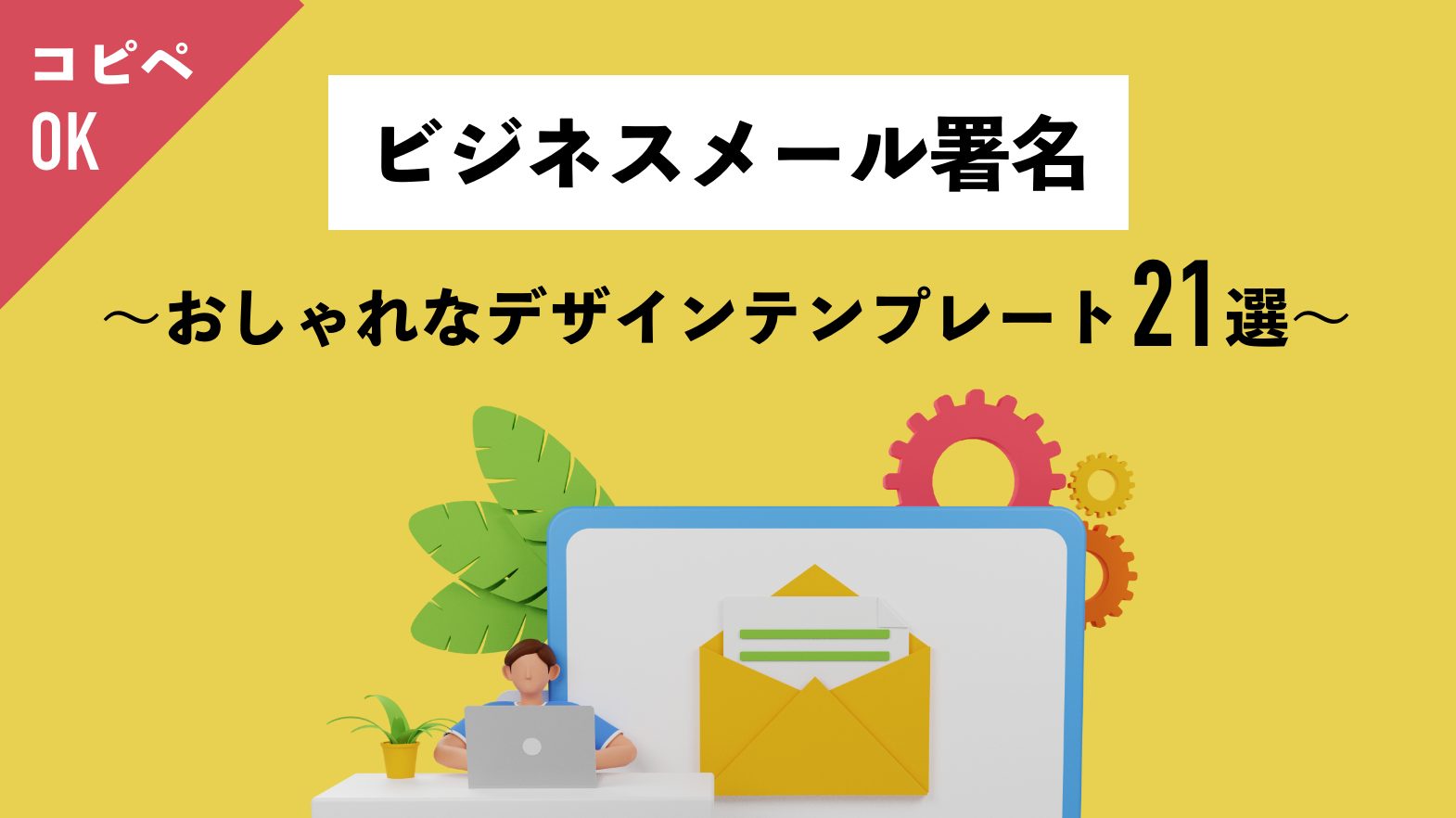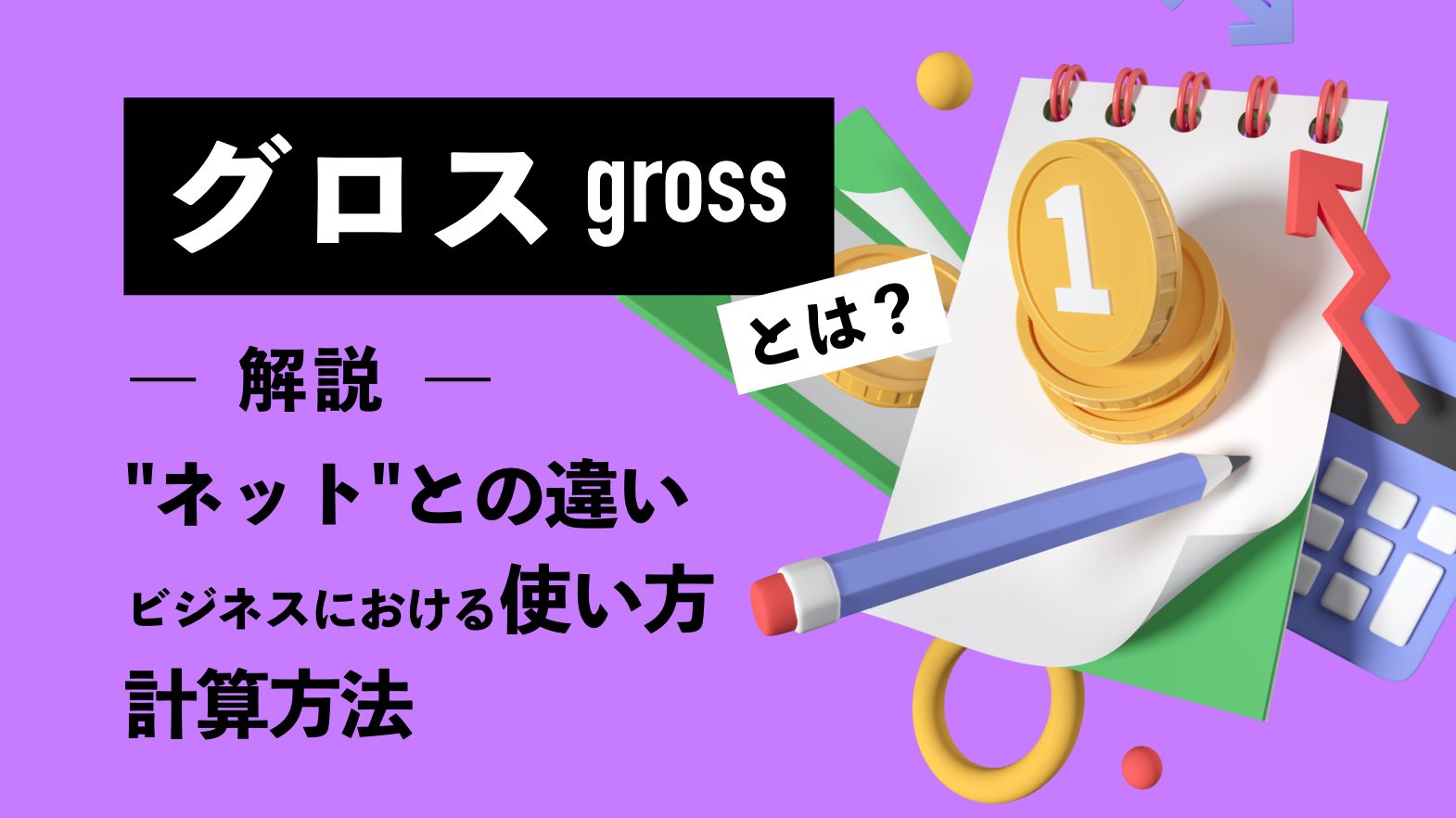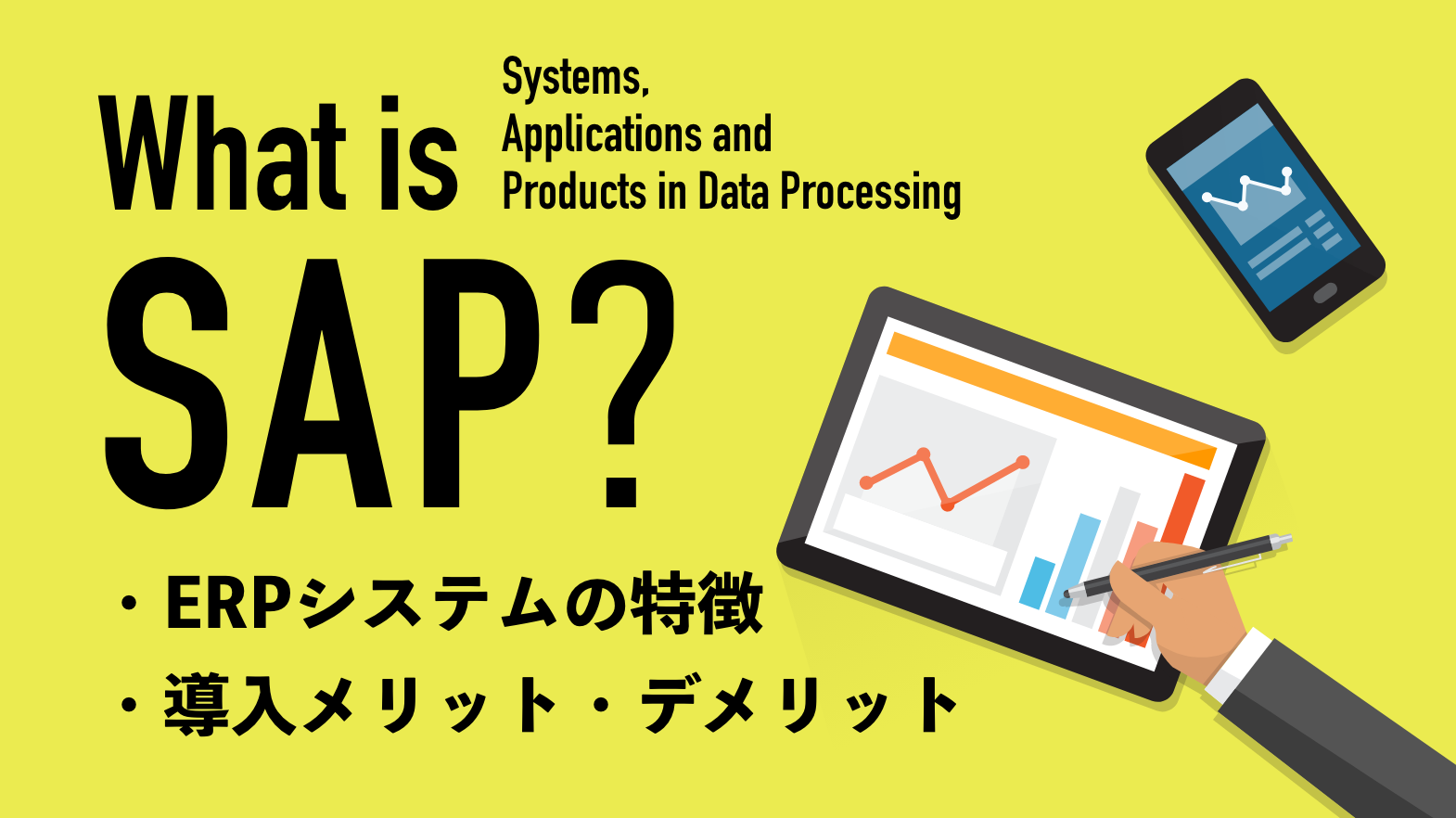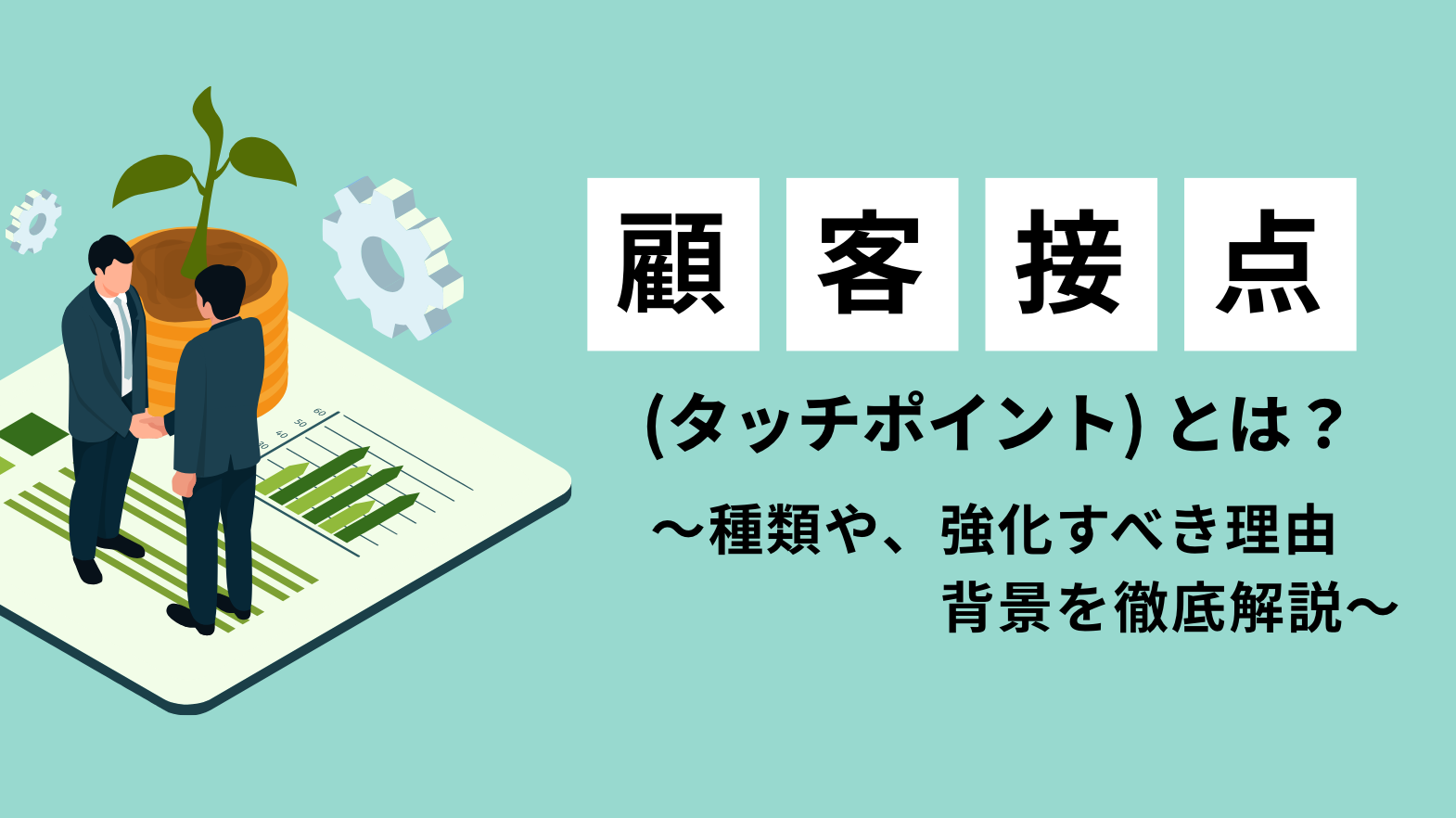パーパスはなぜ事業に重要なのか?実行するステップと進めるポイントを紹介
いま「パーパス」が、事業運営に重要なキーワードとして注目されています。「パーパス経営」は、代表的な用語に挙げられます。パーパスの意味を知り事業運営に活かすことで、従業員や顧客、社会からの支持を得られます。売上アップも実現でき、経営の安定にもつながるでしょう。
この記事ではパーパスの意味や事業運営に求められる理由に触れたのち、パーパスのメリットや実行するステップを解説します。記事をお読みになり、自社の信頼と業績のアップにつなげてください。
このページのコンテンツ
「パーパス」の意味はなにか?求められる理由も解説

そもそもパーパスは、どのような意味を持つ用語なのでしょうか。求められる理由や類似する用語との相違点も含めて、パーパスとはなにか確認していきましょう。
パーパスは企業の社会的意義や存在価値を示す
パーパスとは、企業の社会的意義や存在価値を示すビジネス用語です。
「わが社は社会において、何を成し遂げたいのか?」「わが社が社会に存在する目的はなにか?」への答えが、パーパスです。このため、パーパスは企業により異なり、企業の数だけパーパスが存在します。なかには、パーパスを「志」と解釈する企業もあります。
これからの企業は自社が存在すべき理由や社会における役割を明らかにしたうえで、社会の原理・原則に沿った方針の策定と事業運営が求められます。パーパスは正しい方向を指し示す道しるべとなるでしょう。
パーパスはなぜ企業に求められるのか?
パーパスが企業に求められる理由は、さまざまです。代表的な理由を、以下に挙げました。
| 理由 | 説明 |
| 将来を予測しにくい時代になった | 今はVUCA(ブーカ)と呼ばれる時代。変動性、不確実性、複雑性、曖昧性の特徴を持つ環境で、ビジネスを進める必要がある |
| 事業活動を通じた社会への貢献が必要 | 商品やサービスなど自社の得意分野を通じて、社会の発展や課題解決への寄与が求められる。市民も社会に貢献する企業を求めている。SDGsやサステナビリティ経営は代表的 |
| 優秀な従業員を集める必要がある | 求人へ応募する際に、適切なパーパスを掲げているかは応募先を選ぶ重要な判断基準の一つ |
企業が発展し続けるために、また、人材を確保し社会から評価されるために、パーパスは重要な役割を果たしています。
パーパスと類似する用語との相違点
事業運営の方向を決めるよりどころには、パーパス以外にも複数の用語があります。よく使われる用語との相違点を、以下にまとめました。
| 用語 | パーパスとの相違点 |
| MVV(ミッション・ビジョン・バリュー) | MVVは社内の関係者と取引先が満足すれば足りる。パーパスには社会で果たすべき役割も記す必要がある |
| 経営理念・企業理念 | 経営理念や企業理念には社会的意義を含める必要が無いが、パーパスには必要 |
| クレド | クレドは個々の従業員が行動すべき指針を示す。パーパスは企業にフォーカスし、企業の存在意義を示す |
パーパスとの違いをよく把握したうえで、適切な用語を選んで活用してください。
「パーパス」がついた用語は実務で多数使われる
パーパスはさまざまな用語と組み合わせ、ビジネスで使われています。代表的な用語を意味とともに、以下の表にまとめました。
| 用語 | 意味 |
| パーパス経営 | パーパスに則った経営を行うこと。社会とのかかわりを強く意識した方針になりやすい |
| パーパスステートメント | パーパスを言葉で可視化した文章や語句。自社のパーパスを共有・発信する目的で使われる |
| パーパスドリブン | 自社に関するあらゆる物事が、パーパスをもとに行われる状態 |
| パーパスブランディング | パーパスをブランディングにつなげる手法。認知度のアップにより、自社の中長期的な利益につながる |
目的にマッチした用語を選び実践することは、自社のビジネスを推進する原動力となります。
パーパスを意識した事業運営で得られる4つのメリット
自社の事業運営でパーパスを意識することにより、4つのメリットが得られます。いずれも、企業の価値向上につながる項目です。メリットの内容を、順に確認していきましょう。
顧客や取引先の信用を得やすくなり、企業イメージもアップする
パーパスはその性質上、社会にプラスの効果をもたらす内容となります。パーパスを重視すれば、道義的な事業運営を行えるでしょう。
この結果、“善良な企業”という評価を得られるでしょう。自社のイメージがアップし、顧客や取引先の信用も得やすくなることは大きなメリットの一つです。
従業員は誇りを持って日々の業務に臨める
パーパスは、仕事が社会の役に立っていることを示す言葉です。従業員は誇りを持って、日々の仕事に臨めるでしょう。「私の仕事はどのように役立っているのだろうか?」と悩む必要はありません。
社会貢献できる企業で働けば、モチベーションやロイヤルティ、エンゲージメントが高まり、組織への愛着心も感じやすくなるでしょう。勤続年数のアップや離職率の低下、よりよい人材を確保しやすくなることも、期待できる効果の一つです。
よりよい業務につながる提案が増える
パーパスを意識した事業運営は、従業員の当事者意識も促します。業務を自分ごととして捉え、問題意識を持って能動的に取り組む従業員が増えるでしょう。
従業員の意識が「仕事をやらされている」から「よりよい仕事をしたい」に変われば、業務の問題点が積極的にあぶり出されます。パーパスをもとにした、よりよい業務につながる提案も増え、生産性もアップするでしょう。
口うるさく指示しなくても効率よく業務が進むという、理想的な結果も期待できます。
投資対象として選ばれやすくなる
社会課題を解決する企業は、投資の分野でも注目されています。以下に該当する企業は株価の上昇が期待でき、投資対象として選ばれやすくなるでしょう。
- 掲げたパーパスの社会的意義が大きい
- 社会にプラスの影響をもたらした実績がある
- 今後の成長が期待できる
社会的な課題と経済的な利益を同時に追求する「インパクト投資」や、環境・社会・ガバナンスを考慮し投資する「ESG投資」では、パーパスが重視されやすいでしょう。
パーパスを定めて実行する4つのステップ
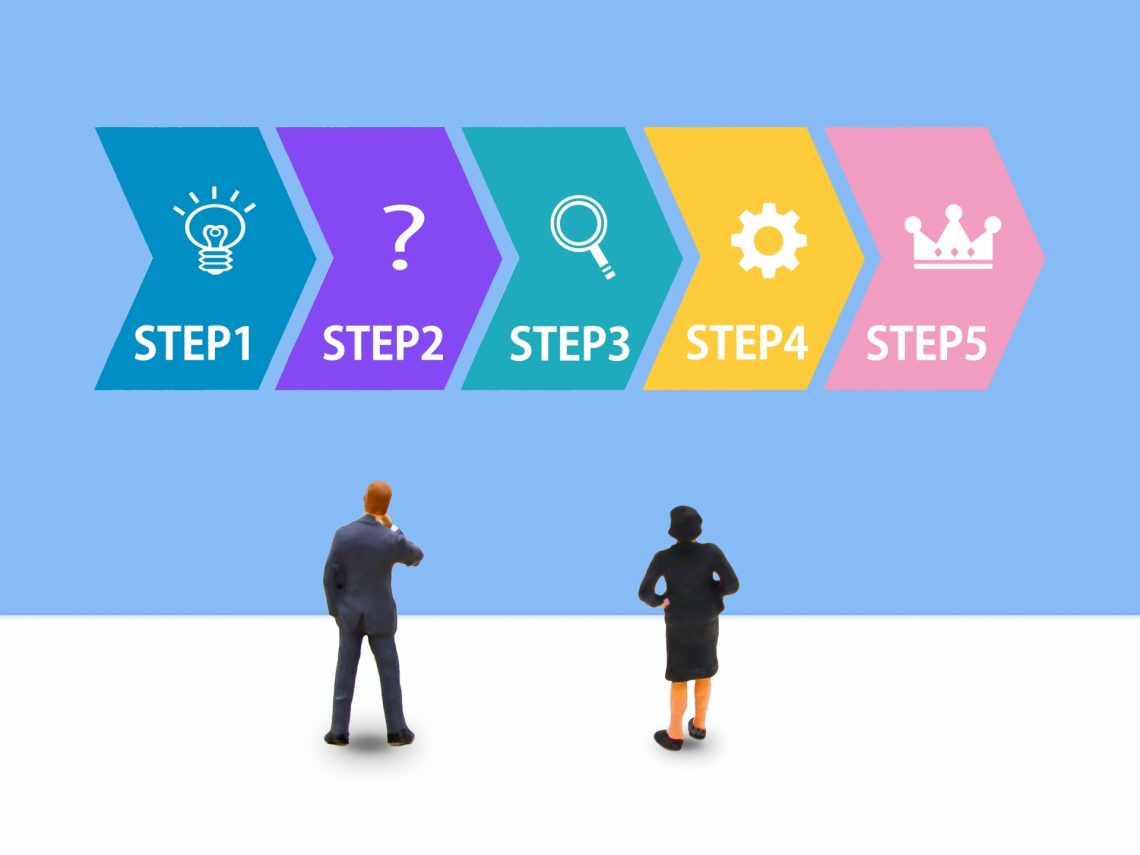
企業の成長につながるパーパスは、正しい手順で作成することが重要です。4つのステップごとに、何をすべきか確認していきましょう。
自社のあるべき姿や目標、ビジョンを定める
パーパスは、企業の社会的意義や存在価値を示します。前提として、自社のあるべき姿や目標、ビジョンを定めていなければなりません。自社が進むべき方向が見えていてこそ、正しいパーパスを定められます。
「とにかくパーパスだけは決めておきたい」と考える経営者様もいるかもしれません。しかし進むべき方向を決めていない状況は、土台がぐらついた家のようなものです。このような状況では、いくら立派なパーパスを定めても意味がありません。
パーパスに含める要素をピックアップする
自社のめざす姿は、いくつかの言葉や文章に分けられるでしょう。そのなかからパーパスにふさわしい語句をピックアップしてください。
社会的意義のある語句を選ぶことは必須です。事業環境やステークホルダーの要望などを考慮しつつ、具体的な、またはひとめで意味がわかる語句を選ぶとよいでしょう。
シンプルでわかりやすい文言にまとめる
パーパスは自社が目指すところを、外部の人々に広く示す文章です。このため、誰でも理解できる文章が好まれます。シンプルでわかりやすく、誰が見ても同じように伝わる文章にまとめましょう。
定めたパーパスが適切か評価する
パーパスを定めたら社内に周知し、実行しましょう。経営トップがみずからパーパスを意識した行動を取ると、社内に浸透しやすいでしょう。
パーパスを実行しても、意図した結果を得られるとは限りません。結果を評価し、定めたパーパスが適切か評価することが重要です。よい結果を得た場合はさらに高い効果を得る方法を、意図した結果でなかった場合は改善する方法を考えましょう。
パーパスを定めるうえで意識したい4つのポイント
パーパスを定める際には、意識して押さえておきたいポイントが4つあります。各項目がなぜ重要か、理由も含めて解説します。事業運営に活かせるパーパスの作成にお役立てください。
自社のビジネスと社会課題の解決をリンクする
パーパスには社会での存在意義が記されるため、パーパスを重視する企業には社会課題の解決が求められます。これらは、自社のビジネスと関連することが重要です。パーパスを定める際には自社の強みを活かし、ビジネスと社会課題の解決をリンクする必要があります。
自社の利益につながる内容を定める
いくら社会貢献が必要であっても、企業は営利事業です。成果をあげ利益を確保しなければ、事業を継続できません。
自社の事業で社会貢献しながら、適正な利益も確保できる内容を定めましょう。「自社も儲かり、社会も良くなる」事業であればWin-Winとなるためベストです。
パーパスの策定は経営層から一般の従業員まで全社で取り組む
人は少々、無理があっても、みずからで決めたことには一生懸命に取り組むものです。パーパスをもとにした行動を実現するために、経営層だけでなく多くの従業員がパーパスに関心を持ち、策定に関わる機会を設けることは有効です。
現場の意見を反映できるとともに、全員が当事者意識を持てるためパーパスの実効性を高められるメリットは見逃せません。
定める・掲げるだけでは効果無し、常にパーパスを意識した行動を
立派なパーパスを定めて公表しても、それだけでは利益につながらず、社会も良くなりません。パーパスを結果につなげるためには、常にパーパスを意識した行動が求められます。企業のトップから新入社員まで、パーパスを日々の業務で実践しましょう。
パーパスにもとづいた行動はときに困難となるかもしれませんが、安易に白旗をあげてはいけません。パーパスと実態が異なることは「パーパス・ウォッシュ」と呼ばれ、従業員やステークホルダー、社会の評価を下げる原因となります。
パーパスは定める・掲げるだけでは効果が無く、パーパスにもとづいた行動が大切です。
パーパスにもとづいた事業運営で、企業価値の向上を目指そう
パーパスは適切に定め実行することにより、社会やステークホルダーの要望にかなう事業運営を行えます。働きがいのある職場となり、貴社で働くことを誇りに思う従業員も増えるでしょう。
パーパスの実行とあわせ、現代を生き抜く組織には「DX推進」も求められています。自社の評判やブランドイメージを向上させるきっかけにもなるため、パーパスにもとづいた事業運営を目指しつつ、DXの推進も同時進行で検討しましょう。